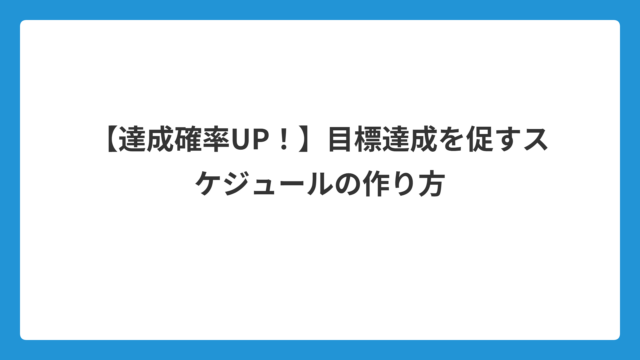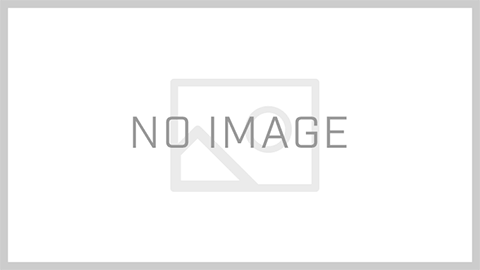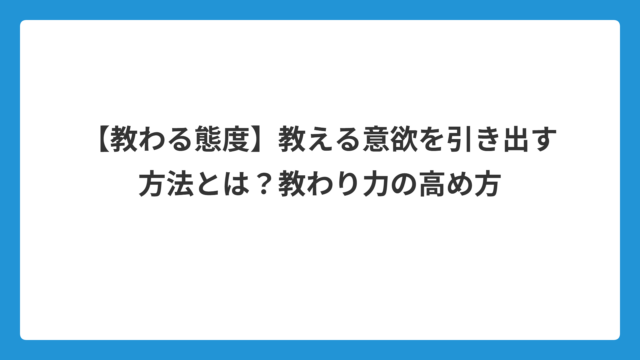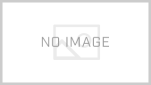できると思える挑戦でないと、私たちのやる気は出てくれません。
どれほど重要な挑戦であろうと、失敗が確実なら全力を出す気がなくなってしまうものです。
そのため、挑戦するときはできると思える感覚、すなわち自己効力感が重要になります。
この記事では、自己効力感を高める方法についてお伝えしていきます。
できないだろうという自信のなさを解決したいときは、ここで紹介する方法を取り入れてみてください。
自己効力感とは
自己効力感とは、1977年にカナダの心理学者であるアルバート・バンデューラが提唱した概念です。
「ある目標に対して自分が求める結果を出せるだろうという確信の程度」のことを指します。
自己効力感が高いほど「自分の力で状況を乗り越えらえる」「人生を自力で作っていける」という感覚により、次の傾向が強まります。
- 新しい挑戦に積極的になる
- タスクへのモチベーションが高まる
- 困難な課題に取り組む意欲と粘り強さが高まる
- ストレスやプレッシャーなどを効果的に対処できる
出典:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jans1981/20/2/20_39/_article/-char/ja/
自己効力感と自己肯定感の違い
自己効力感と自己肯定感は、次のように異なる概念です。
- 自己効力感:課題に対する自分の能力への信頼感
- 自己肯定感:自分の存在そのものを肯定する感覚
自己肯定感が土台にあることで、本心による目標に挑戦できるようになります。
自己効力感を高めるときは、自己肯定感の度合いもチェックするようにしてみてください。
- 自己肯定感(低)×自己効力感(高):自己証明が目的の目標を設定しやすい
- 自己肯定感(高)×自己効力感(高):自己実現が目的の目標を設定しやすい
★自己肯定感が低いことによる弊害
自己肯定感が低いと、挑戦には高い自己効力感が必要になり、努力する方向性も間違えやすくなります。
自己を肯定するためにも、他人からの高評価を確実に得られることを重要視するためです。
挑戦することへの不安を感じたら、失敗したらどうなるのかを検討してみてください。
不安を生み出す原因が「他人からの評価」ならば、自己効力感よりも自己肯定感の改善こそが必要なのかもしれません。

挑戦に欠かせない2つの自己効力感
何かに挑戦するとき、必要な自己効力感は2つに分けられます。
自己効力感を高めるときは、以下の2つのうちどちらを高める必要があるのかを検討してみてください。
- 現在に対する自己効力感:今の私ならできるだろう
- 未来に対する自己効力感:私ならできるようになるだろう
種類①:現在に対する自己効力感
現在に対する自己効力感とは、「私は現状のままで欲しい結果を得られるだろう」という確信です。
もう準備する時間がなく、あとは実行するだけという場合に求められます。
★現在に対する自己効力感が必要な例
・これから試験に望むとき:私なら合格するだろう
・起業アイデアを実現するとき:私ならアイデアを実現できるだろう
・今日の昼からプレゼン発表をするとき:私ならプレゼンに成功するだろう
何かに挑戦しようと考えたとき、私たちはまず「今の私ならそれができるか?」を検討します。
このときに自己効力感が高いほど、挑戦意欲が高まりやすい傾向があります。
- 自己効力感が高い:できるからやってみよう!
- 自己効力感が低い:どうせ失敗するからやめておこう
★現在に対する自己効力感とパフォーマンス
「この挑戦には失敗する」と確信しているとき、それでもパフォーマンスを上げるには目的をすり替えることが有効です。
成長や爪跡を残すことなどを目的にすることで、「できるorできない」ではなく「やるorやらない」の問題に変わります。
結果へのプレッシャーが取り払われ、むしろ十分な力を発揮できることもあるでしょう。
・成長:負けるとしてもこの機会を十分に活用しよう
・爪跡を残す:どうせ負けるとしても自分のことを相手の記憶に刻んでやる

種類②:未来に対する自己効力感
未来に対する自己効力感とは、「努力すれば欲しい結果を得られるだろう」という確信です。
今すぐ成功できないような、遠い目標を達成しようとするときに求められます。
★未来に対する自己効力感が必要な例
・東大を受験すると決めるとき:2年間死ぬほどがんばればなんとかなるだろう
・年商1千万円を稼ぐと決めるとき:思考錯誤すればそのうち成功できるだろう
現在に対する自己効力感が低いからといって、かならずしも挑戦を諦めるわけではありません。
「今はできなくとも将来的にはできるようになるかもしれない」と未来への可能性を信じられれば、困難であっても挑戦する意欲が生まれます。
今の自分には難しいと感じたら、それは「成長した未来の自分」も対象なのかを検討してみてください。
「成功できる自分に成長できるのか」と、自分の可能性に目を向けることがポイントです。
★自己効力感を切り替えるコツ
「現在できないことは未来もできないだろう」と直感的に考えやすい傾向があります。
そのため、「今の私にはできない」と感じたら「未来の私ならどうだろう」と意図的に意識を切り替えることが重要です。
自己効力感を切り替えるコツは、「今の自分」と「未来の自分」を分けて考えることです。
以下のような「現在から未来に費やすリソース」を明確にすることは、この切り分けに役立つでしょう。
・時間:1000時間努力した私ならできそうかな?
・努力内容:このカリキュラムを終えたらできそうかな?
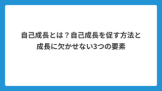
現在に対する自己効力感を高めるポイント
ここでは、「今の私ならできる」という感覚を持つためのポイントをお伝えしていきます。
本番①:能力があるか?
成功するに足る能力があると実感するとき、私たちは自己効力感が高まりやすいです。
能力とは「〇〇があるから私は成功するだろう」という根拠のことであり、知識や経験、スキルやセンスなどが該当します。
- 知識:知っているからできるだろう
- 経験:やったことがあるからできるだろう
- スキル:培った技術力やスペックがあるから上手くいくだろう
- センス:才能や運があるから成功するだろう
失敗する可能性を高める根拠を数えると、自己効力感が低下していきます。
現在に対する自己効力感を高めるときは、成功できる可能性が高いと結論付けるための根拠を探してみてください。
★自信のなさ
失敗理由に焦点を当てていることで、自己効力感が下がります。
そのようなときは、次の2つの方法により自己効力感を高められることがあります。
・失敗理由を論理的に検討する
・失敗理由ではなく成功理由に焦点を当てる
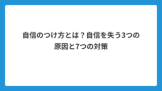
本番②:成功を歓迎できるか?
成功できる確信があっても、その結果への恐れがあると「できない理由探し」をおこなってしまいます。
目先の挑戦が成功するかを考えるとき、「その結果によって未来はよりよくなるのか」も併せて考えるためです。
★成功を歓迎できない例
・お金を稼げてもどうせ幸せにはなれないだろう
・告白には成功するがどうせすぐに振られるだろう
成功後の未来に対して悲観的だと、「総合的には失敗する」と結論付けて自己効力感が低下します。
成功後の未来が不安な場合は、「総合的な成功とは何か」「今できることは何か」などを検討してみてください。
★問題の混同
私たちは複数の問題を1つの問題として混同させてしまうことがあります。
・太っているから恋人ができない
・低学歴だからお金が手に入らない
このような状態では、思考が迷宮入りしてグルグルと失敗する未来ばかりを考えてしまいます。
以下のような方法で問題を切り分けて、問題を1つずつ解決することに専念してみてください。
・時間軸で分割する:過去/現在/未来で切り分ける
・願望と阻害要因で分割する:「欲しいもの」と「ボトルネック」で切り分ける

本番③:パフォーマンスを発揮できるか?
取り組もうとしている挑戦と類似した失敗体験を持つ人は、特に自身のパフォーマンスに疑問を持ち自己効力感が低下します。
「また同じように失敗するのではないだろうか」と疑心暗鬼になり、自信を失うためです。
能力があっても、かならずしも本番でパフォーマンスを発揮できるわけではありません。
状況によって発揮できる能力は左右されるため、「本番への弱さ」を痛感している人は自信を持つことが困難になるでしょう。
- 能力への自信:私はそれができるだろう
- その状況での自信:私はその状況でもそれができるだろう
★パフォーマンスを発揮できない例
・普段は喋れるのにプレゼンになると嚙んでしまう
・友達とは楽しめるのに親とはギクシャクしてしまう
・テレビだとクイズに答えられるのに出場したらダメダメだった
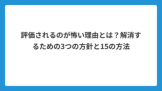
未来に対する自己効力感を高めるポイント
ここでは、「未来の私ならできる」という感覚を持つためのポイントをお伝えしていきます。
未来①:粘り強さがあるか?
遠くにある目標を達成しようとするとき、その道のりを歩み続ける必要があります。
人によって道のりのイメージはさまざまですが、困難な目標であるほど過酷なものを想像するでしょう。
★道のりにおける難易度の要素
・複雑さ:やることがたくさんある
・過激さ:難しくて大変なことをやらなきゃ
「イメージした道のりを自分は踏破できるだろう」という自信がなければ、未来に対する自己効力感が低下します。
未来の自分の可能性を信じるためにも、自分なりの継続するためのアイデアを身につけてみてください。
★コストVS利益
遠くにある目標を目指そうか悩んだとき、「必要なコスト」と「得られる利益」を私たちは天秤にかけます。
しかし、「やりたいorやりたくない」の気持ち次第で結果が変わり、たいていこの比較は失敗に終わります。
少しでも挑戦したいならば、まずは「得られる利益」だけを見て「やりたいorやりたくない」の意思決定をしてみてください。
もし「やりたい」を選んだならば、改めて「必要なコスト」を見ることで覚悟が決まり粘り強さが生まれるでしょう。
・「この目標は簡単な道のりだ」と思うと出発しやすいが粘り強さが低下する
・「この目標は険しい道のりだ」と思うと出発しづらいが粘り強さが向上する
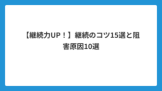
未来②:理想を叶えることを許せるか?
目標を達成して自分の理想を叶えることに、抵抗感を抱く人がいます。
「自分都合の目標達成は自己中心的だ」と捉えて、自分が幸せになることは許されないと感じる人です。
★理想の実現を否定する要素
・罪悪感:私だけ幸せになってはならない、他に優先すべきことがある
・他者評価:幸せになったら周りにバカにされる、嫉妬される
遠くの目標を達成することを許可できない限り、未来に対する自己効力感は高まりません。
夢や理想を実現することを許せないときは、まずはその許可取りから始めてみることをおすすめします。
★理想実現の許可取り
理想実現の許可取りでは、次の5つの方法が考えられます。
・否定する要素を取り除く
・最も贅沢な理想を描いてみる
・自分の欲望を叶えることに慣れていく
・「何を大切にしたいのか」と「何を大切にできるのか」を分類して明確にする
・「自己犠牲による他者貢献」ではなく「自己幸福のための他者貢献」を検討する
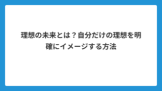
未来③:締切までに実現するリソースがあるか?
遠くの目標を達成するためのリソースが欠けていると感じると、未来に対する自己効力感は低下します。
★目標達成に必要な主なリソース
・才能:努力して成長できるか
・時間:その努力をする時間を作れるか
・環境:成功しやすい環境が整っているのか
・人脈:成功するためにたよれる人はいあるか
・資格:挑戦するために必要な資格を持っているか
・お金:その努力に必要なお金を支払う余裕があるか
ここで大切なのは「締切を守れるだろう」という確信です。
「100年頑張ればその目標は達成できるがそれでは意味がない」というように、締切を守らなければ結果による利益は失われます。
もし締切までに実現するリソースが不足している場合、取れる方法は主に次の3つから選ぶ必要があるでしょう。
- 諦める:挑戦しないと決める
- リソースを補填する:ないリソースを得るための行動をする
- リソースを工夫で補う:ないリソースを知恵や工夫でカバーする
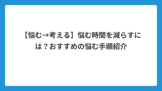
自己効力感を高める7つの方法
ここでは、自己効力感を高める方法についてお伝えしていきます。
方法①:成功体験
挑戦する内容と類似した成功体験を得ることで、それが根拠になり自己効力感が高まります。
★有効な成功体験
・現在に対する自己効力感:同じような挑戦に成功したことがある
・未来に対する自己効力感:同程度の困難を乗り越えたことがある、成長したことがある
成功体験を得るには、主に次の2つの方法が挙げられます。
- 成功体験を作る:小さな成功体験を積み重ねる
- 成功体験を思い出す:過去にある重要な成功体験を振り返る
「成功できるかもしれない」という可能性を見出すには、実際の進歩を実感することが重要です。
挑戦を難しいと感じさせている課題に対して、小さくてもよいので達成する成功体験を作ってみてください。
例.webライターで月商30万円を稼ぐ
1.可能性の予測:私は国語の授業が得意だったからライターで稼げそうだ
2.可能性の実感:実際に文字単価1円の記事を納品したら褒められた。これなら月商30万円を目指せるかも!
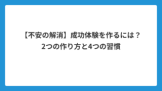
方法②:代理体験
代理体験とは、自分以外の人を観察することで得られる挑戦への成功を信じさせる根拠のことです。
見て学ぶことで成功する自分の姿をイメージしやすくなり、これなら私にもできそうだと感じられるようになります。
★代理体験の主な対象
・失敗者:何をして失敗したのか
・成功者:どういう過程で成功したのか
・架空の自分:自分の成功イメージ、現在から成功までの道のりを歩む自分の姿
効果的な代理体験は、自分のリソースと類似した対象を観察することで得られます。
メンターやロールモデルを見つけるときは、自分のリソースと似通った人を探すことが重要です。
★架空の自分による代理体験
計画立ては、この代理体験をするのに有効です。
計画を実行した架空の自分を想像することで、できそうか否かを判断できるためです。
自己効力感が低いときは、成功できると思えるような計画を探してみるのも1つの手になるでしょう。
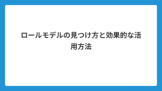
方法③:課題の調整
困難な課題であるほど、自己効力感が低下します。
ただし私たちは課題を適正に評価せずに、難しい課題や簡単な課題と思い込む傾向があります。
★課題の難易度に影響する要素
・締切:締切までの期間が短いほど難しい
・成功基準:高い品質を求めるほど難しい
・挑戦回数:挑戦できる回数が少ないほど難しい(失敗による損失が大きいほど挑戦回数は少ないと感じやすい)
課題が難しいと感じたら、挑もうとしている課題が本当にその難易度なのかを検討してみてください。
焦りや完璧主義は、課題の難易度を高いと感じさせる原因です。
★難易度を上げてしまう思考
・焦り:早く目標達成しなければと締切を短く捉える
・完璧主義:自分や他者からの期待が大きく成功基準が高いと認識する

方法④:自己の再評価
自己の再評価とは、自分の能力をもう一度客観的に捉えなおすことです。
「自分には無理だ」と感じていても、実は成功するための能力が十分に備わっていることがよくあります。
自己を再評価するコツは、視点を変えることです。
自分目線ではなく、他者や第三者による俯瞰した視点から自分の能力を確かめてみてください。
★自己を再評価する方法
「他者や自己との比較」や「他者からのフィードバック」により、以下の情報を集めることをおすすめします。
A.全体との比較:全体から見て自分はどのレベルに位置するのか?
→主観的だと自分を過度に低くor高く評価しがち
B.時間軸による変化:自分のこれまでの、これからの成長はどうか?
→主観的だと自分は過去からまったく成長していないと捉えがち
→主観的だと自分は時間をかけてもまったく成長しないと捉えがち
C.成功者の情報:成功者はどんな能力を身につけているのか?
→主観的だと成功者はとんでもない能力を持っていると考えがち
→主観的だと成功者はまったく努力していないように捉えがち

方法⑤:周囲からの肯定
周囲からの肯定とは、「あなたならできるよ」と可能性を他者から承認されることです。
「自分には無理」と自分で捉えていても、他者から肯定されることで「実はできるのかもしれない」と考えを改めることがあります。
★周囲からの肯定の主な種類
・保証:成功を約束されること
・ラベル付け:強みをフィードバックされること
・可能性の承認:成功する資質があると認められること
自己効力感は案外直感的に抱くものであり、その要因は主にセルフイメージです。
過去の成功体験や周囲からの肯定はセルフイメージを高め、直感的に自分なら「できるだろう」と感じさせてくれます。
自分の努力や変化、可能性を承認してくれる人が近くにいることで、このような潜在的な自己効力感が高まりやすいです。
★「あなたはやればできる」の罠
学生時代、親や先生から「やればできる」と声かけをしてもらった人は多いのではないでしょうか。
この声かけは潜在能力の肯定であり、「自分にはやればできる能力があるんだ」と思わせる土台を育むことに役立ちます。
しかし、「やればできる」と思い込むことは「そもそもやることができない」という課題から目を背けさせる原因でもあります。
「本気を出す機会があれば成功する」と慢心させ、地道な努力を軽視するようになるでしょう。
そのため、「潜在能力の肯定」だけではなく「努力できる資質の肯定」をすることも大切です。
少しでも努力できたなら、成功や潜在能力だけでなく、その努力や勇気を肯定する声かけをしてみてください。
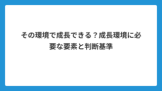
方法⑥:楽観視可能な状態
「まぁなんとかなるか」と楽観的な状態であるほど、自己効力感は高まる傾向があります。
楽観的な状態では成功に焦点が当たりやすくなるとともに、失敗によって生じる損失を小さく評価するようになるためです。
何かに挑戦しようと考えるとき、まずは自分が楽観的な状態かを確認してみてください。
もしも悲観的な状態なのであれば、一度悩むことをやめて元気なときに再度意思決定をすることをおすすめします。
★楽観的になるための方法
・よく寝る
・ストレスを解消する
・アファメーションをする
・失敗による損失を再評価する
・「できる」と思ったほうが都合がよいと認識する
・「未来のことは正確に予測できない」と不安を手放し現在に集中する
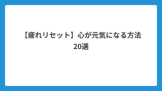
方法⑦:理想の自分になりきる
理想の自分になりきることで、目先の挑戦への恐れを小さくできます。
通過点の1つと見なすと同時に、理想の自分であり続けようとプライドを持てるためです。
- 現状の自分であろうとする:新人研修中の私
- 理想の自分であろうとする:一流ホテルマンである私
自分のあり方が書き換えられると、思考や行動、習慣が変わります。
自信のない挑戦はすべて試練となり、失敗することよりも上手くできるようになることに焦点を合わせられるようになるでしょう。
- 失敗に焦点を当てる:失敗したらどうしよう、叱られるかも…
- 成功に焦点を当てる:成功するにはどうすればいいのだろうか、理想の自分ならどうするか
ただし、理想の自分とは肩書きではないことに注意が必要です。
心から「なりたい」または「ありたい」と思える自分であり、言葉の定義を重視してください。
- 肩書き:社長になりたい、課長になりたい、母親になりたい
- 理想の自分:子供たちに夢を与えられる存在でありたい、家族を守れる存在でありたい
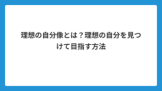
自己効力感が低いことをあらわす3つのサイン
問題に躓いている理由が自己効力感の低さにあると自覚することは難しいものです。
そのため、ここでは自己効力感が低いときに生じる兆候についてお伝えしていきます。
ここで紹介するサインが現れたら、「私はできる気がしていないのでは?」と自分に問いかけてみてください。
サイン①:他責思考
自己効力感が低いときは、他責思考の傾向が強まります。
「もうこれ以上自己を改善できない、けれど問題を解決したい」というときは、外に働きかけるしか手がなくなるためです。
他人や環境への怒りを感じたら、自己効力感が低いサインかもしれません。
「自分が本当にその問題に影響を与えられないのか」をもう一度検討することで、他責思考が軽減することがあります。
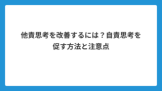
サイン②:やる気のなさ
成功する確信が持てないと、やる気はなかなか湧いてきません。
行動から得られる利益が少なく、労力を割く必要性を感じられなくなるためです。
また、失敗を確信しているときは、失敗による損失をより強く意識してやる気が失われていきます。
★よくある失敗による損失
・恥ずかしい目にあう
・時間やお金、機会や人脈が失われる
・自分のダメな部分を直視してしまう
やる気が出ないときは、挑戦や失敗から得られるものを再評価してみてください。
同時に次の問いについて再検討することで、やる気が湧いてくる可能性があります。
- 本当に失敗する可能性は100%なのか?
- 失敗したら何を失い何を得られるのか?
- 私は何%の成功確率がなければ動けないのか?
- 成功する可能性を高める方法は1つもないのか?
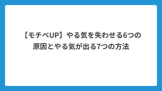
サイン③:セルフハンディキャップ
セルフハンディキャップとは、失敗による自尊心の低下を阻止するための工夫のことです。
挑戦に対して自信がないときに、心の傷を広げないためによく使われます。
★セルフハンディキャップの例
・失敗の予告:「全然テスト勉強していない」と友人に伝える
・自分への縛り:課題の難易度を上げる縛りを自分に課す
・ネガティブな言動:「どうせ私なんか無理」と常に自分の能力の低さを公言しておく
セルフハンディキャップを活用している自分に気づいたら、「あぁ私は失敗すると感じているんだ」と自覚してみてください。
「失敗時の対策」だけでなく「成功確率を高める方法」にも焦点を合わせることで、より建設的な思考ができるようになります。
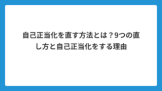
自己効力感の4つの注意点
ここでは、自己効力感に関する注意点をお伝えしていきます。
注意点①:自己効力感の善し悪し
自己効力感とは、高ければ高いほどよいというわけではありません。
高い自己効力感にも、低い自己効力感にもメリットとデメリットが存在するためです。
★高い自己効力感のメリット・デメリット
・メリット:挑戦を容易だと捉え、行動への抵抗感が軽減する
・デメリット:挑戦を容易だと捉え、慢心し挑戦や努力が止まる。難易度が容易なほど失敗しないためにも挑戦を回避するようになる
★低い自己効力感のメリット・デメリット
・メリット:困難な挑戦だと捉え、成功のための努力を徹底するようになる
・デメリット:困難な挑戦だと捉え、行動への抵抗感が増大して挑戦できなくなる
自己効力感の善し悪しは、その後の行動によって結果論的に決まります。
つまり、自己効力感がどの程度あるのがよいかは、人によって全く異なるということです。
そのため、「自己効力感が低いからダメなんだ」「自己効力感を高めればすべて解決するんだ」と安易に考えないようにしてください。
自己効力感を高めるのは1つの手段であり、目的によってはかえって逆効果や遠回りだということもありえます。
★自己効力感は主観的なもの
ダニング=クルーガー効果のように、スキル練度が低いのに自分の能力を過大評価することがあります。
自己効力感は主観的な感覚であり、「感覚」と「実際の結果」がかならずしも一致しないためです。
自己効力感が目標達成行動を妨げる原因になっているときは、その根拠の信憑性を確かめることをおすすめします。
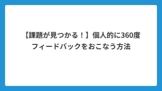
注意点②:挑戦に対する保証依存症
挑戦に対する保証依存症とは、他者から成功を約束されないかぎり実行意欲が湧かないことです。
「自分の能力把握」ではなく「失敗の責任転嫁」を目的に保証を求めているのであれば、保証依存症かもしれません。
★自己効力感と保証依存症
・能力に対する低い自己効力感
→他者からの保証がないと「自分は何をしても絶対に失敗する」と思い込んでしまう。
・能力に対する高い自己効力感 × 仮説を作り出すことへの低い自己効力感
→「自分は方法さえ分かっていればできる」と他者に保証されたやり方ばかりを探してしまう。
起業のような不確実な挑戦では、保証してくれる相手やフィードバックの精度が減り、保証依存症は行動を止める原因になります。
安心感を得るために高額の自己投資をして、資金を減らす起業家は少なくありません。
不確実な挑戦をするとき、「不確実性を減らす努力」は大切ですが、「不確実性の許容」も同じくらい大切です。
安心を得ることばかりに注目するのではなく、「勇気を持って挑戦できるスキル」にも焦点を合わせてみてください。
★保証依存症への主な対策主
・不確実性を減らす:指導者に教わる、小さく実験する、他者から保証される
・無理な期待を捨てる:どのぐらいの成功率がないと動けないのかを明確にしてその期待を検証する
・不確実性を許容する:不安や恐怖を明確にして小さくする、リスクを許容する、失敗による利益に注目する
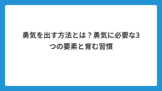
注意点③:「やりたくない」と「できない」の混同
自分の本心が分からなくなり、「やりたくない」と「できない」が混同することがあります。
自己効力感が低いとき、またはやりたくないと思っているとき、本当にそうなのかを確かめてみてください。
- できない→実はやりたくないと思っているだけ
- やりたくない→実はできないと思っているだけ
自分の本心を確かめるには、目的論で考えることがおすすめです。
「私はその判断や行動をしたことで何を得られるのか?」と否定的な態度を取ることのメリットに焦点を合わせることで、自分が持つ期待や目的が明確になります。
★自己効力感が低いことで得られるもの
・挑戦せずに済む
・失敗したら被害者になれる
・恥ずかしい思いをせずに済む
・期待を下げることで成功したときの報酬感が増える

注意点④:協力を仰ぐことも自己効力感に含まれる
「他者に聞いたり頼んだりすればこの目標は達成できる」と思えることは、自己効力感が高いと言えます。
「できる気がする」という感覚は、「自分が実行可能」ではなく「自分が目標達成可能」というものだからです。
- 誤った自己効力感:自分1人の力で誰にも頼ってはならない
- 適切な自己効力感:自分に不足している部分は他者の力を借りてもよい
自己効力感を高めたいならば、自分の能力を向上させるだけでなく、自分の周りにいる人々に焦点を合わせてみてください。
「何かあっても助けてくれる人がいる」と思えることで自己効力感が高くなり、困難な挑戦にも楽観的な態度で臨めるようになります。
★虎の威を借る狐
「虎の威を借る狐」とは、背景にいる権力者の威光によって、力の弱い人が威張ることの喩えです。
これも「協力を仰ぐことで何とかなる」という認識によって、自己効力感が高まっている状態だと言えます。
あまり良い意味では使われない言葉ですが、「誰の威を借りることで成功するだろうか」と考えることは新しい視点を生み、自力では困難な問題を解決する突破口になるかもしれません。
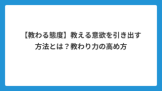
自己効力感に起因した個人事業主の陥りがちな問題
ここでは、自己効力感と関係する個人事業主のありがちなケースについてお伝えしていきます。
ケース①:自己投資だけに精を出す
できる気がしないとき、成功確率を高めるために情報収集をしたり指導を受けたりすることはよいアイデアです。
個人事業主やフリーランスなどには上司のような指導者がいないため、スキルアップをするために高額な自己投資が必要になります。
★よくある自己投資の種類
・指導:成功者のカリキュラムによる教育を受ける
・情報提供:成功者の成功法則やロードバックを教わる
・コーチング:対話による目標達成や自己成長の支援を受ける
・フィードバック:成功者に自分のスキルや成果物の状態をチェックしてもらう
しかし、ここで問題なのが「自己投資さえすれば成功するだろう」という期待です。
この期待で自己投資をすると、結果を他責にしてしまいます。
「失敗しても自分が悪いわけではない」と考えるようになり、失敗や努力を積み重ねないことを自己正当化するようになるのです。
★自己投資への誤った期待の例
この商品に自己投資するだけで…
・やる気が出る
・一流になれる
・失敗せずに済む
・努力せずに済む
・稼げるようになる
・100%の成功法則が分かる
あくまで自己投資は成功を約束するものではなく、成功確率を高める時短テクニックでしかありません。
自己投資したことで安心感を得て、自分の責任範囲を放棄しないように気を付けてください。
まずは「できない気がする」の原因となる課題を突き止めるためにも、実践して自分の躓きポイントを明確にしてみましょう。
その明確になった課題を乗り越えるための自己投資をすることで、自分と講師の責任範囲を混同しづらくなります。
「できない気がする」という漠然とした不安を取り除くための自己投資は、十中八九失敗します。
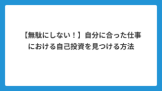
ケース②:フィードバックを回避する
現在に対する自己効力感が高いと、それを否定するフィードバックに回避的になります。
できていないことを直視したくないため、現在地を知る手掛かりとなるネガティブな情報を受け取らなくなるのです。
★現在地を知る手がかり
・計画:目標の全体像と現在地
・目標:人生がどこに向かっているのか、今どこにいるのか
・結果測定:どれほど効果的だったか、どこに問題がありそうか
・他者からの指摘:できている部分とそうでない部分
フィードバックを回避しようとする人にありがちなのは、自己流にこだわろうとすることです。
自己流ならば他人からとやかく言われる筋合いがないため、成果が出なくても自己流で貫こうとします。
しかし、自分の仮説を信じていない自己流は、事故の原因でしかありません。
思いついたことや目の前にあることに手を付けるだけであり、その場しのぎをするためにやった感を出しているにすぎないでしょう。
★自己流の効率性
・効率的な自己流:一般的な方法で生じる問題を解決するための工夫、周囲の情報に好意的
・非効率的な自己流:すでにある情報を調べない思い付きによる工夫、周囲の情報に否定的
フィードバックを受け取りやすくなるには、現在に対する自己効力感を下げて、理想に対する自己効力感を高めることが有効です。
「できるようになるための情報」にどん欲になれれば、フィードバックを1つの情報として求められるようになります。
★指導するときのフィードバック
一般的に私たちはネガティブフィードバックを嫌うものです。
そのため、フィードバックするときはポジティブフィードバックに言い換えることをおすすめします。
・ネガティブフィードバック:欠点や失敗に焦点を当てる(~がダメ)
・ポジティブフィードバック:美点や成功に焦点を当てる(~がよい、~すればもっとよくなる)

ケース③:できることだけで稼ごうとする
「今できること」だけで稼ごうとするのは、短期的な成果を得るためには有効です。
しかし、すぐに天井に至り、小さな成果で頭打ちになってしまいます。
同じことを繰り返す日々になり、自転車操業のような働き方になるでしょう。
★個人事業主の一般的な働き方のサイクル
1.達成する
2.効率化する
3.余力で新しいものに着手する(新規開拓、事業拡大)
もし自転車操業のような働き方から解放されたいなら、一旦効率化にシフトしてみてください。
「今できること」だけで達成できた目標でも、効率化しようとしたらたくさんの「今できないこと」が現れ、それこそが重要な成長ポイントになるためです。
ただし、「今できること」だけ稼ごうとしていた場合、その新たな挑戦には強い抵抗感が生じます。
現状維持への強い力が働くため、その感情と折り合いをつける必要があるでしょう。
★効率化のパターン
・単価を上げる:「1万円/1つ」を「3万円/1つ」にする
・リソースを減らす:「20個/1カ月」を「50個/1カ月」「50個/1週間」にする
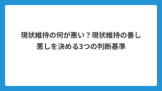
まとめ
自己効力感には、次の2つの種類があります。
- 現在に対する自己効力感:私は今それができるだろうという感覚
- 未来に対する自己効力感:私はがんばればできるようになるだろうという感覚
これらの自己効力感を高めるには、次の6つの方法が有効です。
- 成功体験
- 代理体験
- 課題の調整
- 自己の再評価
- 周囲からの肯定
- 楽観視可能な状態
人によって、自己効力感が高まりやすい思考パターンが異なります。
過去を思い出し、自分が自己効力感が高まった瞬間や高かった状態のきっかけを検討してみてください。
それを再現することで、現在の課題や挑戦に対しても自己効力感を効果的に高められるでしょう。
ただし、自己効力感は高ければよいというものでもありません。
自己効力感を高める際は、自分が自己効力感に何を期待しているのかを検討することをおすすめします。