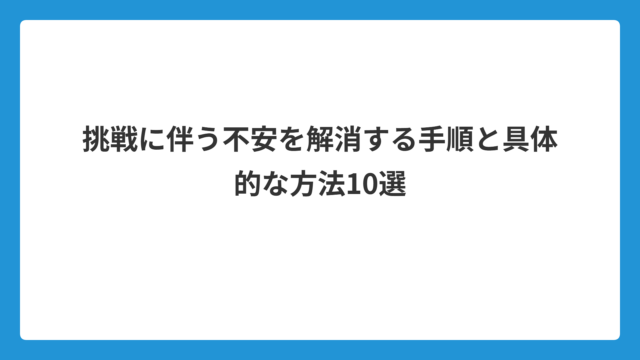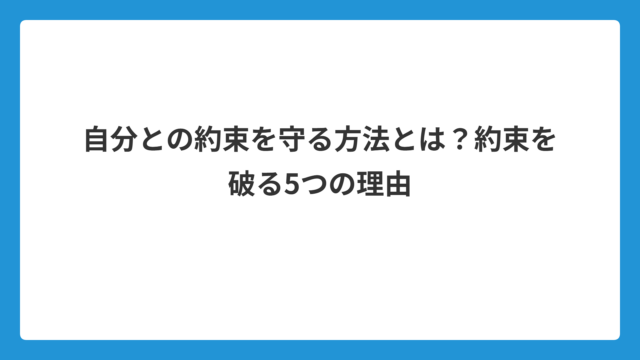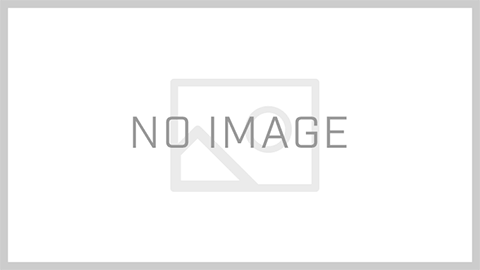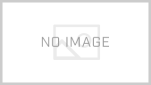「またやることが増えた…」
「あれもこれもやらなきゃ…」
「やるべきことがたくさんある…」
上記のようなげんなりする感覚が「多忙感」です。
多忙感はタスクが増えること、またはリソースが失われることに反応して生じます。
そのため多忙感が生じやすい人は、次のようなことに苦手意識を持つ傾向があります。
- コツコツ作業するのが苦手
- 他人の手伝いをすることが苦手
- スケジュールや計画通りに動くことが苦手
この記事では、多忙感を解消するための方法についてお伝えしていきます。
多忙感のストレスを軽減したいときは、ここにある情報を取り入れてみてください。
「多忙」と「多忙感」の違い
多忙と多忙感は似た言葉ですが、ニュアンスが異なります。
事実と感覚の違いがあり、同様の状態や状況でも同じように多忙感を抱くとは限りません。
多忙であるから多忙感を感じるわけではなく、多忙でないから多忙感を感じないわけでもないということです。
- 多忙:実際に忙しい、客観的な状態をあらわす、事実
→例.仕事に追われて睡眠時間すら削られている状態 - 多忙感:忙しいという認識、主観的な状態をあらわす、感覚
→例.やるべきことが多すぎて自分の時間が残されていないという感覚
よくある勘違いですが、「多忙感=悪感情」というわけではないことに注意が必要です。
「多忙感が心地よい」「むしろ多忙でなければ不安になる」と感じる人も一定数存在するのです。
そのため本記事では、多忙感を不快に感じる際の解消法についてお伝えしていきます。
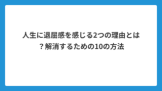
多忙感が生じる3つのパターン
ここでは、多忙感が生じる3つのパターンをお伝えしていきます。
多忙感を解消するために、不快感がどのパターンに起因したものかをつきとめましょう。
パターン①:リソース不足
リソース不足とは、タスクを実行するための時間が足りない状態のことです。
実際の多忙であり、その忙しさを認識して不快感が生じます。
★リソース不足による多忙感
・もうこれ以上仕事を増やしたらパンクする
・今日の仕事を終わらせるために残業しなきゃ
リソース不足である場合、多忙感を解消するにはまず「タスクをリソース内に収めること」を目指したほうがよいでしょう。
会社のようなタスクが永遠に増え続けてくる環境の場合は、その環境自体を変える、またはその環境から離脱することも視野に入れる必要がありそうです。

パターン②:自己決定感の低下
他人にやらされている感覚は、多忙感を生じさせます。
「不本意なタスク=自分の時間を奪う厄介なものだ」と捉えやすいためです。
★自己決定の低下による多忙感
・なんで私があなたの手伝いをしなければならないの
・10時間後には再び辛い仕事をしなければならないのか
自己決定感によって多忙感が生じている場合、「時間の使い方」について意識してみることをおすすめします。
自分はどんな人生や在り方でいたいのかを明確にすることで、やらされている感は低下するでしょう。
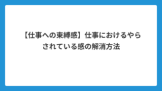
パターン③:情報量のキャパオーバー
情報量のキャパオーバーとは、情報量が多すぎて整理できていない状態のことです。
情報量が整理できていない状態では、タスクを終わらせるイメージができません。
苦しい状態が一生続くと考えてしまい、その思考が多忙感を生み出します。
★情報量のキャパオーバーによる多忙感
・起業をするにはたくさんのことを調べなきゃ…
・買い物行って洗濯して迎えに行って…やることが多すぎる
情報量のキャパオーバーによって多忙感が生じている場合、タスクを終わらせる目途をつけることを目指してみてください。
「これをこの順番でやればこの期間で終わるだろう」と捉えられると、タスクが積み重なっていること自体からのストレスが低下します。
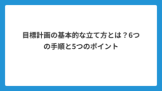
リソース不足を解消する方法3選
ここでは、リソース不足に起因する多忙感の解消方法についてお伝えしていきます。
リソース①:生産性を上げる
テコの原理のように知恵や工夫を用いて生産性を上げることで、多忙が解消されます。
所有しているリソースを洗い出して、その活用方法を模索してみてください。
★生産性を上げるための工夫
・外注:資金リソースを時間リソースに転換する
・仕組化:無駄のない工程、ハプニングにも対応できるマニュアル
・効率化:少ないリソースで目的を達するための手段の模索
・回復する:パフォーマンスを十全に発揮できる心身の状態を取り戻す
・自己成長:心理的/スキル的な成長によりタスクの難易度を低下させる
・タスク管理:緊急度と重要度によるタスクの断捨離
・環境づくり:集中できる環境、相談できる環境、応援される環境
生産性を上げるには、すでに成功している人をロールモデルにすることがおすすめです。
その人の手段・思考・環境などを真似たほうが、自分で1つずつ仮説検証するよりも簡単に生産性を上げる方法を見つけられます。
★大量行動
改善する手間を惜しんで低い生産性を保持しようとする誘惑に負けないように注意しましょう。
生産性は一長一短に上がるものではなく、情報収集や振り返り、実践による仮説検証を繰り返す必要があるためです。
この誘惑と折り合いをつけて大量行動を実施することが、生産性を高める最初の1歩になります。
・NG:効率的な方法がないから今のままでいいや
・OK:効率的な方法を見つけるためにたくさん動き回ろう
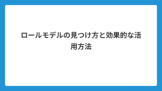
リソース②:リソースを増やす
リソースが足りないなら、リソースそのものを増やすというのも1つの解決策になります。
「リソースがどれほどあれば間に合うか?」と自問して、必要なリソース量を検討してみてください。
★リソースを増やす方法
・お金:別口で稼ぐ、節約する、借金する
・時間:やらないことを決める、隙間時間を活用する
・人脈:新しい人と出会う、今いる人と関係性を深める
多忙感の主な原因は、時間的リソースの不足です。
時間の上限には限りがあり、「タスクAへの時間」を増やすときは「タスクBへの時間」を減らす必要があります。
時間を捻出するためにも「1日24時間」の使い方を洗い出し、時間配分を再調整することから始めてみましょう。
また、「他人の時間も分けてもらえる」という前提を持つことで、不足したリソースを補うことも可能です。
★ないものねだりに注意
難しい挑戦をするときは、以下のような言い訳により行動が止まりがちです。
・~がないからできない:時間がないからできない
・~さえあればできるのに:資金さえあれば稼げるのに
ないものを補う努力は大切ですが、現在の状態で成功する方法を検討することも同じくらい大切です。
ないものを補えないと分かったら、現在の状態でどうやってうまくいかせるかを模索してみましょう。
A.忙しい→時間がない→時間を増やそう→時間を増やせない→だから無理
B.忙しい→時間がない→時間を増やそう→時間を増やせない→現状のままで解決できる方法は?
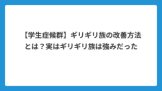
リソース③:成功基準を下げる
ここでいう成功基準とは、自分が自分に定めている合格ラインのことです。
高い成功基準を持つほど必要な労力が増えて、リソースはますます不足していきます。
★成功基準の例
・掃除はチリひとつ残してはならない
・テストは80点以上取らなければならない
・関わる人全員からは絶対に嫌われてはならない
・誰よりも優れた画期的なアイデアを披露しなければならない
成功基準を下げるには、高い成功基準を自分に課す必要性を検討してみてください。
何かしらの期待から、必要以上に高い成功基準を設けている場合があるためです。
高い成功基準を課す目的を明確にして、それが今の自分にとって本当に必要なのかを確かめてみましょう。
★高い成功基準を課す目的/期待
・何かを得たいから:チリひとつ残さずに掃除すると褒めてもらえるから
・何かを失いたくないから:チリひとつでも残すと激しく叱られるから
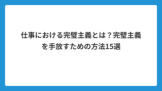
自己決定感の低下を解消する方法3選
ここでは、やらされている感に起因する多忙感の解消方法についてお伝えしていきます。
決定感①:意味づけを見直す
意味づけを見直すとは、タスク自体の解釈を自分にとって有意義なものとして捉えなおすということです。
タスクを実施することが自分の利益になると分かれば、やりたい感覚が強まり多忙感が小さくなります。
★意味づけを見直す例
・母親の手伝いをしなければならない
→将来モテるためにも料理スキルを磨いておこう
・学校の宿題をしなければならない
→好きな子に恥ずかしい姿を見せないためにも宿題をしよう
意味づけを見直すには「タスクに費やすリソース」ではなく、「タスクを実施または実施しなかったときの結果」に焦点を当てることが有効です。
自分にとって好ましい展開とは何かを考えながら、多面的にどんな影響が生じるのかを検討してみてください。
★苦手なタスクは多忙感を生み出す
意味づけをポジティブなものにしても、そのタスク自体に苦手意識があると多忙感は解消されません。
「苦手=失敗しやすい」ということであり、失敗への不安で思考リソースを大量に費やしてしまうためです。
苦手なタスクにより多忙感が生じている場合は、次の5つの解消方法が挙げられます。
・切り替える:考えても仕方がないと割り切り目先のタスクに集中する
・成功基準を下げる:赤点さえ取らなければよいと最低限の基準を設ける
・成功基準を変える:「批判されない文章」ではなく「ターゲットに響く文章」
・苦手を克服する:損失を最小限にする対策を練る、失敗確率を下げる工夫を施す
・成長に焦点を当てる:「失敗するか否か」ではなく「どんな成長ができるか」を考える

決定感②:選択肢を検討する
選択肢を検討するとは、「やりたいこと」と「やるべきタスク」を明確にするということです。
やりたいことは漠然としていることが多く、何をどのぐらいやりたいのかを明確にすることで他のタスクとの折り合いをつけれる可能性があります。
★選択肢を検討する例
・勉強したら遊ぶ時間がなくなる
→遊ぶ時間は3時間で十分かも。残りの2時間は勉強にあてよう
・家事をすると自分の時間がなくなる
→家事をすることも育児をすることも私の時間である。ただ今期のドラマを観ることができればもっと嬉しい
ただし、選択肢を検討するときは、デュレーション・ネグレクトという認知バイアスに注意してください。
私たちは時間に比例して報酬感や損失感が生じると期待しがちですが、実際は時間の長さとは比例していません。
「どのような経験をするのか」こそが大切であり、その経験をする時間が長いからと言って幸福感や苦痛が大きくなるわけではないということです。
この認知バイアスを踏まえたうえで、やりたいことにどれほどリソースを費やすのかを考えることをおすすめします。
★嫌な選択肢を作ってみよう
選択肢を検討するときは、意図的に嫌な選択肢を作ることも1つの手です。
「やるべきタスク」がもっとも嫌な選択肢であるよりも、さらに嫌な選択肢が他にある状態のほうがタスクへの意欲が高まりやすくなるためです。
・やるべきタスクが一番嫌な選択肢である:嫌だけどやらなければならないのか…
・やるべきタスクより嫌な選択肢がある:嫌な選択肢を回避できるならこれぐらいやろう!
嫌な選択肢をつくるときは、次の2つの方法が挙げられます。
・嫌いなタスクをつくる:整理整頓をするぐらいなら仕事をしたほうがマシだ
・タスク量に差をつける:8時間ではなく5時間だけ仕事に集中しよう
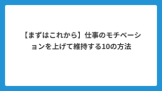
決定感③:フィードバックを受け取る
フィードバックを得るとは、実施した、または実施しなかったことによる結果を実感するということです。
自分の行動がどのような影響を及ぼすのかを体感することで、その結果を再体験したいか否かという新しい判断基準が生まれます。
例.「親に手伝いを頼まれたとき」のフィードバック
・手伝った×ポジティブフィードバック:感謝される、工夫ポイントを褒められる
→またやりたい!
・手伝わなかった×ネガティブフィードバック:悲しむ姿を見る、自分のお願いを伝えづらくなる
→次は手伝った方がいいのかも
嫌なタスクを実施したときは、小さくてもよいのでそれによるプラスの影響を受け取ってみましょう。
「まぁやってもいいかな」程度にまで心が傾けられれば、自己決定感が高まり多忙感が解消されます。

情報量のキャパオーバーを解消する方法3選
ここでは、情報量のキャパオーバーに起因する多忙感の解消方法についてお伝えしていきます。
情報量①:具体化する
大きなタスクは終わるイメージがつきづらいため、多忙感が生じやすい傾向があります。
「どこから手を付ければいいのか」「どれほど繰り返せばいいのか」と思考することにリソースを費やしてしまうのです。
終わりが見えない挑戦ほど、苦しいものはそうそうありません。
★大きなタスクの例
・膨大な量の宿題
・初めての論文づくり
・起業して稼げるようになる
大きなタスクによる多忙感を解消するには、タスクを具体化することが有効になります。
小さく分けて考えることで現在から完了までのステップが明確になり、タスクを終えられる希望が芽生えるためです。
まずは、1つの大きなタスクを3~5つのステップに分けてみてください。
それでも大変そうだと感じる場合は、さらのそれらのステップを3~5つのステップに分解してみましょう。
★小さく分ける方法
・数字に分解する:腕立て伏せ100回→腕立て伏せ25回×4セット
・手順で分解する:情報発信する→ネタづくり、ピックアップ、執筆、修正
・構成要素で分解する:年商1千万円稼ぐ→30万円の商品×30人に売る
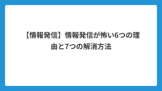
情報量②:抽象化する
大きなタスクは小さく分けたほうが多忙感が生じづらいですが、一方で細かいタスクが多すぎても多忙感が生じます。
私たちは数が4つ以上だと「たくさん」と感じやすく、量に圧倒されて辟易としてしまうためです。
「Aをして、Bもして、Cもして」とやるべきタスクが溢れたら、「つまり何をするの?」と自問自答して抽象化してみてください。
参考:https://coanexus.com/coastudy/blog/science002/
★抽象化の例
・パソコンを閉じて、ボールペンをしまって、カバンを出して…
→片づけをする
・服を着替えて、車に乗って、お店について、商品をとって、会計して…
→買い物をする
・パソコンを開いて、情報を集めて、情報をまとめて、見出しを作って…
→ブログの第一工程
具体化にしても抽象化にしても、タスクをロジックツリーに図化することが有効になります。
ロジックツリーにおけるどの階層を意識することで多忙感が薄れるのかを検討することで、「あれもこれもやらなきゃ」と感じづらくなります。
ロジックツリーを作ることはタスクの効率化にも役立つため、ぜひとも作ってみてください。
- 具体化する:たとえば何?
- 抽象化する:つまり何?
★未完了のタスクリスト
未完了のタスクは残っているだけで思考リソースが奪われて多忙感が生じます。
しかし、思いついたその場でタスクをすぐに完了することはマルチタスクの原因にもなり、現実的ではありません。
そのため、未完了のタスクがあるときは「雑用」とラベル付けして、特定の曜日や時間に終わらせる習慣を身につけることをおすすめします。
・特定の曜日:毎週金曜日は「雑用」を一括で終わらせる日
・特定の時間:毎日16時からの1時間は「雑用」を終わらせるための時間
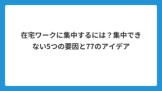
情報量③:スケジュールに落とし込む
やるべきことがたくさんあっても、今できることは1つだけです。
気が焦っていても多忙感が生じるだけなので、何をどの順番で実施すべきかを整理して、今できることにだけ集中することをおすすめします。
★スケジュール作りの手順
・手順①:実現したい未来を明確にする
・手順②:目標を設定する
・手順③:行動計画を立てる(目標の要素分解)
・手順④:今月の目標を設定する
・手順⑤:直近1ヵ月の休日を配置する
・手順⑥:直近1ヵ月の締切と開始日を配置する
・手順⑦:直近1週間の1日ごとのスケジュールを作る
ただし、パンパンなスケジュールは、見るだけでも多忙感が生じるものです。
具体化と抽象化を使い、1日や1つのタスクにおけるざっくりとしたルーティンを確立してみてください。
習慣化された思考や行動は、抵抗感や葛藤が生じづらく多忙感を抑えられます。
★タスクの割り込みとバッファ
スケジュール作りではバッファを組み込むことが大切になります。
想定以上に時間を要したり、急な頼みごとをされたりとイレギュラーは起きるものだからです。
ただし、時間を多く確保するだけのバッファは気持ちが緩んでペースが落ちる原因にもなるため、次のような予定を組み込むことをおすすめします。
・自由時間:目標達成のためのタスクなら何をしても許される時間
・貢献する時間:他者の手伝いのように貢献する時間(1日1善のようなルール)
・インプット時間:情報収集をして視野を広めたり思考を深めたりする時間
・未完了を完了する時間:雑事を終わらせるための時間
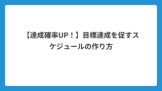
多忙感を抱きやすくする3つの信念
信念とは、安定して保持しているイメージのことです。
信念を通して現実の出来事を解釈し感情が生まれるため、信念を変容することで多忙感を抑えられる可能性があります。
ここでは、多忙感を感じやすくなる信念についてお伝えしていきます。
ここで紹介する信念を持っている場合は、その変容をするための検証行動を実施してみてください。

信念①:自由=予定が空白
忙しくなるほど、私たちは自由を求めるようになります。
しかし、「予定が空白であること」を自由であると捉えている場合には注意してください。
自分で決めた予定でさえも多忙感が生じやすくなり、常にストレスをかかえるようになるためです。
- 自由=予定が空白:予定が入っているだけでストレスがたまる
- 自由=自分で行動を決めること:自分で決めた予定ならストレスが生じづらい
すべての予定からストレスが生じるときは、自分が求めている自由を言語化してみてください。
「何もしていないこと」ではなく「何をしていること」を自由と呼ぶのかを再検討することで、スケジュールに対する多忙感が抑えられるようになります。
★過去の束縛
自分で決めた予定であっても、やらされている感に苦しむことがあります。
これは「過去の自分に無理やりやらされている」という強制感を感じてしまうためです。
自分で決めた予定にストレスを感じたら、「何をすべきか」ではなく「すべき理由」に焦点を当てて「やる/やらない」の判断をしてみてください。
「やる/やらない」の選択肢は常に自分にあると考えることで、過去の束縛による苦しみが和らぎます。
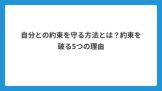
信念②:忙しい=悪いこと
忙しいこと自体をネガティブに捉えている場合、前向きな目標を持っていても行動への抵抗感が強まります。
「何を何故おこなうのか」以前に、「忙しい状態そのもの」に苛立ちを募らせるためです。
★怒りの矛先
何を何故:なぜ私がそんな無意味なことをしなければならないのか
→実行するタスクの質に対する不満
忙しい状態:なぜ私がこんなにも忙しく動き回らなければならないのか
→スケジュールがパンパンなことに対する不満
忙しいことへの嫌悪感を解消するには、次の2つの方法が挙げられます。
忙しいの許容量を増やす:1日8時間労働は忙しくないと感じられるようになる
忙しい=よいことという信念を持つ:忙しいほど何かを前に進められていると捉える
いずれの方法を実施するにしても、「なぜ私は忙しいことが嫌なのか」を自問自答してみてください。
本当に恐れていることや期待していることを明確にすることで、どのような考え方をすればいいのか、どのような検証をすればいいのかの方向性が見えてきます。
★「忙しい=悪いこと」と考える人の思考例
・忙しいと心身を壊してしまう
・忙しいとチャンスを逃してしまう
・忙しいとみすぼらしく見えてしまう
・忙しいと自分の時間が失われてしまう

信念③:タスク=完璧にこなすべき
合格ラインとなるタスクの完成度は、他者や自身が求める結果によって変動します。
しかし、タスクを完璧にこなそうとする人は、「すべてのタスクは高い完成度にすべき」という強迫観念からタスクごとに完成度を調整することが困難です。
すべてのタスクは全力を費やすべきものであり、だからこそ簡単なタスクが1つ増えるだけで多忙感が生じてしまいます。
★完成度の調整
・掃除は5分でちゃちゃっと終わらそう
・たたき台を作ればいいから30分で終わらせて上司に見せよう
・社外の人に見せる資料だから分かりやすいように丁寧に作ろう
大したタスクでもないのにストレスが生じる場合、強迫観念を生み出している”恐れ”を明確にしてみてください。
その恐れの妥当性と損失具合を検討することで、より小さな完成度にする許可を与えられるようになります。
- 妥当性:その恐れる結果は本当に生じるのか?
- 損失具合:その結果でのダメージは本当に甚大か?
タスクを一括りで考えず、1つひとつのタスクを個別に完成度を調整することが大切です。
自分の期待・周りからの期待・最低限の成功などを区別しながら、それぞれのタスクに隠れる強迫観念の核心を探してみましょう。
- 自分の期待:私はどんな成果や未来を求めているのか
- 周りからの期待:周りはどんな成果物を求めているのか
- 最低限の成功:どれほどの完成度なら致命傷にならないか
★本当の能力
限られたリソースで作れる成果物の完成度が、現状の能力値だと言えます。
いくらでも時間をかけてよいのであれば、小学生でも社会人でも完成度はたいして変わらないためです。
能力値を水増すためにリソースを多く費やそうとする誘惑には注意しましょう。
・偽りの能力値→どんな成果物を用意できたか?
・本当の能力値→その成果物にどれほどの時間をかけたか?その時間でどれほどの成果物を作れたか?
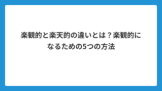
多忙感による個人事業主の問題ケース
ここでは、個人事業主が陥りがちな多忙感による問題についてお伝えしていきます。
ケース①:計画段階から進めない
計画を立てていると、行動に着手していないのに多忙感が生じることがあります。
経験が乏しいタスクは完遂するまでのイメージがしづらく、大変だと感じやすいためです。
★計画段階における多忙感
・こんなにやらなきゃならないのか
・これをずっと続けなきゃならないのか
・なんか大変そうなことをいっぱいする必要があるのか
そして計画段階での多忙感は、次の2つの行動のいずれかに誘導します。
「機会があったらがんばろう」と考えてしまい、気づいたら何年も経っていたなんてことになるでしょう。
より簡単な方法を見つけようとする
大変なことをするために必要な条件が整うまで先延ばしにする
非日常的で困難な目標に挑戦するときは、まずはこの多忙感と折り合いをつけることが最初の難関です。
忙しいことの奥にある欲求や恐怖に目を向けて、何をそんなに嫌がっているのかを突き止めてみてください。
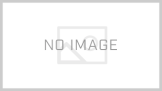
ケース②:事業を次の段階に進められない
個人事業主として1つの目標を達成すると、腰が重くなり現状維持に舵を切りやすくなります。
新しい挑戦にはさらなるタスクが必要であり、より一層忙しくなることに恐れを抱くためです。
★目標の衝突
・収入を増やしたいけど自分の時間も欲しい
・もっと事業を拡大したいけど今いるお客様とも密に接したい
次の段階に進むことへの多忙感が生じたら、目標が衝突しているサインだと認識してみてください。
そして、複数の目標を言語化して、次のいずれかの方法を試してみることをおすすめします。
- 優先順位をつける:今は自分の時間よりも仕事を拡大するフェーズにする
- 折り合いをつける:自分の時間も大切にしつつ事業を拡大する目標を達成する
★事業の循環
事業を無理なく循環させるには、「目標達成→効率化→新たな目標達成」の流れが大切です。
1つの目標達成をしたら、次にやるべきことは効率化であり、効率化が終わって余力ができたらようやく次の段階に進めるということです。
・NG:10のリソースのうち、10を現在のタスクに費やし、さらに5を追加して新たな事業に充てる
・OK:10のリソースのうち、効率化して7を現在のタスクに費やし、残りの3を新たな事業に充てる
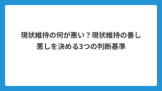
ケース③:本当に大切なことを蔑ろにしてしまう
忙しいとは、充実の一種でもあります。
思考が満たされている感覚であり、今あるタスクにさえ注意を向けていればよいという迷いの少ない状態です。
★忙しさと折り合いをつけるたけめの期待
・この忙しい日々をこなしていけば家族は幸せになる
・この忙しい日々をこなしていけば私は事業で成功する
しかし、今取り組んでいるタスクだけで、自分の理想が実現するとは限りません。
お金を得るだけで家族が幸せになるわけではないように、理想を実現するには複数の目標を達成することが不可欠だからです。
にもかかわらず忙しさにかまけて目先のことばかりに注目していると、本当に大切なことを蔑ろにしてしまうことにつながります。
★目標における順番と優先順位
・順番:何から目標を達成していく必要があるか?最終的にはすべての目標を達成する
・優先順位:どの目標を達成すべきか?自分にとっての重要度と緊急度の明確化
「日々のタスクに集中すること」も大切ですが、「理想につながっているのか」を確認することも同じくらい大切です。
特に個人事業主は自分が事業の舵を握っているため、事業またはお金を増やすことばかりに専念してしまう傾向があります。
その充実した日々に夢中になるのもよいですが、定期的にこのままで理想を実現できるのかを検討する機会を設けてみてください。
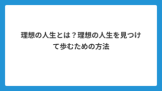
まとめ
多忙感を解消するには、その原因ごとに対処する必要があります。
多忙感に気づいたら、まずは以下のうちのどのパターンによる多忙感なのかを検討してみてください。
- パターン①:リソース不足
- パターン②:自己決定感の低下
- パターン③:情報量のキャパオーバー
「実際に忙しすぎることが問題」である場合は、タスクの調整が必要になります。
「忙しい感覚になることが問題」である場合は、自分の認識と向き合い、本当はどうしたいのかを検討することが多忙感を解消する手掛かりになるでしょう。
いずれにしても、何かを達成したいときは多忙な日々を過ごすことがほぼ必須事項です。
自分なりの多忙感と折り合いをつける術を身につけることは、今後の人生を楽しむには欠かせない技術になるはずです。