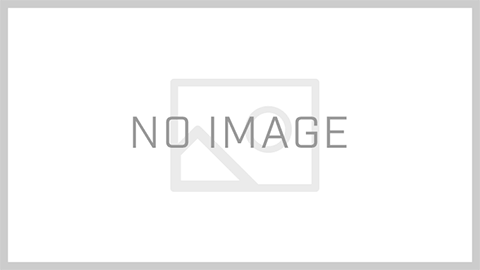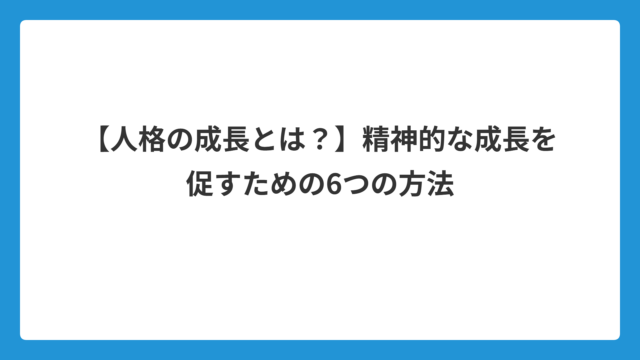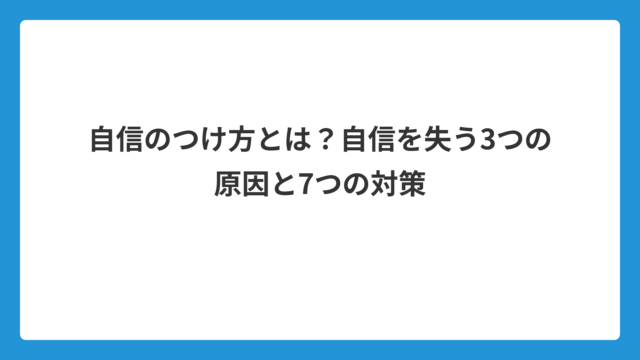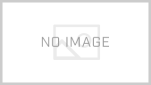勉強やダイエット、SNS投稿や筋トレなど、継続しなければ効果が出ないものがたくさんあります。
しかし、継続する力が弱いと三日坊主になりがちで、望んだ未来を得られません。
自分で人生を大きく変えることができず、外的要因が訪れるまで待つしかなくなるでしょう。
この記事では、継続力をつけるための思考錯誤の方法についてお伝えしていきます。
才能がなくとも継続は可能なので、ぜひここで紹介する方法を取り入れてお試しください。
継続力とはなにか
継続力とは、取り組みたい行動を意志と仕組みで続けられる力のことです。
- 意志:行動や目的への意欲や解釈
- 仕組み:行動継続を促すルールや外部要因
継続力が高い人は、自分が継続できる要件や継続を阻害する要件を理解しています。
自分の取り扱い方を把握しているため、高い確率で継続することが可能です。
- 継続できる要件:私はこんな意志や仕組みがあったら継続しやすい
- 継続を阻害する要件:私はこういう考え方や外部要因があると継続しづらい
また、「好きな行動」ほど、継続力が低くても続けやすい傾向があります。
継続力を上げるには、「苦手なことを続ける継続力を高める方向性」と「苦手なことを好きになるための解釈力を高める方向性」の2つあることに注意が必要です。
- 継続力を高める:勉強はきらいだけど続けよう
- 解釈力を高める:数学が実はおもしろいということに気づいたから続けよう
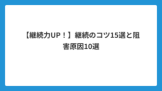
継続力をつけるための4つのステップ
ここでは、継続力を向上するためのサイクルについてお伝えしていきます。
この3つのサイクルを回して、自分の取り扱い方を把握できれば継続力が高まるでしょう。
ステップ①:目標を設定する
まずは、行動を継続して目指す地点となる「目標」を設定しましょう。
望まない目標だと、そもそも継続する意味を感じずに行動がすぐに止まります。
目標を設定するときは、「自分にどんな変化があったら嬉しいか」を言語化するようにしてください。
★目標設定はSMARTの法則にあてはめよう
・Specific(具体性):イメージが湧くような具体的な目標
・Measurable(測定可能):測定ができる数値化された目標
・Achievable(達成可能):今の自分でも達成可能で現実的な目標
・Relevant(関連性):目的と関連性の強い目標
・Time-based(期限):いつまでにやらければならないのかという期日
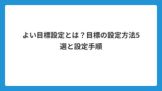
ステップ②:継続する行動を設定する
目標を決めたら、その目標を達成するための手段となる行動を検討します。
「どんな行動を続けることでその目標が達成できるのか」というストーリーを複数個考えてみてください。
例.ダイエットのストーリー
・1日1500カロリーに抑えたら3カ月後には5kg痩せるだろう
・週3でテニスサークルに参加したら3カ月後には5kg痩せるだろう
・毎日30分のウォーキングを続けたら3カ月後には5kg痩せるだろう
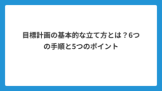
ステップ③:継続をするための工夫を施して実行する
「何を継続するか」を決めたら、その継続率を高めるための工夫を施します。
★継続率を高める2つの工夫
・継続しやすくなる工夫:あらかじめメモ帳にランニングする日に〇をつける
・継続の失敗パターンを排除する工夫:同僚に飲みに誘われないように目標を伝えておく
特に大切なのは、継続を阻む失敗パターンを想定して対策を練ることです。
少なくとも5つの失敗パターンを想定することで、継続率が大きく高まります。
失敗パターンを想定するには、継続しようとして失敗した過去を思い出すことがおすすめです。
★失敗パターンと対策を想定する質問
1.どんな挑戦に失敗したのか?
2.どんなきっかけで続けられなかったのか?
3.そのきっかけが続けられなかった理由は何か?
4.何があったら続けられたのか?

ステップ④:原因を探り改善案を試す
実行しても継続できなかったら、その原因を探しましょう。
原因を探るときは、自分が継続をやめたときの思考を思い出すことが有効です。
継続したい行動以外を選択した思考を把握することで、本当に手を加えるべき原因が絞れます。
例.ウォーキングが続かなかったときの思考
・歩いている姿を見られたくない→どんな場所や姿なら見られてもいいのか?
・痩せたってどうせ幸せになれない→本当はどうなりたいのか?何を得たいのか?
・ビールを飲んだから今日運動するのは危険だ→なぜビールを飲んだのか?
「私は〇〇だから続けられないのか」と納得できる原因が見つかったら、そのうえで継続するための改善案を複数個挙げてみてください。
その案を1つずつ効果検証していくことで、自分に合う継続する術が身についていきます。
★改善案はAIに聞いてみよう
自分が出す案は、今まで試したものばかりになる傾向があります。
異なる施策を試すためにも、AIに「継続が失敗する原因」を伝えて、どんな改善案があるのかを尋ねてみてください。
出した案をいくら試しても継続できない場合は、そもそもの原因が間違いである可能性が高いです。

継続を難しくさせるよくある原因と対策
ここでは、継続を断念させるよくある原因についてお伝えしていきます。
継続に失敗した原因を突き止めるときの参考になれば幸いです。
原因①:忘却
もっとも継続を失敗させる原因は、忘れてしまうことです。
「やるぞ!」と決断したことなのに、やることを忘れたり、そもそもなぜあんなにやる気になったのかを忘れたりした経験は多くの人があるのではないでしょうか。
★継続を阻む2つの忘却
・継続行動の忘却:「やりたい、けどやりたくない」という葛藤が生じない
→例.今日筋トレするの忘れてた…
・目標の意味の忘却:行動することの必要性や重要性を忘れてしまう
→例.何で私は筋トレする必要があるんだっけ、筋トレしたってどうせ意味がない…
忘却への対策は、「思い出すべきタイミング」で「思い出すべき内容」を思い出す工夫をすることです。
常に忘れないように意識し続けることは現実的ではないため、どのタイミングで何を思い出すべきかを設定しておきましょう。
思い出すべきタイミング:継続する行動を始める直前
思い出すべき内容:どんな行動をするのか、なぜそれが必要で重要なのか
★忘却への対策
・日記を書く
・他人に宣言する
・2日連続で休まない(完全休日を作らない)
・スケジュール管理する
・リマインダーをセットする
・目標を紙に書き毎日読み上げる
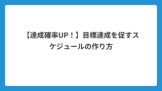
原因②:迷う
行動前に「やるかやらないか」を悩む人ほど、継続できる可能性は下がります。
毎回その葛藤に打ち勝たなければならず、一度でも負けると継続が止まってしまうためです。
例.行動前の葛藤
・今日も嫌いな勉強をするの?
・勉強とゲームどっちに取り組む?
・今日は不調だから勉強しても非効率的じゃない?
この葛藤への対策は、「やる」と決めきって「やらない」という選択肢を排除することです。
「もう決めたからやるしかないんだ」と割り切れれば、葛藤が小さくなり迷いがなくなります。
ただし、その行動を続ける意味を考え直す機会も大切なため、「決断するフェーズ」と「実行するフェーズ」に分けることをおすすめします。
- 決断するフェーズ:何を目指しどんな行動が必要か、今の行動の効果はどれほどか
- 実行するフェーズ:いちいち迷わない、やると決めきり無心で取り組む、行動から快を見出す
★迷いへの対策
・決断を固める:やるかやらないかをはっきりと決める
・特例を作らない:サボる特例を作ると選択肢が増えて毎回迷うようになる
・心配事を排除する:継続することで生じる損害を明らかにして対策を練る
・強制力を活用する:継続するのが当たり前の集団に属する、他人に管理される
・スケジュール調整する:「やるべきことA」と「やりたいことA」をどちらも実行する
・キャンペーン期間を用いる:いつからいつまでやってみようと仮決めする、一生続けるとは決めない
・意志力をより使わない方法を選ぶ:自宅で筋トレするのではなくジムに通う
・継続行動まで意志力を温存しておく:ストレス過多の状態では継続が難しい
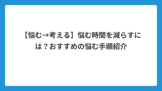
原因③:飽きる
継続はたいていが同じ行動の繰り返しであり、しだいに飽きてきます。
飽きた行動にはやる気が出ないため、継続することに消極的になってしまうでしょう。
例.飽き
・ウォーキングするにもいつも同じ風景でつまらない
・これ以上自分が成長できる気がしないから続ける意味がない
・仕事して資格取得のための勉強してという日々の繰り返しはつまらない
歯磨きのように「やらざるを得ない理由」があるならば、飽きていても行動を継続できます。
しかし、勉強やダイエットのように、やらなくても大きな損害が生じない行動は飽きたら継続することが困難です。
- 飽きても継続しやすい行動:継続しないと大きな損失が生じる行動
- 飽きたら継続が困難になる行動:継続すると大きな報酬が得られるが、継続しなくても大きな損失が生じない行動
飽きることへの対策は、刺激を増やすことが有効です。
行動自体を変えたり、行動から生じるフィードバックを変えたりすることで、ほどよい緊張感を持ちながら行動を継続できるようになります。
- 行動自体を変える:いつもとは異なる場所で運動をする、運動の内容を変える
- フィードバックを変える:時間を測る、出来栄えを評価してもらう、目標を設定する
★飽きへの対策
・タイムを縮める:効率化を目指す
・進歩を実感する:目標に近づいた距離感を把握する
・意味づけを変える:お金をかける、危機感を強める、何かのネタとして活用する
・新しい何かを取り入れる:場所/ツール/行動/手順などを変える
・フィードバッカーを用意する:誰かに指導/評価してもらう
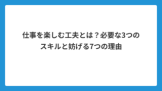
原因④:めんどくさい
私たちは今よりもラクではない行動を選ぼうとしたとき、「めんどくさい」と感じます。
これは恒常性によるものであり、「本当にエネルギーを消費する意味あるの?」という身体からの訴えです。
継続しようとする行動は短期的には成果が出づらい傾向があるため、より一層この身体からのサインが強まります。
- めんどくさいを感じづらい行動:すぐに報酬を得られる(食事、ゲームなど)
- めんどくさいを感じやすい行動:すぐに報酬を得られない(勉強、仕事など)
めんどくささへの対策は、思考よりも行動を優先させることが有効です。
やることをシミュレーションするほどめんどくさいと感じるため、「やると観念する段階」まで思考せずにおこなってみてください。
例.やると観念する段階
・仕事:スーツを着る、電車に乗る、会社に着く
・腕立て伏せ:最初の1回を実行する
・宿題をする:親の目の前で参考書を開く
ただし、行動を続けても一向にめんどくささが小さくならない場合は、それは身体からの本格的な警告かもしれません。
行動を続けることによる苦痛や影響を洗い出し、本当に継続すべきかを検討することをおすすめします。
★めんどくさいへの対策
・口癖を変える:「めんどくさ」と言ったら「まぁでもやるか」と付け加える
・無心で行動する:思考を進めずに行動する、ルーティンを作る
・優越感を味わう:めんどくさいから意味がある、他者はこれをやらないから差が出る
・習慣とセットにする:既にある習慣を継続行動のトリガーにする
・ゴールを小さくする:腕立ての姿勢をしたらOK、原稿に1文字書いたらOK
・めんどくさいを言語化する:何が嫌なのかを明確にして対処する

原因⑤:目標が衝突している
目標の衝突とは、「願望A」に向き合うほど「願望B」が叶わなくなる状態のことです。
目標が衝突することで「やりたい、けれどやりたくない」という葛藤が生まれ、やる気が下がり継続が困難になります。
例.目標の衝突
・稼ぎたい、けど遊びたい
・贅沢したい、けど貯金もしたい
・結婚したい、けど1人でエンジョイする時間も欲しい
衝突している目標のどちらを選んでも、後ろ髪を引かれてストレスが溜まります。
そのため、片方だけを選ぶのは最後の手段にとっておき、まずは次の3つのいずれかの対処をしてみてください。
- 本心を見つける:葛藤を引き起こす願望はどれも本当に自分が欲しいのかを検討する
→例.私は本当に遊びたいのだろうか、私が求める遊びとは何だろうか - 優先順位をつける:すべての願望を叶える前提で順番を決める
→例.あらかた贅沢してから貯金を始める、贅沢2割/貯金3割/生活費5割 - 第三の選択肢をつくる:どちらの願望も一緒に叶う目標を設定する
→例.短時間で大きく稼ぐことを目標にする、贅沢が経費になる分野で仕事をする
この問題は、目標設定への妥協によって生じます。
目標を設定するときは、本心を洗いざらい言語化して、自分がワクワクしつつも納得できるものを目指す地点にしましょう。
★目標の衝突への対策
・重い目標を安易に設定しない
・コーチングを受講して目標設定をする
・本心を探る、優先順位をつける、第三の選択肢をつくる、どちらかに決断する
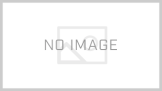
継続力をつけるためのマインド5選
マインドとは、思い込みや信念などと呼ばれる自分が持つ固定観念のことです。
ここでは、継続しやすくなるマインドについてお伝えしていきます。
マインド①:継続できる私が好き
私たちは「ありたい自分」であると報酬感が得られ、「ありたくない自分」であると損失感が生じます。
継続している自分のあり方が好ましくないのであれば、何かを続けること自体に違和感を抱いてしまいます。
- ありたい自分:こういう振る舞い方をする人間でありたい
- ありたくない自分:こういう振る舞い方をする人間は嫌いだ、私はそうありたくない
継続する態度に嫌悪感を抱いている場合は、「継続することも悪くない」程度にまで嫌悪感が和らげることを目指してみましょう。
具体的には、継続することへの意味づけを変える方法がおすすめです。
例.継続することへの意味づけ
・ポジティブな意味づけ:努力することに意味がある、コツコツすることは格好いい
・ネガティブな意味づけ:才能がないから継続が必要なんだ、継続は無駄な足掻き
意味づけを変えるには、「内省すること」と「体感すること」の2つの方法が挙げられます。
人によって合う合わないがあるため、どちらの方法も試してみてください。
- 内省する:自分の意味づけを把握してそれが絶対に正しいのかを検証する
- 体感する:継続することのよさを体感する、他者の継続するさまを観察する

マインド②:行動量が成長を促す
継続とは結果を得るための手段の1つです。
しかし、結果ばかりに焦点を当てると、成長や前進などの継続による成果物を見逃してしまう恐れがあります。
また、結果が出ないことへの焦りや絶望から、ストレスが溜まり継続することへの意欲が低下してしまうでしょう。
例.継続に対する焦点
・結果だけに焦点:このまま続けても優勝できないから無意味だ
・結果以外にも焦点:以前よりもタイムが縮まってきた、周囲の指揮が上がってきた
継続力をつけるには、継続することで得られる成果物をどれほど多く認知できるかがカギです。
継続により得られたものを見つけて、喜びを感じられるようになってください。
★継続による成果物
・成功すること
・前進すること
・経験を積めること
・自分を知れること
・能力が向上すること
・関係性を広げられること
・関係性を深められること
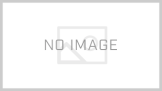
マインド③:継続力は仕組みが9割
「継続できるかは才能である」と考えるほど、継続力は身に付きません。
継続するための工夫を模索せずに、「ありのままの自分がどれほど継続できるか」ばかりを考えてしまうためです。
「継続しやすいもの」を探すならば問題ありませんが、「継続力をつけたい」ならば才能は脇に置いておきましょう。
- 継続しやすいもの:工夫せずに楽しめて続けやすいもの、興味関心、強み
- 継続力をつけたい:好きでなくとも続けたいことを続けるための能力
継続しづらいことを続けるためには、それを楽しむことやサボらないことを促す仕組みが重要になります。
継続しやすいルールや感覚は人によって異なるため、試行錯誤して自分に適した仕組みへと作りこまなければなりません。
- 楽しみための仕組み:上を目指す、意味づけを変える、競争する、報酬を味わう
- サボらないための仕組み:宣言する、目標設定する、環境を変える、危機感を強める
また、「一定期間における行動量」を指標にすることも、継続を考えるときは重要な工夫の1つです。
「継続=毎日コツコツ実施すること」という解釈をしていると、むしろ継続が難しくなる可能性があります。
- 毎日コツコツ:1日10分のウォーキングを毎日おこなう(長距離走的な感覚)
- 短期間にガツン:1日60分のウォーキングを週1度おこなう(短距離走的な感覚)
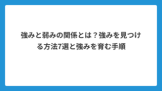
マインド④:手段にやる気を求めない
継続するとき、続けようとする行動自体にやる気を求めないことが重要です。
継続することを楽しむ力は大切ですが、それはオプションに過ぎません。
常に楽しいと感じることは非現実的であり、継続行動にやる気を求めるとすぐに継続を断念することになります。
例.手段にやる気を求める
・勉強:勉強が楽しいから続ける、つまらなくなったから続けない
・運動:動くと調子がよくなるから続ける、疲れたから続けない
継続行動に対しては、「必要or不必要」をベースに考えるようにしてみてください。
「必要だからやる、その上で楽しむ」という順序を守ることで、継続行動に対して無暗にやる気を求めなくなります。
★手段に対するモチベーション
継続したい行動は、「やる気があるからやる」のではなく「やり始めたらやる気が出てくる」という類のモチベーションが重要です。
これは作業興奮と呼ばれる現象であり、一度行動を開始するとドーパミンが分泌されて取り組み続けることが容易になります。
そのため継続したい行動に対しては、「やる気の有無」ではなく「とにかく取り組み始める」ことを意識してみてください。
継続したい行動をやり終えたときに「心地よい疲労感」が残るならやる気がある証拠であり、やる気を探す必要はありません。
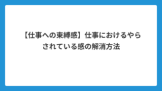
マインド⑤:過去の自分を裏切りたくない
「継続を決めた過去の自分」と「継続しようとしている現在の自分」を区別することで、約束を守ろうとする力が強まり継続が容易になります。
私たちは自分との約束は簡単に破るのに対して、他者との約束はできる限り守ろうとする傾向があるためです。
過去の自分を他者として認識することで、この傾向により継続する動機が強まります。
- 過去の自分:「ダイエットするために毎日15分ウォーキングする」と決めた瞬間の私
- 現在の自分:実際にウォーキングをしようとしてる瞬間の私
- 未来の自分:疲労感がある状態で家事をこなす私
過去の自分を裏切りたくないという気持ちを持つのと同時に、やりきった後のことは未来の自分に任せるようにしてみてください。
行動しようとするときに生じる「でもな」という反論の多くを脇に置いて、”現在”に集中できるようになります。
★過去の自分の奴隷にはならない
過去の自分が決めたことだからと言って、かならずしも守る必要はありません。
それが必要か否かを判断することは、現在の自分の役割だからです。
しかし、過去の自分を大切にするためにも、それを不必要だと判断するにはそれなりの材料が必要になるでしょう。
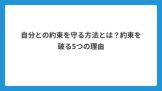
継続力が低い人のよくある行動30選
- 最初から完璧を目指しすぎる: 完璧主義は、小さなつまずきで挫折感を生みやすいです
- 目標が高すぎる、または曖昧すぎる: 具体性がなく、達成不可能な目標はモチベーションを削ぎます
- 計画を全く立てない、または細かすぎる計画に固執する: 無計画は迷走しやすく、過密な計画は柔軟性を失わせます
- いきなり長時間取り組もうとする: 最初は短時間から始め、徐々に慣らしていくのが継続のコツです
- 結果ばかりを気にしすぎる: プロセスを楽しむ視点が欠けると、成果が出ない時期に苦しくなります
- 他人と比較して落ち込む: 自分のペースを守ることが大切です。比較はモチベーション低下の元です
- すぐに効果が出ないと諦めてしまう: 成果が出るまでには時間がかかることを理解しましょう
- 失敗を過度に恐れて行動できない: 失敗は学びの機会と捉え、次に活かすことが重要です
- 一度の失敗で全てを終わりにしてしまう: 失敗は誰にでもあること。そこからどう立ち直るかが鍵です
- 自分を責めすぎる、自己否定に陥る: ポジティブな自己対話を心がけ、自分を励ますことが大切です
- 「時間がない」を言い訳にする: 本当に時間がないのか、優先順位の問題なのかを見極めましょう
- 「疲れている」を言い訳にする: 疲労が原因なら休息が必要ですが、単なる気乗りしない言い訳になっていないか注意が必要です
- 取り組むための環境が整っていない: 集中できる環境、必要な道具が揃っていないとスムーズに進みません
- 誘惑の多い環境で取り組もうとする: スマートフォンやテレビなど、誘惑物は遠ざけましょう
- 睡眠時間を削って取り組む: 睡眠不足は集中力や判断力を低下させ、継続を困難にします
- 適切な休息を取らない: 休息はパフォーマンス維持に不可欠です。燃え尽き症候群を防ぎます
- 進捗や努力の記録をつけない: 記録は達成感を可視化し、モチベーション維持に繋がります
- 定期的な振り返りをしない: 何がうまくいき、何が問題だったのかを分析し、改善することが大切です
- 誰にも目標を宣言しない、またはプレッシャーをかけすぎる人に宣言する: 適度なコミットメントは力になりますが、過度なプレッシャーは逆効果です
- 一人で抱え込み、助けを求めない: 仲間や支援者を見つけることで、困難を乗り越えやすくなります
- 情報収集ばかりして行動に移せない: インプット過多でアウトプットが伴わないと、何も進みません
- 間違った情報や効果の薄いノウハウに頼る: 正しい情報源を見極め、自分に合った方法を選ぶことが重要です
- ご褒美が不適切(大きすぎる、頻繁すぎる、または全くない): 適切なタイミングと内容のご褒美は、モチベーション維持に効果的です
- モチベーションだけに頼りすぎる: モチベーションは感情に左右されるため、習慣化の仕組みを作ることが重要です
- 小さな成功体験を軽視する: 小さな達成感を積み重ねることが、大きな目標達成への自信に繋がります
- 体調管理を怠る: 健康は全ての基本です。不調は継続力を著しく低下させます
- プロセス自体を楽しもうとしない: 義務感だけで取り組むと長続きしません。楽しむ工夫が必要です
- 手段が目的化してしまう: 本来の目的を見失い、作業をこなすこと自体が目的になっていないか注意しましょう
- 自分に合わない方法を無理に続ける: 他の人に効果があった方法でも、自分に合わなければ苦痛になるだけです
- 「頑張っている自分」に満足して具体的な成果を求めない: 努力の方向性が間違っていると、成果には結びつきません
まとめ
継続力をつけるには、自分が継続に失敗するパターンと対策を把握して活用できるようになることが重要です。
誰にでも有効で一瞬で継続できる魔法の杖を探すのではなく、地道に自分に適した継続するノウハウを見つけてみてください。
「私だって〇〇があったら継続できるのに」というのは、たいていがないものねだりです。
それを続けても一向に継続力はつかないため、自分の思考習慣や行動習慣を見直して、「どこにどのようにてこ入れすべきか」という仮説を作り検証することをおすすめします。
「自分マニュアルを作りこむこと」を目的にすると、自分の継続を断念する理由と前向きに向き合えるでしょう。
そうした試行錯誤や継続すべき行動を判断するための目的探しを支援してもらいたい場合は、コーチングを活用してみましょう。