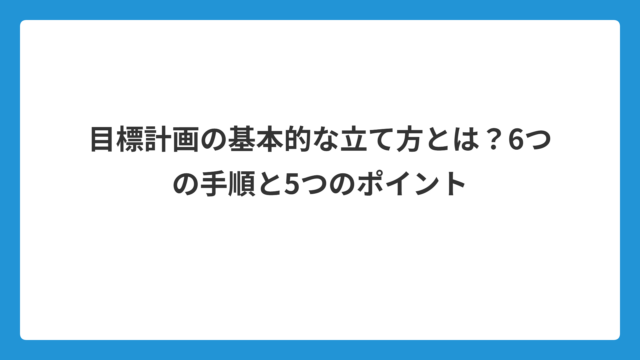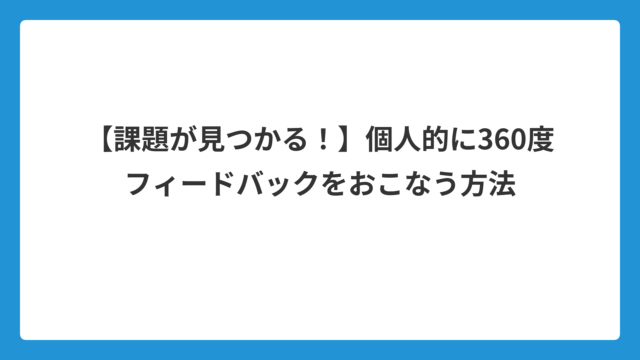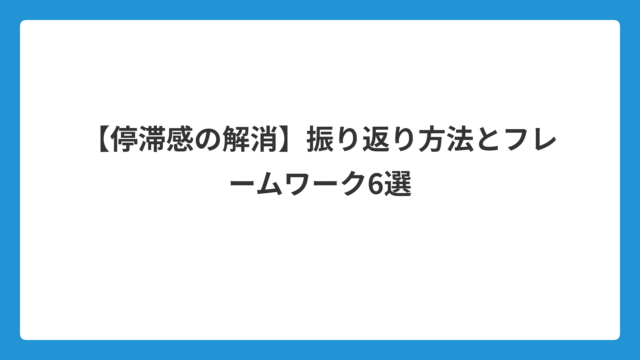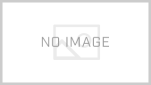欲しい成果や目指したい地点があるとき、目標設定はそれを得るための有効な手段になります。
しかし目標という言葉を聞くだけでなんだか苦しくなり、目標を決めたくない感覚を持つ人は少なくありません。
そんな強い抵抗感を持っていても目標設定をしたいときは、どうすればよいのでしょうか。
この記事では、目標への苦手意識を取り除く方法についてお伝えしていきます。
苦しいけれど目標設定をしてみたいという人は、ここで紹介する内容を取り入れてみてください。
目標設定への苦手意識を取り除く方針
目標設定への苦手意識を取り除くには、目標への嫌悪感の正体を明らかにすることが最初のステップです。
ここでは、目標設定への苦手意識が生じる主な理由についてお伝えしていきます。
★目標への嫌悪感の正体を見定める理由
目標設定をするか悩んだとき、「めんどくさい」「こわい」という感情が生まれます。
この抵抗感は抽象的な感覚であり、本当にその感覚通りの理由で目標設定を先延ばしにしているとは限りません。
目標への抵抗感と折り合いをつけるためにも、抵抗感が生まれる原因を言語化して、目標への嫌悪感の正体を明らかにしてみてください。
・めんどくさい→例.本当はがんばっている姿を他人に見せたくないだけ
・こわい→例.本当は失敗する姿を他人に見せたくないだけ

方針①:束縛感を取り除く
束縛感とは、自分の人生や行動が目標に縛られているような感覚のことです。
自分が決めたはずの目標なのに、時間とともにやらされている感が強まっていきます。
例.目標への束縛感
・人生が目標に振り回されている気がする
・目標を決めると他の可能性が潰えてしまう
束縛感を抱いていると、目標設定が大きな決断のように感じてなかなか「GO」を出せません。
たとえ目標を設定できたとしても、今度は他の選択肢への名残惜しさからやる気がどんどん低下していくでしょう。
この束縛感を取り除くには、目標を手段として活用するマインドが重要です。
そのため、目標を設定する理由と深く向き合う習慣が必要になります。
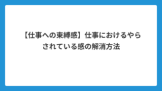
方針②:失敗への恐怖を小さくする
失敗への恐怖とは、目標未達時に生じるペナルティへの恐れのことです。
「目標設定=リスクが大きすぎる行為」と捉えているため、設定するために強い覚悟が必要になります。
例.失敗への恐怖
・不完全だとバカにされる
・夢が叶わなかったら呆れられる
挑戦に伴うリスクを予測することは、ギャンブル的な行為をしないためにも必要な工程です。
しかし、私たちはリスクを過大評価する傾向があり、客観的には小さなリスクでも挑戦する足かせになることがあります。
そのため、失敗への恐怖を小さくするためには、リスクマネジメント力を向上することが大切です。
リスクを見つけるだけで満足するのではなく、そのリスクがどれほど重大なものなのかを把握できる能力を磨いてみてください。
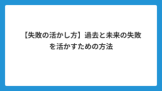
方針③:現状維持バイアスを解除する
現状維持バイアスとは、現状を過大評価して変化した未来を過小評価する認知の歪みのことです。
誰にでも備わっている変化への抵抗感であり、恒常性(ホメオスタシス)とも呼ばれています。
例.現状維持バイアス
・今ある人間関係を壊したくない
・資格取得のためにゲームの時間を減らしたくない
・ブラック企業だけど転職せずにこのままでもいいかな
目標を達成するには、現在とは異なる行動や思考が必要になります。
しかしその変化を負荷だと感じてしまい、「目標設定=ラクの阻害要因」と捉えて苦手意識を持ってしまうのです。
現状維持バイアスを解除するには、自分の意識を理想の未来に置くことが重要になります。
理想の未来から見なければ現状に不満を感じることができず、目標を追うことを強い負荷だと認識してしまうためです。
自分にとっての当たり前を明確にして、それを更新することで目標設定への抵抗感が和らぎます。
★部屋をきれいにしたい人における意識の位置
・現状に置く:いつも通りの部屋。これでも快適なのだから掃除する必要がない
・理想の未来に置く:汚い部屋。いつも通りのきれいな部屋に戻すだけ
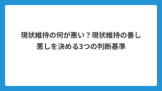
束縛感を取り除く方法3選
ここでは、目標に対する束縛感を取り除く方法についてお伝えしていきます。
束縛感①:初志貫徹をやめる
目標への思い込みの1つに、一度決めた目標は達成するまで継続すべきだというものがあります。
たしかに、「絶対にやりきってやる」と覚悟や情熱を持つことは、その後の粘り強さを生むために大切です。
しかし、「やるorやらない」を決める段階では、この初志貫徹マインドがむしろ覚悟を決める足かせになりかねません。
一度決めたら最後までやりきらなければならず、目標設定を呪いのように感じてしまうのです。
- 初志貫徹のメリット:継続しやすい、挑戦に慎重になれる
- 初志貫徹のデメリット:始めづらい、方向転換しづらい
「目標設定したからやらなければならない」のではなく「理想を実現したいから目標設定を活用する」という考え方がおすすめです。
そのような考え方を維持するには、次の2つの期間を繰り返すことが有効になります。
- 自分と向き合う期間:「私にはこの目標が今でも必要か」を検討する期間
- 達成のために動く期間:設定した目標達成行動を全力でおこなう期間
「検討する機会が来るたびに目標は手放せる」という認識を持てれば、目標設定を呪いのようには感じなくなります。
少なくとも四半期に1度は、今の目標が必要か否かを検討してみてください。
★サンクコスト効果
目標を手放せなくなる理由の1つに、サンクコスト効果があります。
サンクコスト効果とは、「ここまで取り組んだのにやめるのはもったいない」というような、すでに支払ったコストを惜しむ感覚のことです。
このサンクコスト効果に強く影響される人は、「一度で成功しないとすべて無駄になる」と考えやすく、目標設定や再設定に慎重になる傾向があります。
目標に縛られないためにも、成功以外の成果物を見つける能力を養い、サンクコスト効果の影響を弱めてみてください。
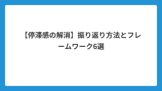
束縛感②:目標を身近なものにする
目標に対して束縛感を感じている人は、目標自体を特別視している傾向があります。
「何か大きなことを成し遂げるときにだけ目標設定をするんだ」と考えて、目標が遠い存在のように感じているということです。
しかし実際は、私たちは無意識的に目標設定を活用しながら生活しています。
★目標設定の例(目標→行動)
・遅れずに出勤しよう→1本早い電車に乗る
・面白い動画を見て癒されたい→スマホを操作する
・のどか湧いたから水を飲みたい→コップを手に取る
目標設定は誰にとっても身近なものであり、特別な技術ではありません。
無意識的な目標設定を、意識的におこなってみようというだけなのです。
「目標設定は自分とは縁のない存在だ」という違和感を抱いているのであれば、意識的に目標設定してから普段の無意識的な行動をおこなってみてください。
目標設定が身近なものだと感じられるほど、目標への束縛感が弱まり1つのツールに過ぎないと感じられるようになるはずです。
★小さな目標達成のメリット
普段の無意識的な行動を、あえて目標設定してから行動することでセルフイメージが高まります。
有言実行を続けることで、「自分との約束を守れる私」という自分像を持てるようになるためです。
そしてその自分像は、より大きな目標に対しても「私ならなんとかできるかもしれない」と自信を持つことにつながり、挑戦することへの意欲を高めるでしょう。
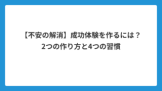
束縛感③:理想のあり方を明確にする
私たちは、どういう振る舞いをしたいのかという理想のあり方を持っています。
目標達成するという振る舞いへの認識が、自分の理想のあり方に反するとき、目標に対して強い抵抗感が生じます。
例.理想のあり方とのギャップ
・理想のあり方:のびのびとしていたい、自由でありたい
・目標達成への態度に対する認識:焦っているみたい、ガツガツしているみたい
理想の在り方とのギャップを小さくするには、理想のあり方を明確にすることが最初のステップです。
たいていは抽象的であるため、より具体的なものへと言語化してみましょう。
★理想のあり方を明確にするための問い
・私はどんな自分が好きか?
・私はどんな振る舞いをしたいのか?
・私は周りにどんな影響を与えたいのか?
・私は周りからどんな評価を受けたいのか?
・私はなぜそのあり方でありたいのか?
・誰からも絶対に好かれるとしたらどういうあり方でありたいのか?
理想のあり方を明確にしたら、そのあり方に相応しい目標達成のシナリオやルールを作ってみてください。
「自由でありたい」のであれば、その自由であり続けられる目標達成の態度を検討してみるのです。
理想のあり方にマッチする自分なりの目標達成のシナリオやルールを作れれば、目標設定はそのあり方を阻害する要因ではなくなって抵抗感が小さくなります。
★言葉の定義を明確にしよう
理想のあり方を探っていくと、重要なキーワードが出てきます。
しかしそのキーワードは辞書通りの意味ではなく、自分のニュアンスで使っている言葉です。
そのキーワードをどのような意味で使っているのかを考えて、自分の言葉で定義化してみてください。
・自由でありたい:働かない、無理しない、興味を活用する、時間に縛られない、自分で舵を取る
・ユニークでありたい:発明をしたい、自分でレールを引きたい、大切なことを大切にする人生にしたい
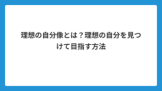
失敗への恐怖を小さくする方法3選
ここでは、目標未達時の恐れと折り合いをつけるための方法をお伝えしていきます。
失敗①:相談相手を見つける
心の支えとなる上司、先輩、講師、メンターなどを探してみてください。
「問題が起きてもこの人に尋ねれば何とかなる」という安心感を得ることで、失敗することを意識から外せるようになるためです。
また、たとえ失敗したとしても「自分1人だけの責任ではない」と考えられ、前向きな気持ちで結果と向き合いやすくなります。
- 講師:問題に精通して指導してくれる人
- メンター:自分の目指している未来をすでに実現している人
ただし、相談相手に疑心を持ってしまうと、アドバイスやフィードバックを受け入れられなくなります。
相談相手を見つけるときは、「その人を信頼したいか?」を最重要の判断基準として探すようにしましょう。
★保証依存症
目標の達成確率を高める手段として、相談相手を見つけることは有効です。
しかし、「相談相手がいるからがんばれる」「相談相手がいないとがんばれない」は異なることに注意しなければなりません。
指導者がいないと行動できないというのは、失敗責任を他者に押し付けたいという保証依存症です。
そのような過度な他責思考を持っていると、次のようなデメリットが生じます。
・経験を成長に活かせない:自分は悪くないから改善意欲が上がらない
・指導者とよい関係を築けない:成果は自分のおかげ、失敗は指導者の責任
・教わる態度がふてぶてしくなる:お客様感覚
相談相手を見つけることは、あくまで成功しやすくなるための手段です。
目的が「保身」であるならば、まずはその保身を優先しようとする背景と向き合う必要があるでしょう。
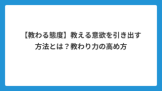
失敗②:失敗の数を見積もる
1度の挑戦で成功しようとすると、失敗への恐れが強くなり慎重になるものです。
しかし、自分にとって困難な挑戦であるほど、何度も試行錯誤が必要になりすんなりとは成功できません。
失敗を許容して何度も試行錯誤するには、必要な失敗回数を見積もることをおすすめします。
- 失敗ゼロを前提とした挑戦→完璧主義的、能力主義的、目的が失敗しないことになる
- 複数の失敗を前提とした挑戦→成長主義的、目的が成功にたどり着くことになる
もしも失敗回数を見積もった時点で挑戦への抵抗感が生じるのであれば、失敗への意味づけがネガティブなことが理由だと考えられます。
その場合は失敗を恐れる理由を明らかにして、その理由が現実的なのかを検証してみてください。
実際の成功者がどれほど苦労して今の地位を築いたのかを調べることは、失敗をポジティブなものとして捉えるための役に立つでしょう。
★失敗させない覚悟
「失敗を前提とすること」と「失敗させない覚悟で挑むこと」は別物です。
失敗を前提としつつも、試す仮説を成功させるつもりで試行錯誤するようにしましょう。
・失敗を前提とすること→成功までには100の失敗が必要だろう
・失敗させない覚悟で挑むこと→今回試す仮説を粗雑に扱わない、どうせ失敗すると考えて手を抜かない

失敗③:最悪の未来を想定する
失敗への耐性を高めるためには、失敗による損失を評価することが有効になります。
致命傷を見極めることで、それ以外の失敗に対して軽く流せるようになるためです。
- 損失の評価をしない→すべての失敗は危険で怖い
- 損失の評価をする→この失敗は危険で怖い、この失敗は大して痛くない
ただし、失敗は無数にあり、すべてのパターンを評価することはできません。
まずは最悪の未来を予測して、それがどれほど深刻であり起こりやすいのかを確かめてみてください。
最悪の未来が深刻である場合は、次のようなことを検討してみることをおすすめします。
- なぜそれが深刻だと感じるのか?(本当の恐れの正体とは)
- その最悪の未来が生じたら挽回できないのか?
- その最悪の未来での損失を抑えるにはどうすればよいのか?
- その最悪の未来が生じる可能性を抑えるにはどうすればよいのか?

現状維持バイアスを解除する方法3選
ここでは、現状維持バイアスを解除するための方法をお伝えしていきます。
現状維持①:延長線上の未来を想定する
現状維持バイアスは、現状に対する認識を楽天的なものにさせます。
そのため、「このままだとどうなるのか」と延長線上の未来を再評価することは、目標設定を促す動機として役立つでしょう。
例.転職するか否かの悩み
・現状維持バイアス:このままでもなんとかなるか、機会があったら考えよう
・延長線上の未来の再評価:このままだと心が病むだろう、収入は300万円どまりだろう
「このままがいい」のか「変化が嫌」なのかを明確にしてみてください。
今のままで欲しいものが手に入らないのであれば、リスクを冒してでも現状を変える必要があるかもしれません。
変化が嫌なのであれば、本当の望みを言語化して、その望みを手に入れることへの抵抗感と向き合ってみましょう。
- このままがいい→現状維持が本当の願望、どうすれば現状維持できるかを考えよう
- 変化が嫌→損失回避的な欲求、本当の願望は現状維持ではない
★現状維持への期待
「現状維持を続けていればいつかは欲しいものが手に入る」と期待することがあります。
継続することは大切ですが、それが現実的な確率であるかは確かめる必要があるでしょう。
現状の方法を続けるかを検討するときは、あらかじめ損切りタイミングを仮決めしておくことをおすすめします。
・ギャンブル→続けていれば勝てるかもしれないが、コストを回収できる確率は非現実的
・恋人づくり→今まで振り向かれなかったのだから、このままでは関係性を変えられない
・3年間続けたブログ→続けていればバズるかもしれないが、3年続けても収益化できていないなら戦略を練り直したほうが成功確率は高まる

現状維持②:許容できる負荷を確かめる
目標達成のための行動には、必ずといってよいほど「嫌だな」と感じるものが含まれています。
普段とは異なる行動は負荷に感じやすく、その行動に伴うネガティブな側面ばかりに注目してしまうためです。
例.ダイエットのために運動をするときの「ネガティブな側面」
・汗をかいている姿を他人に見られたくない
・自分の体重を見るたびに気持ちが萎えてしまう
・毎日5km歩くと仕事に支障が出てしまいそうだ
とはいえ、自分が負荷に感じるものすべてに対して、真正面から打破することはおすすめしません。
「〇〇は嫌だけど、△△までなら大丈夫かも」という境界線を見極めたほうが、早く行動に移せるためです。
- 真正面から打破:汗をかいている姿を晒しても動揺しなくなる
- 境界線を見極める:スポーツジムの人になら汗をかいている姿を晒してもいいかも
何かを嫌だなと感じて目標設定を渋ってしまうときは、白黒思考で考えるのではなく、許容できる負荷を確かめてみてください。
どういう条件なら実行可能かを検討することで、恒常性を抑えながら変化を起こせるようになります。
★「嫌な行動」へのおすすめの対処手順
1.まずはやってみる
2.やっても「嫌だ」と感じたら境界線を探る
3.境界線を探っても行動できないなら信念の変容を促す
→「嫌だ」の本当の理由を明確にして検証する

現状維持③:負荷を許容できる環境を整える
現状よりも負荷がかかる行動に対して、恒常性が働きます。
そのため、「自分にとっての当たり前」を更新することは、恒常性を抑える方法として有効です。
- 現状の当たり前:運動しないのが当たり前、毎日10分のウォーキングでもきつい
- 学生時代の当たり前:運動するのが当たり前、10分のウォーキングなんて朝飯前
自分にとっての当たり前を更新する最も簡単な方法は、基準が高い集団に属することです。
理想の自分像に近い人たちが多く所属しているグループに加入してみてください。
私たちが持つ「当たり前」と捉える基準には外部から影響を受けやすいという特性があり、その集団が持つ基準を自分のものとして取り入れられます。
行動することへの心理的抵抗感が和らぎ、むしろ行動しないことに対する抵抗感が強まるでしょう。
- 勉強するのが常識の集団:毎日1時間は勉強するのが当たり前、勉強しないのは恥ずかしい
- 勉強しないのが常識の集団:毎日勉強するなんてありえない、勉強するのは恥ずかしい
★高い視座は持続しない
視座を高めることで、視座の低い行動すなわち目標達成を阻害する行動への抵抗感が強まります。
これは自分にとっての当たり前が更新された結果によるものです。
視座を高める方法の1つとして「理想の自分像を意識すること」が挙げられますが、他のタスクを実施したら理想の自分像が頭から抜け落ちてしまうため、この試みはたいてい三日坊主で終わります。
視座を高く持続するためには、理想の自分像に近い集団に属し、定期的に他者からの刺激を受け取ってみてください。
理想の自分像の代理人としての他者や集団を見つけることで、視座が下がってもすぐに高い位置に戻せるようになります。
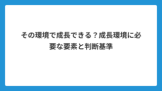
目標設定に対するよくある疑問5選
ここでは、目標設定に拒絶反応を示す人が持ちやすい疑問についてお伝えしていきます。
疑問①:自己否定と何が違うの
設定した目標を達成するには、自分の行動や思考を変えることが求められます。
それに対して「自分を変える=自己否定」と捉えてしまい、目標設定に抵抗感を示してしまうのです。
- 目標設定=自己否定→自分は悪くないのに自分が変わる必要なんてない
- 目標設定=自己変容→今のままでは欲しい成果を得られないから手段を変える
しかし、行動や思考には善悪はなく、重要なのは「現状維持がよい」のか「今とは異なる成果が欲しい」のかです。
どんな方法を実施するのかという「手段」ではなく、求める成果や理想の未来などの「目的」に焦点を合わせてみてください。
「悪いから変える」のではなく「得るために必要だから変える」という捉え方をすると、自己変容に対して前向きになれます。
また、外部要因を固定的なものとして捉えると、自分の行動や思考を変えることへの態度が軟化しやすいです。
- 外部要因は固定的だ:周りは変わらない状況でその成果が欲しいなら私が変わるしかない
- 外部要因は変動的だ:私は悪くないのだから周りが変わるべき
★自己否定的な目標設定
「自分が悪いから」「ダメだから」という理由で目標設定をすることはおすすめしません。
自己否定的な目標設定だと、達成するまでの過程をすべて苦行に感じ、たとえ達成されても充実感は一時的で終わるためです。
目標設定をするときは、その目標を達成したい理由について深く検討してみてください。
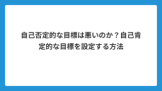
疑問②:チャンスをとり逃しそう
目標設定をすると、チャンスをつかみ損ねるという考え方があります。
設定した目標だけに焦点を合わせるため、周りにある機会を見つけられない、または機会を活かす余力がなくなるという考え方です。
例.漫画家になるという目標
・機会を見つけられない:バーに行ったら編集者と出会えるかもしれない、ビジネスマンとして成功する可能性がゼロになるかもしれない
・機会を活かす余力がなくなる:編集者と出会っても商談をする余裕がない、気の合う異性と出会っても友達止まり
しかしこれは、目標設定をしない人生を楽天的に考えすぎです。
目標設定をしない自分がどんな生き方をするかは、夏休み中や大学時代の自分の行動を振り返れば明らかでしょう。
チャンスを逃すと危惧するときは、目標設定しない人生だったらどうなるのかを現実的に考えてみてください。
- 目標設定をした自分はどんな未来になるのか?
- 目標設定をしない自分はどんな未来になるのか?
また、「目標設定=すべての時間を費やすべきだ」と白黒思考で考えると、チャンスを逃すという考え方になりやすいです。
チャンスをつかめる余力を持ちつつ、目標達成のための行動ができるというバランスを検討してみることをおすすめします。
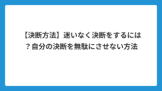
疑問③:生き方が楽しくなさそう
目標設定をすると大変そうで、生き方が楽しくなさそうという意見もあります。
たしかに目標設定をすると、達成行動が義務的に感じますし、負荷のかかる行動が求められるため大変だと感じやすくなるでしょう。
しかし、「負荷がかかり大変である=楽しくない人生」とは必ずしも成り立たないことに注意する必要があります。
★目標設定のメリット・デメリット
・メリット:行動に意味を見出せる、リソースを割くべき方向性が明確になる
・デメリット:義務感を抱きやすい、疲れる行動が求められる、進捗に一喜一憂する
この疑問において重要なことは、どんな人生を自分が求めているのかを明らかにすることです。
楽しいだけの人生も、つまらないだけの人生も滅多に存在しません。
だからこそ、どういう人生を築くついでに楽しさを感じたいのかを検討することが大切になります。
例.自分にとっての素晴らしい人生
・常に冒険していて刺激的な人生を過ごしたい
・安心感を抱くような家族と平和な人生を過ごしたい
・自分の才能を最大化していけるところまで到達してみたい
目標設定とは、自分にとっての素晴らしい人生を築くための手段の1つです。
目標設定の有無だけで、人生が楽しくなったりつまらなくなったりするものではありません。
「目標設定をすると人生が楽しくなくなる」と感じたら、そもそも自分はどんな人生でありたいのか、どうやったらその人生を歩めるのかを検討してみてください。
★理想の人生は仮説である
理想の人生を描いても、それは仮説の1つにしかすぎません。
「ずっとダラダラゲームする人生でありたい」と心から望んだとしても、実際にそのように生きたらすぐに飽きてしまうことがあります。
そのため、人生の理想像を描いたら、本当にそれを自分が求めているのかを検証することが大切です。
検証方法としては、次の2つの方法を両方おこなうことをおすすめします。
・お試しとしてその人生を歩んでみる:1週間有休をとってずっとゲームだけをしてみる
・その人生を歩んでいる人を観察する:50歳で1日中ゲームしている独身を見て同じ人生を歩みたいかを考える
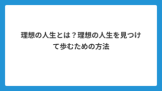
疑問④:余裕がなくなり不機嫌になりそう
目標設定をすると、達成への焦りによって余裕がなくなることがあります。
実際に「趣味としてなら楽しめたのに、それを本気で取り組み始めてからは楽しむ余裕がなくなった」という経験をした人は少なくないでしょう。
成果を得るための行動からは報酬感を受け取りづらく、ストレスが溜まって不機嫌になりやすくなるものです。
- 目標達成:勝ちたい、成長したい、それを実施するだけでは物足りない
- 趣味感覚:負けても成長しなくても気にしない、それを実施できることが楽しい
しかし、厳密にいうとこれは「目標設定」ではなく「目標達成能力の低さ」の問題です。
「得られたもの」ではなく「不足しているもの」ばかりに焦点を合わせてしまう能力の低さが、余裕のなさを生みます。
そのため、目標設定で不機嫌になってしまうことを危惧している場合は、目標達成能力を上げることを目指してみてください。
★不機嫌になりたくないときの対処法
・対処法1:義務感のある目標を手放す(本当はどうしたい?)
・対処法2:ポジティブフィードバックなどの報酬を提供してくれる相手と目標達成を目指す
・対処法3:目標設定しても余裕を持てるようにメンタルをコントロールする術を身につける
目標達成能力を上げるには、コーチングを受講することをおすすめします。
自分に合った目標設定や計画立て、行動から報酬を得る支援や本当の問題を見つける支援など、目標達成に関する適切な手助けをしてもらえるためです。
そうしてよりよい目標達成を繰り返していくことで、自分1人でも余裕を持ちながら目標達成を目指すことができるようになります。
★目標達成を楽しむには
目標達成の過程を楽しむには、「よりよくなるにはどうすればよいのだろうか?」という視点を持ち続けることが重要になります。
その視点を持っていることで、「仮説検証」と「成果の実感」が報酬感になります。
・仮説検証:何を試してみたいか、自分なりの工夫
・成果の実感:行動から何を得られたか、問題点や成長ポイントなど
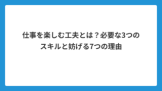
疑問⑤:思い付きの行動のほうが生産性が高まりそう
計画的な行動よりも、思い付いた行動を片っ端から実施したほうがよいのではないかという疑問があります。
たしかに「やってみたい!」と思った行動は、モチベーションが高く生産性が高まりやすいです。
- 直感的な行動:やる気がある、自分の欲求に従っている感覚がある、熱が冷めやすい
- 計画的な行動:やる気が出づらい、衝動を抑えなければならない
しかし、直感的な行動は「未知の体験」にばかりアンテナが立ちやすいという傾向に注意しなければなりません。
たとえば「プロのバスケット選手になりたい」と直感的に思ってバスケを始めても、1カ月もすればその熱は冷めてしまいます。
すぐに別のことに関心が向き、始めては辞めてを繰り返して何も極められない「飽き性」というレッテルを貼られるようになるでしょう。
ここで重要なことは、どちらか一方だけではなく次のように使い分けをすべきであるということです。
- 直感的な行動の活用:やりたいことややってみたいこと、どんな人生でありたいのかを探るとき
- 計画的な行動の活用:やりたいことを仮決めしたら目標設定をして計画的に前進してみる
自分の直感を大切にしたいフェーズなら、どうやったら興味関心がもっと湧くようになるのかを検討してみてください。
そして、小さな興味関心を察知できるようになるとともに、それを実行する行動力を養いましょう。
「もっとがんばってみたい」というものに出会えたら、それは目標設定をして計画的な行動を始める合図になります。
★興味関心と惰性の混同に注意
「やりたいからやる」と「他にやることがないからやる」は別物です。
取り組もうとしていることが興味関心によるものか、惰性によるものかを区別するようにしてください。
一定期間実施してもまだやりたいと感じているならば、それを続けたい理由を内省してみましょう。
「目標設定のような負荷は嫌だ」というならば、それは惰性である確率が高いです。
・興味関心:面白そうだからゲームをやってみたい
・惰性:やることないからゲームをしよう、依存
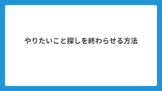
苦しくなる目標設定の4パターン
ここでは、よく起こりがちな目標設定の失敗例についてお伝えしていきます。
パターン①:衝突する目標を立てる
衝突する目標とは、「欲しい未来A」と「欲しい未来B」がトレードオフのような関係な状態です。
「”欲しい未来A”を得るために”欲しい未来B”を諦めなければならない」という思いから、目標達成行動へのモチベーションが低下してしまいます。
例.衝突する目標
・子供は欲しいが結婚はしたくない
・家族を養いたいが趣味も大切にしたい
・自由でありたいがビジネスマンとしても大成したい
大切にしたい目標が衝突するときは、どちらを選んでも後悔するものです。
目標達成への粘り強さがなくなったり、過度な成果主義になったりしてしまいます。
- 粘り強さの低下:やっぱり欲しい未来Aを選ぶべきだったかな…と悩み続ける
- 過度な成果主義:欲しい未来Aを諦めたのだからすべてを失ってでも欲しい未来Bを手に入れなければ
この問題を解決するには、まずは衝突する目標を明らかにして、それらが本当に自分が欲しいものなのかを検討してみてください。
自分が欲しいものではなく、社会や世間が求めるものである場合は、その目標を手放すことで衝突がなくなります。
どちらも自分が欲しいものである場合は、次のうちのいずれかをおこなってみるとよいでしょう。
- 両取りする:欲しい未来Aと欲しい未来Bを同時に手に入れられる目標を設定しよう
- 優先順位をつける:まずは欲しい未来Aを手に入れてから欲しい未来Bを叶えよう
★目標の両取り
固定観念からトレードオフのような関係だと思い込んでいることがよくあります。
そのため、衝突する目標が見つかったら、両取りできないのかを検討することで新しい選択肢が生じることがあります。
・欲しい目標A:趣味を大切にしたい
・欲しい目標B:収入を増やしたい
・新しい選択肢C:短時間で大きく稼げる事業を起こそう
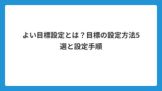
パターン②:大きすぎる目標を立てる
分かりやすい地点を目標にしようとして、私たちは大きすぎる目標を立てやすい傾向があります。
しかし、現状から離れすぎている目標は「大変そう」「どうせ無理」という感覚を生み出しモチベーションを下げる原因です。
目標設定をするときは、「自分にでもなんとかできそうだ」という簡単すぎず難しすぎない程よい難易度調整が重要になります。
- 夢:叶うか分からないけどこうなれたらうれしい!
- 程よい目標:がんばればなんとかなるかも、失敗してもバカにされないだろう
- 簡単すぎる目標:こんなの朝飯前だから後でやろう、失敗したらバカにされるかも
- 難しすぎる目標:どんなにがんばっても無駄だから諦めよう
達成困難な目標を設定してしまったら、階段を作るように小さな目標に分解してみてください。
そのためにも現在地を明確にして、ゴールにたどり着くまでのストーリーを描くことが大切になります。
自分なりの仮説的なストーリーができあがれば、大きすぎる目標に対してもモチベーションが高まるはずです。
★渾身の目標は探さない
自分の人生に意味を見出せるような、「これぞ」という渾身の目標はそう簡単に見つかりません。
そういった目標は、たくさんの目標に手を出しながら自己理解を深めることで見つかるものです。
目標が見つからないときは、渾身の目標ではなく、興味関心を活かした目標を設定してみてください。
「今はこれが気になるから3カ月後はこうなっていたい」という程度の軽い気持ちで目標を立てつづけることで、渾身の目標が見つかりやすくなり、また目標達成能力が上がっているため実現しやすくなるでしょう。
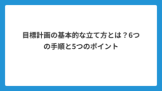
パターン③:ノルマと目標を混同させる
ノルマと目標は別物です。
これらを同じものだと考えると、目標への義務感が強まりモチベーションが低下します。
- ノルマ:達成しなければならない下限
- 目標:達成したい地点
ノルマは達成しなければなりませんが、目標は達成しなくても問題ありません。
その方向に進む道しるべ的な役割であり、前進する力を強めるための制約のようなものだからです。
- 目標なし:ただ単にいつも通りの野球をするだけ
- 目標あり:地区大会で優勝できるように野球を練習する
設定する目標は「絶対に超えるべき基準」よりもさらに上の地点に置きましょう。
そのためにも、目標の成果は6割~8割に留まるという前提を持つことをおすすめします。
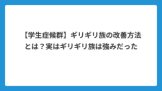
パターン④:目標達成できるコンディションではない
目標設定に抵抗感が生じているのは、元気のなさが原因の可能性があります。
心身に元気がない状態では、どんな目標も苦しみばかりを生み出してしまうものです。
そんな状態でどんなに自分の本心からの目標設定ができても、余力のなさから悪い方向に進んでしまいます。
- 元気な状態:欲しい未来を考えたり他者や自分を気にかけたりする余裕がある、前進の期間
- 非元気な状態:現状から逃げ出したい一心、他者や自分の状態を把握できない、回復の期間
目標を持つことには多くの活力が求められるため、まずはコンディションを整えることから始めるようにしてみてください。
ただし、単に休むだけだと身体は元気になっても、心にエネルギーが戻りません。
コンディションを整えるときは、現状に適したリフレッシュ方法を実施することが大切です。
- 身体の回復:休む、寝る、ストレッチ、軽い運動、タスクの断捨離、タスクの効率化
- 心の回復:休む、寝る、軽い運動、他者との交流、刺激的な体験、ストレス源を取り除く
コンディションを整えるタイミングでは、「何かを得ること」ではなく「より快適になること」を目指してみましょう。
退屈感を抱き、他に興味関心が持てるほどの余裕ができたら、改めて「何かを得るため」の目標を探してみることをおすすめします。
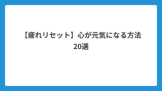
まとめ
目標設定への苦手意識を取り除くには、その苦手意識の正体を明らかにして折り合いをつける必要があります。
まずは、「なぜ私は目標自体をそこまで嫌うのか」を言語化してみてください。
正体が明らかになったら、自分の過去や周囲の人、論文などを参照してその原因を検証することで折り合いをつけやすくなります。
ただし、私たちは自己正当化のプロであり、「目標=悪であるべきだ」という前提を持っているとどんな証拠を見つけても苦手意識は覆せません。
そのため、「なぜ私は目標が必要なのだろうか」と自問自答して、目標設定をすることによる期待を明らかにしてみることをおすすめします。
「目標は自分にとって必要かもしれない」と目標を受け入れられたら、改めて目標設定の苦手意識の正体と向き合ってみましょう。