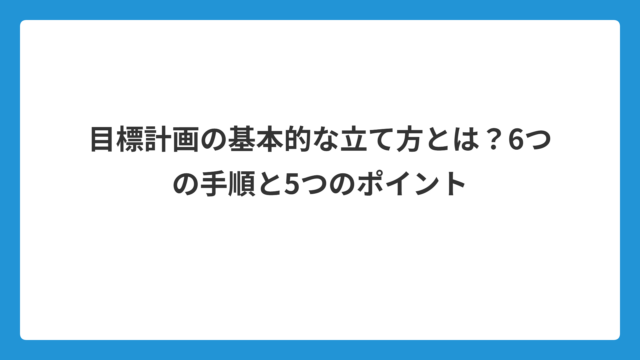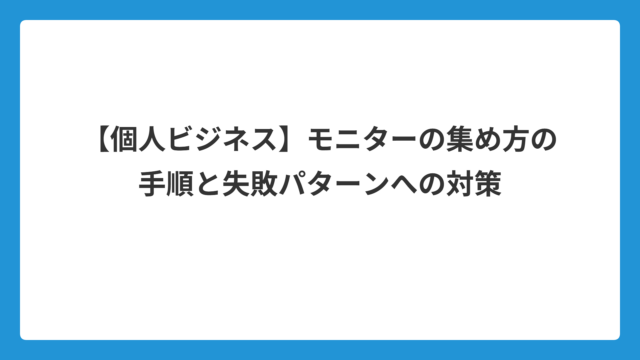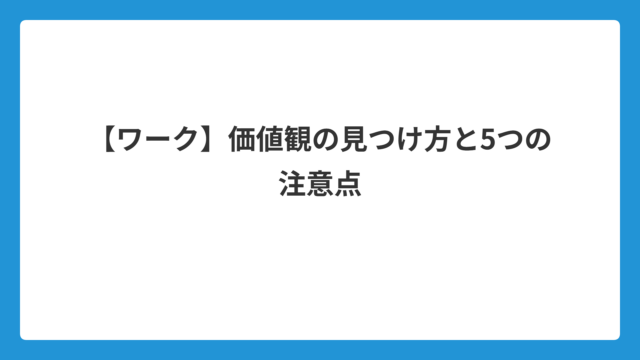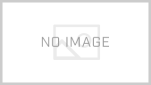自分にとっての幸福な人生を築く戦略は、主に次の4つが挙げられます。
- 現状維持型
- 目標達成型
- 興味関心型
- スピリチュアル型
この記事では、上記4つの戦略について紹介していきます。
また、目標達成型に関する基本的な要素や手順、阻害要因についてもお伝えしていきます。
理想とは何か
理想とは、制限を外した状態で想像できる最高の未来のことです。
ただし夢想とは異なり、現実的であり、自分軸による願望が核心にあります。
- 夢想:非現実的、または世間や他者の願望をコピーした未来の姿
(例.宝くじを当てて贅沢三昧な生活をしたい) - 理想:現実的、自分の素直な願望による未来の姿
(例.家族が帰ってきたいと思える場所を築きたい)
「こうなりたい」「こうありたい」という理想は、たいてい現状の延長線上には存在しません。
理想を実現するには人生にてこ入れをする必要があり、そのための戦略が以下の4つです。
- 戦略①:現状維持型
- 戦略②:目標達成型
- 戦略③:興味関心型
- 戦略④:スピリチュアル型
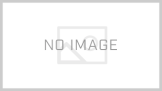
理想を実現する4つの戦略
ここでは、理想へ目掛けて人生にてこ入れをする4つの戦略をお伝えしていきます。
「これを選択すべきだ」という確かな方法はありません。
戦略と目的を入れ替えないように注意して、戦略の検証を徹底するようにしてください。
- 目的の入れ替わり:「この方法で幸せになりたい」と方法に固執すること
- 戦略の検証:期間ごとに効果を確かめて、その方法をまだ採用し続けるかを検討すること
戦略①:現状維持型
現状維持型とは、今まで通りの過ごし方を継続することです。
もっとも採用されやすい戦略ですが、もっとも無意識的に選ばれやすくもあります。
★現状維持型のメリット
・未来を予測しやすい(このままだとどうなるだろうか)
・新たな仕組みが必要ない
・停滞するよりかはマシなことが多い
・現状維持を決めきってしまえば余計な思考をせずにラクになる
また、よくある誤解に「現状維持=悪」というものがあります。
しかし実際は、現状維持が悪なのではなく、現状維持における予想と実際に差分があることが問題です。
- 予想:いつもの日常を過ごしていれば幸せであり続けられるだろう
- 実際:今は幸せではなく暇つぶしをしているだけ、現状が破壊される出来事に対する無防備さ
無意識的に選びやすい現状維持型だからこそ、この戦略を採用するときは仮説を設定してください。
「どこを目指したいのか/このままだとどうなるのか/なぜこの戦略なのか」などを検討して、惰性的な選択にならないようにしましょう。
★現状維持型を選択するよくある理由
・変化することへの恐れ
・人生を変えることへの無力感
・現状が幸せであり、そのための維持
・変化するためのコストへの不安や恐れ
・ベストなタイミングが訪れるまでの待機
・現状を続けた先に幸福が待っているという期待
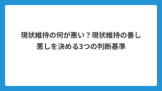
戦略②:目標達成型
目標達成型とは、理想を構築する要素を分解して、それらを満たすための計画を立て実施することです。
一般的な目標達成であり、受験や会社ではよくこの戦略で前進することを目指します。
★目標達成型のメリット
・選択と集中ができる
・未来を予測しやすい(計画が実行できば成果を得られやすい)
・必要なものや条件をそろえやすい
しかし、必ずしも想像した理想が本物であるわけではなく、核心をついているわけでもありません。
また、「できそうなこと」で目標を立てやすく、延長線上の未来から大きく変わりづらい傾向もあります。
★目標達成型のデメリット
・理想を固定してしまう:理想は経験や時間によって変化するのに、それを否定して固執する
・変化の幅が限られている:今よりもよい収入、いい偏差値など延長線上の変化にとどまる
・大切なものを見誤っている:数値的な見栄えに振り回される、目標と目的の混同
目標達成型は、現状を変える力があり、誰もが簡単に選択できます。
ただし活用する際は「何を目指すのか」「何故目指すのか」という目的地を見誤りやすいことには注意してください。
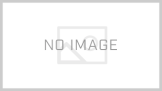
戦略③:興味関心型
興味関心型とは、やりたいことに没入することで人生を変える戦略です。
一般的に興味関心型の理想の地点は、それを継続するための手段でしかありません。
たとえば野球を続けたいからプロ野球選手になりたいのであり、プロ野球選手になるために野球を続けているのではないということです。
- 打算的な行動:何かを得るための手段としての行動
- 目的的な行動:その行動自体が手段でもあり目的でもある行動
興味関心型は、一般的に憧れられる理想への進み方です。
「好きでやっていて、気づいたら大きな成果を得ていた」という類の成功であり、私たちの多くはそれこそが理想の生き方だと考え、そうした没入できる何かを探してしまいます。
★興味関心型のメリット
・行動に没入でき常に充実感がある
・打算的ではなく純粋な生き方のように感じられる
・成長することにも失敗することにも喜びを見出せる
しかし、よく聞く成功談のように没入できる何かを見つけることは容易ではありません。
また、興味関心があったとしても、それの強度が低かったり、お金に結び付かなかったりすることもよくあります。
★興味関心型のデメリット
・好きの強度が低い:ちょっとした困難で興味が失われる。関心ごとを育む力は別
・お金に結び付かない:極めたからと言って収入に結び付くわけではない分野もある
・簡単には見つからない:探したからといって見つかるものではない
・惰性と勘違いしやすい:「好き」と「習慣」や「暇つぶし」を混同して同じ行動を続けてしまう
興味関心型は人生を豊かにするほどの情熱をもたらしますが、それが仕事になるとは限りません。
「やりたいこと」がないのであれば、「興味関心ごとを探す」だけでなく、「今やっていることから好きを探す」ことにも挑戦してみてください。
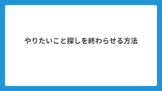
戦略④:スピリチュアル型
スピリチュアル型とは、直感的、または伝統的な方法を用いて人生を変える戦略です。
考え方が根本から異なり、目標達成型とよく対比されます。
- 目標達成型:設定した目標に対する行動を実施すれば人生はよりよくなる
- スピリチュアル型:目標は設定しない。よりよく生きれば自然と人生は好転する
「元気であれば好機が訪れやすくなる」「人は各自のルールに則って生きており他者を気にする必要がない」など、受け入れられやすい考えもあり、ロジカルではないとは言い切れません。
しかし、水素水や量子力学などの科学者を敵に回す発言も多く、スピリチュアル型は好き嫌いが特に分かれる戦略だと言えます。
とはいえ、スピリチュアル型でも成功している人がいるのも事実です。
目標達成型で躓いたり拒絶反応を示したりする場合は、一度スピリチュアル型を参考にしてみてもよいかもしれません。
目標達成型で理想を実現するための2つの要素
ここでは、目標達成型で理想を実現するときの要素をお伝えしていきます。
要素①:理想の具体化
理想の具体化とは、目指したい地点を言語化することです。
自分が進みたい方向性を明らかにするために、今幸福だと思える地点を具体的にします。
よりよい理想を描くには、内省力や妄想力、浸透性の高さが重要です。
- 内省力:自分の感情や思考、行動を感じ取り考察する力
- 妄想力:自由に未来を発想する力
- 浸透性の高さ:外の世界を見て自分の世界を広げやすい状態
描く理想によって設定する目標や取り組むべき行動が変わり、人生が現状から大きく乖離する可能性が生まれます。
ただし、理想は経験や時間、時代や人間関係などにより変化するため、定期的にその方向に進みたいのかと点検することが必要です。
また、理想を言語化しようとすると漏れが発生しやすいです。
理想を追いながら、理想の位置を調整するようにしましょう。
- 点検:過去に描いた理想が現在も理想であり続けているのかを確かめること
(例.仕事で冒険したかったが、今は他者に変化を与え続けられる存在でありたいと感じている) - 調整:目指している理想に漏れがないか、偽りでないかを確かめること
(例.家族が安心できる場を築くことが理想だったが、留守番するだけの私はなんか違う)
準備中:情熱の見つけ方
要素②:理想への接近
理想への接近とは、描いた理想や設定した目標にどのように近づくかということです。
「ルートを選ぶ力」と「進む力」に分けられ、いずれかの能力が不足していると理想にたどり着きづらくなります。
- ルートを選ぶ:陸路か空路か、富士宮ルートか御殿場ルートか
→お金や強みなどの内部要因、需要や競合などの外部要因によって有効なルートが変わる。 - ルートを進む:どれほどのペースで、どの順に進んでいくのか
→ルートが分かっても自分がゴールまで歩めるとは限らない。躓く課題は人によって異なる。
正しいルートが分かれば成功するという考え方もありますが、適切なルートは人によって異なります。
Aさんの成功ステップを自分が実践したからといって、同じ期間で同じ成果物を得られるとは限りません。
適切なルートを選ぶためには、自分の資質に合った方法を探ることが有効です。
誰かに教わる場合は、その人が自分と似た資質の持ち主であるかを確かめることをおすすめします。
例.副業で3万円稼ぎたいときのルート選び
・適切なルート①:人の世話を焼くのが好きだからゲーム実況者になる
・不適切なルート①:書類作業が苦手なのにブログで稼ごうとする
・適切なルート②:3カ月以内に稼ぎたいから知人の事業のお手伝いをする
・不適切なルート②:3カ月以内に稼ぎたいのにプログラマーになろうとする
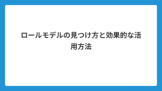
理想を具体化する方法
ここでは、理想を具体化するための3つの方法をお伝えしていきます。
具体化①:価値観
価値観とは、満たすことで心に充実感をもたらす要因のことです。
高揚感とは異なり、それを得ることで人生に意味を感じさせます。
- 高揚感:一時的な喜び、楽しさ、快楽、お得感
(例.ゲームに勝った、宝くじが当たった、環境が変わったなど) - 充実感:じんわりとした喜び、意味感
(例.家族と一緒に過ごせた、新しい挑戦を始められるなど)
価値観は人によって異なり、他者の欲求をコピーしたものではありません。
他者とは関係なく自分が大切だと感じることであり、「こんな人生でありたい」という理想の核心が価値観です。
「価値観が満たされる」とさえ感じるならば、未来の姿に固執しなくなります。
大きいか小さいかではなく、その未来の姿で自分がその価値観を満たせられていると解釈できるのかが重要になるためです。
例.価値観による未来の幅
・価値観:冒険
・価値観への定義:冒険とは、未知を探索することである
・理想①:トレジャーハンターである自分
・理想②:新しいゲームを攻略している自分
・理想③:他者とふれあい深く理解しようとしている自分
理想の土台を得るためにも、自分の価値観を見つけてみてください。
「これを大切にしたい人生なんだ」というものが見つかれば、視野が広がるとともに、大切でないものに振り回されなくなります。
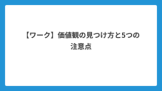
具体化②:ビジョン
ビジョンとは、幸福な未来を想像したときに得られる五感の情報です。
理想の中身であり、言語化が難しいニュアンス的な部分を理解できます。
例.理想とビジョンの違い
・理想:独自性を発揮した事業を展開していたい
・ビジョン:朝から作ろうとしている未来にワクワクし、コーヒーを飲みながら数人の従業員に囲まれて作業に没入できている、休日は…
理想と目標はよく混同されがちであり、数値目標さえ達成できれば理想は実現されると誤解されます。
しかし、理想とは状態を表すもので、結果を表すものではありません。
- 状態を表す:どういう働き方、暮らし方、生き方をしているか
- 結果を表す:何を達成したか、何を得たか、何を失ったか
理想を100%言語化することは難しく、それを補うためにビジョンが役に立ちます。
未来について考えるときは、数字を一旦脇に置き、どんな状態であるのかをありありとイメージしてみてください。
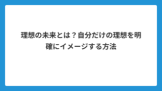
具体化③:人生の輪
人生の輪とは、人生を8つの要素に分解し、要素ごとに理想を検討する方法です。
私たちは理想を考えようとすると、特に重要だと考える要素だけに焦点を合わせます。
しかし、実際は1つの要素だけでは満たされないこともあり、人生全体のバランスを検討するためにこの方法が用いられます。
★人生の輪の構成要素
・仕事/キャリア:どのような活動を仕事にしていたいか
・お金・経済:どれほどお金が必要か、どれほど稼ぎたいか、貯蓄
・健康:どんな健康状態でいたいか、高負荷の運動ができるほどか
・家族/パートナー:どんな家族関係でいたいか、家族への振る舞い方
・人間関係:人間関係の広さと深さ、特定の他者との関わり方。他者への振る舞い方
・学び/自己啓発:何を学んでいたいか、どんな態度で学んでいたいか
・遊び/余暇:どんな休日を過ごしていたいか
・物理的環境:住まいなどの環境
人生の輪で大切なことは、各要素における方向性と必要量です。
重視したいことや必要だと考える量は人によって異なります。
見栄えを気にしたり、脳死的にたくさん求めようとしたりせずに、自分にとっての幸せの形をありのままに表現しようとしてみてください。
- 要素ごとの方向性:どんな幸せの形を目指したいのか
(例.切磋琢磨できる人間関係を築いていたい) - 要素ごとの必要量:どれほどの規模があれば満足なのか
(例.仕事はそれほど重視しないが、家族とは徹底的に関わりたい)
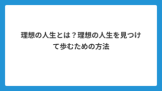
理想に接近する方法
ここでは、理想に接近するための方法をお伝えしていきます。
どれか1つでも欠けると、前進できずに足踏みすることになります。
どれに手を付けるべきか分からない場合は、紹介する順に取り組んでみてください。
接近①:目標設定
目標とは、理想を実現するための要件のことです。
現状から理想までの距離が離れているほど、目標の数は多くなる傾向があります。
- 現状と理想の距離が近い:欠けている要素が少ない
- 現状と理想の距離が遠い:欠けている要素が多い
目標設定にはコツがあり、内容によって前進速度が変わります。
まずはSMARTの法則を基本にして、達成確率が70%ほどの難易度の目標を設定してみてください。
★SMARTの法則
・Specific(具体性):イメージが湧くような具体的な目標
・Measurable(測定可能):測定ができる数値化された目標
・Achievable(達成可能):今の自分でも達成可能で現実的な目標
・Relevant(関連性):目的と関連性の強い目標
・Time-based(期限):いつまでにやらければならないのかという期日
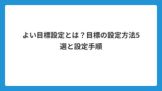
接近②:計画策定
計画とは、現状から目標を達成するまでのストーリーのことです。
中目標と小目標をつくり、どういう流れで目標達成されるのかというロジックを組みましょう。
- 大目標:理想を実現するための要件、今取り組んでいる行動の目的的な立ち位置
(例.月商50万円を稼ぐ) - 中目標:大目標を達成するための要件、大目標までの距離が分かる
(例.5万円の商品を作る、10人に売れる仕組みを作る) - 小目標:中目標を達成するための要件、中目標までの距離が分かる
(例.本を10冊読む、モニターを取る、SNSを始めるなど)
大目標・中目標・小目標の順で、具体的で流動的になります。
特に初めての取り組みであるほど、小目標を変える必要性が生じやすいです。
新しい情報を得るたびに、フィードバックして加筆修正するようにしてください。
- 初めての取り組み:予測と実際の情報の隔たりが大きい
- 手慣れた取り組み:予測と実際の情報の隔たりが小さい
ただし、臨機応変に行動を変えることと、計画を投げ出すことは別の行為です。
大目標と中目標への影響を踏まえて、なぜ計画や行動を変える必要があるのかを明確にしましょう。
- 計画を投げ出す:より大きな目標への影響を考慮せずに変えること
(例.難しそうだからやめる、もっとラクなものがありそうだからやめる) - 臨機応変に計画や行動を変える:より大きな目標への影響を把握しながら変えること
(例1.やってみたがこれでは締切に間に合わないから別の方法や工夫を探る)
(例2.まず本を読もうと思ったが、イメージがわかないため実践から始めてみよう)
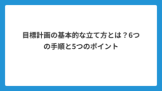
接近③:能力開発
能力開発とは、目標達成に必要な技術的スキルを身につけることです。
目標達成に有効な能力には、専門的な技術や目標達成能力などが挙げられます。
- 専門的な技術:専門的なノウハウを実行するための知識や技術
(例.短時間で記事を書ける、集客率の高いLPを作成できる) - 計画実行能力:立てた計画通りに実行するための知識や技術、マインド
(例.コツコツと継続する、失敗が怖くても挑戦する、元気がなくても行動する) - 目標管理能力:目標達成プロセスを回すための知識や技術
(例.適切な目標や計画を立てられる、目標や計画を点検できる。進捗速度を調整できる) - 環境調整能力:意志に頼らず行動や成長を促すための知識や技術
(例.朝から仕事ができる環境、他者からフィードバックを得られる環境)
開発したい能力とは、「現状ではできないけど、理想または目標達成時点ならできるはずのこと」です。
ただし、「できるにこしたことがない能力」と「できなければ目標達成が難しくなる能力」は区別しましょう。
また、必要な能力は実践により明確になることもあります。
まずは現状のまま挑戦してみて、そこから得られた情報をもとに、課題の優先順位や必要なレベル感の仮説を立てることをおすすめします。
準備中:上達するには
理想の実現を妨げるよくある思考6選
ここでは、理想の実現を妨げやすい思考についてお伝えしていきます。
障害①:他者比較
他者比較は、現状を客観視するために有効な手段です。
しかし、誤った比較は自信だけではなく、本心を見失う原因になります。
自分よりも幸せそうな他者を見ると、自分の理想に価値がないように感じ、他者の幸福を真似しようとしてしまいます。
- 適切な他者比較:Aさんより劣っているから〇〇を改善するための練習をしよう
- 不適切な他者比較:他の人のほうが幸せそう、何のために私はがんばっているんだろう
他者比較は理想を実現するのに役立つツールですが、取り扱い方や解釈には気を付けなければなりません。
理想の精緻化や計画や行動の修正のために、意識的に比較するようにしてください。
- 理想の精緻化:自分が求める未来をより詳細に言語化するための比較
- 計画や行動の修正:理想に近づくための仮説を改善するための比較

障害②:他責思考
すべてを自分の責任と捉える必要はありませんが、過度な他責思考は挑戦意欲と改善意欲を失わせます。
理想に向かうことや近づくことを阻害し、人生を停滞させてしまうでしょう。
- 挑戦意欲の低下:私には才能がないからどうせ失敗する。やるだけ無駄だ
→挑戦しない理由をすべて”才能”の責任にしている - 改善意欲の低下:私は悪くない。だから私は変わる必要がない
→結果責任をすべて”他者”や”環境”に押し付けている
責任の線引きはきっぱりと引けるものではありません。
そのため、「自責」と「他責」のどちらの視点も持つことが重要です。
例.失敗結果への責任
・自責①:自分が変えられる「結果に影響するもの」はどれだろうか?
・自責②:お金がないから成功できなかった。お金がない条件で成功するには?
・他責:その結果に自分の責任が一切ないとしたらこれから何に取り組むべきだろうか?
人生にテコ入れしようとすると、現状維持を正当化するために他責思考が生じます。
しかし、「今のままでいい」という甘い誘惑に抗わない限り、現状を変えて理想を実現することは困難です。
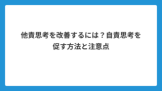
障害③:効率思考
時間やお金などの資源は有限であり、効率化を目指すことは何事においても大切です。
しかし、効率化の対象は「できること」または「できるであろうこと」であり、現実的でなければなりません。
- 現実的な効率化:より早く作業を完了できるようにする、正解までのプロセスを簡略させる
- 非現実的な効率化:一度で成功する方法を探す、一度で正解を引こうとする
特に「失敗=非効率」という信念を持つ人は、効率思考によって決断や行動が難しくなります。
行動して失敗することを恐れ、一度で成功させようといつまでも準備段階から抜け出せません。
例.効率思考による悩み
・これは本当にやりたいことなのか?
・これに取り組むことは時間の無駄ではないのか?
・お金がもったいない。独学で成功する方法はないのか?
・時間がもったいない。手早く成功する方法はないのか?
・失敗や挑戦のプロセスは無駄である。もっと簡単に成功できる方法はないのか?
効率的に考えることはやめてはなりませんが、最後には今使える手札の中から選ぶ必要があります。
手札にない選択肢ばかりに焦点を当てて、「持っている手札は非効率だしな」と歩みを止めないようにしてください。

障害④:低い自己愛
自分を蔑ろにすべきだと捉えていると、自分の欲求に素直になれなくなります。
欲しいものを欲しいと言えず、自分を幸せにすることへの抵抗感が強まるでしょう。
- 低すぎる自己愛:自己犠牲的な理想を描きやすい、自己が考慮されていない
(例.私はどうなってもいいから誰かの役に立ちたい) - 高すぎる自己愛:自己中心的な理想を描きやすい、他者が考慮されていない
(例.愛されたいから優しくする。お金が欲しいから詐欺で稼ぐ)
「他者を慮ること」と「自分を軽視すること」は別の考えです。
たとえ他者のための行動であったとしても、その核心は自分を幸せにするためでなければなりません。
他者を慮る:他人がよりよくなるための力になりたい
自分を軽視する:私は犠牲になるべき、幸せになってはならない、多くを求めてはならない
ただし、偽りの低い自己愛には注意が必要です。
自分を守るために自分を蔑ろにしようとすることもあるので、その行動や思考の理由は丁寧に掘り下げるようにしてください。
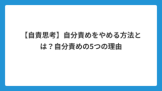
障害⑤:低い自己効力感
実現できる確信が小さいほど、そこにリソースを割くことへの粘り強さが弱まります。
努力に対して意味を見出せなくなり、理想を諦めたり、行動を続けることが目的になったりするのです。
- 理想を諦める:どうせ無理だと大会に勝つことを諦める
- 手段が目的になる:「甲子園に出場すること」ではなく「練習に参加すること」が目的になる
理想の実現には大きな変化が求められますが、実現するだろうという確信はほとんど持てません。
それが本当に理想なのか、この行動を続ければ理想が実現するかも未知数であり、無理かもしれないという諦めの気持ちが強まります。
しかし、自己効力感が高い理想はたいてい現在の延長線上であり、惰性や妥協によるものである可能性が高いです。
「できる自信はないけれどそれを実現したい」と思える自己効力感の低さは、自分にとっての現状の理想だと裏付ける根拠になり得るでしょう。
- 効力感が高い理想:できると思えるからやろうとしているのかもしれない
- 効力感が低い理想:「できる/できない」ではなく「実現したい/したくない」によるものかもしれない
描いた理想に対して実現できる自信を持てないのは、一般的な反応です。
とはいえ、自己効力感が低いままでは、粘り強さが弱くすぐに断念してしまいます。
自己効力感を高めるためにも、「これなら理想を実現できるかも」または「この目標ならとりあえず達成できるかも」という物語や指標を作ることが重要です。
- 物語:どうしたら理想が実現されるかという仮説
- 指標:理想に近づいていると実感するための目印
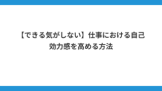
障害⑥:低い意味づけ力
私たちは同じ行動であっても、その意味づけは人それぞれ異なります。
もし「やるべきこと」と「やりたいこと」が一致するような意味づけができないと、やらされている感が強まってしまいます。
例.親の手伝い
・意味づけ力が低い:時間を浪費させられるだけ、なぜ親のためにやらなきゃならないのか
・意味づけ力が高い:家事力が身につく、親を喜ばせられる、好きな人に誇れる、楽しい
理想を実現したいとき、全ての行動が自分の好きなものであるとは限りません。
むしろ一般的には手間だと感じる行動が大部分を占め、その理想や目標を持っていなかったらやろうと思えなかったものでしょう。
また、理想は遠い存在ですぐに実現できないこともあり、「理想を実現するため」という動機だけでは燃え尽きやすい傾向にあります。
- 理想だけが動機:すぐに叶わないから力尽きやすい
- たくさんの意味がある:定期的に報酬を得られるため意欲が継続しやすく力尽きづらい
燃え尽きた居ないためにも、特に抵抗感が強い行動に対しては、それに取り組む理由を多角的に挙げておきましょう。
「だから私はこれをやる必要がある」と納得できる複数の意味づけができれば、失敗への恐れや飽き、確実性の低さに負けない粘り強さが生まれます。
例.SNSの運用
・低い意味づけ:稼ぐためには必要だから
・高い意味づけ:誰か1人の役に立つだろう、スキルが上がればいつでも声を広く届けられるようになるだろう

まとめ
理想を実現するためには、4つの戦略があります。
- 戦略①:現状維持型
- 戦略②:目標達成型
- 戦略③:興味関心型
- 戦略④:スピリチュアル型
一般的に正しい戦略を探すのではなく、自分に適した戦略を見つけることが大切です。
前に進めるのであれば、間違っているかもしれないと感じたとしてもその戦略を採用すべきでしょう。
また、効果が低い戦略にこだわり続けることにも注意してください。
目的はあくまで理想を実現することであり、手段に固執する必要がありません。
採用した戦略で試行錯誤してみて、それでも前に進めないならば他の戦略を採用してみることをおすすめします。
- OK:「目標達成型」を1年間試してみてがうまくいかなかったから「興味関心型」を試してみよう
- NG:「目標達成型」が正しいはずだ。もう何年も進めていないけど変えるべきではない