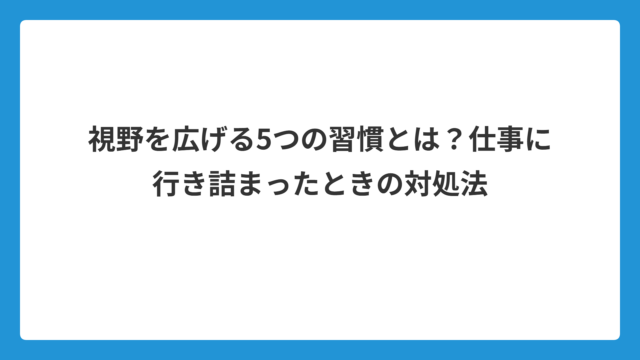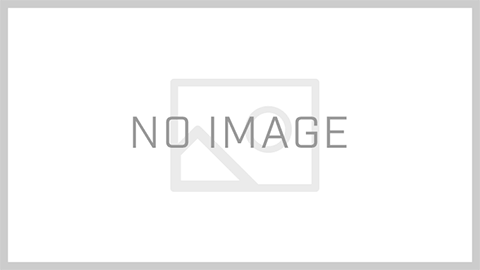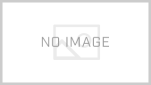何かに挑戦するとき、「やり方がわからない」と躓き立ち止まることがあります。
しかし、「やり方がわからない」は抽象的な感覚であり、方法を探すことだけが解決策ではありません。
自分の課題について深く理解し、その課題に有効な対処法を採用しないと、いつまで経っても前進することはできないでしょう。
この記事では、「やり方が分からない」を引き起こす要素と対処法についてお伝えしていきます。
前に進むための方法が分からなくなったら、どの要素によるものなのかを確かめてみてください。
やり方が分からないに陥る3つの要因
ここでは、「やり方が分からない」を引き起こす3つの要因についてお伝えしていきます。
前進できない理由を「やり方が分からない」で片づけず、もう少しだけ具体化してみましょう。
要因①:失敗への恐怖
失敗への恐怖とは、「仮説はあるけど試したくない」という感覚です。
絶対に成功する方法を求めて、今の自分はやり方が分からないのだと判断します。
例.失敗への恐怖
・痩せる方法が分からない→運動すればいいがそれでは間に合わないだろう
・プレゼンの方法が分からない→プレゼンはできるがこのままではウケないだろう
失敗への恐怖が生じる主な理由は、「理想が高いこと」と「失敗できない挑戦であること」です。
いずれにしても過度な思い込みであることが多く、客観的な思考をすることで次にやるべきことが明確になります。
- 理想が高い:3カ月ではなく1週間で-5kg痩せたい
- 失敗できない挑戦:プレゼンで高評価を得ないと私の人生は終わってしまう
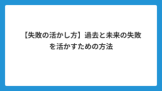
要因②:課題への理解不足
課題への理解不足とは、「何を調べるべきか分からない」という感覚です。
自分が何に躓いているかが不明であるため、次にやるべきことが分からないと判断します。
例.課題への理解不足
・痩せる方法が分からない→ちゃんと痩せるには何を試せばいいのだろう?
・プレゼンの方法が分からない→プレゼンを改善するにはどの本を読むべきだろう?
課題への理解不足が生じる主な理由は、「ざっくりな問い」と「過程のジャンプ」です。
いずれにしても「適切な問いを立てるための情報収集」がまずは重要になります。
- ざっくりな問い:抽象的で答えが無数にある問い
(例.モテるにはどうすべきか、幸せになるには何をすべきか) - 過程のジャンプ:現状のスキルを無視した願望、階段の二段飛ばし、二極化思考
(例.算数ができないのに数学のテストでよい点数を取ろうとする)

要因③:リサーチへの抵抗感
リサーチへの抵抗感とは、「調べること自体が億劫」という感覚です。
情報収集自体へのやる気が出ないことを、「やり方が分からないからだ」と結論付けてしまいます。
例.リサーチへの抵抗感
・痩せる方法が分からない→運動すればいいのは分かるが運動方法を調べる気にならない
・プレゼンの方法が分からない→調べるのがめんどくさいからこのままでいいや
リサーチへの抵抗感の主な理由は、「感情的抵抗感」と「身体的抵抗感」です。
いずれにしても、リサーチする余力を持てることが必要になるでしょう。
- 感情的抵抗感:めんどくさい、独自性が失われることへの危惧、尋ねることへの恐怖
- 身体的抵抗感:圧迫したスケジュール、疲弊した心身
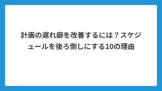
失敗への恐怖を解消する方法4選
ここでは、「やり方が分からない」を引き起こす要因の1つである「失敗への恐怖」の解消方法についてお伝えしていきます。
ただし、恐怖自体がゼロになることはないことに注意してください。
恐怖①:仮説を作り込む
「成功すること」ではなく「精度の高い仮説を作ること」を目的にすることで、次にすべきことが明確になります。
「この挑戦は成功するための1つの過程に過ぎない」と考えられるようになり、絶対に成功しなければならないという思い込みが外れるためです。
- 成功することが目的:確実に成功するには?失敗する仮説は仮説ではない
- 精度の高い仮説づくりが目的:成功しやすくなるには?今ある仮説を仮説として認識する
また、仮説を作りこむうちに愛着が湧き、より完成度の高い仮説に昇華させたいと感じるようになります。
そのための試行や情報収集として捉えるようになり、ますます行動力が向上します。
ただし愛着が強すぎると、改善が難しい非効果的な方法に固執する危険性があることに注意してください。
固執しないためには、あらかじめ複数の仮説を持っておくことが有効です。
1つの有効そうな仮説を作りこみ、無理そうなら別の仮説に切り替えられるようにしましょう。
例.仮説を作りこむ方法
・壁打ち:実行前にこの仮説をさらによくなる方法、リスクを抑える方法を検討すること
・小さく試す:実際に検証して現実的な課題を明確にすること
・パターン出し:この仮説で生じる結末パターンを検討すること
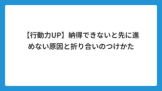
恐怖②:他者に保証される
今ある仮説を他者に保証してもらうことで、安心感から実行する意欲が高まります。
客観的な意見を取り入れることで視野が広がり、自分よがりの方法ではないと実感できるためです。
- 保証された仮説:「この方法なら成功確率が高い」と他者から安心感を与えられたもの
- 保証されていない仮説:成功確率は直感や文献によるもので現実味がないもの
ただし、他者からの保証は責任転嫁につながる恐れがあります。
「あなたが言ったから実行したのに失敗したじゃん!」と恨んだり、相手の助言をわざと失敗して陥れようとしたりするのです。
そのように相手に依存しないためにも、他者からの保証は根拠の1つに留めるようにしてください。
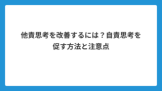
恐怖③:致命傷を見極める
「どんな成果を欲しいか」という成功基準だけでなく、「どんな失敗さえしなければいいのか」という失敗基準も検討しましょう。
「成功か失敗しかない」と捉えると、確実に成功できる方法以外を試す気にならなくなるためです。
成功確率が低い仮説はないのも当然と考え、「やり方が分からない」と立ち止まるようになります。
- 成功基準:「大成功」「成功」「普通」の境界線となる指標
(例.8割が喜べば大成功、3割が喜べば成功、1割が喜べば普通) - 失敗基準:「致命的な失敗」「失敗」「普通」の境界線となる指標
(例.チャンスをもらえなくなるのは致命的な失敗、がっかりされるのは失敗、反応がないのは普通)
今ある仮説を仮説として認識することは、「やり方がわからない」から抜け出す重要なステップです。
そのためにも、「今ある仮説はどの結果になりやすいのか」を客観的に評価してみてください。
たとえ致命的な失敗になりやすいとしても、「単なる失敗に昇華する方法」の模索には価値があります。
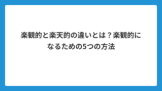
恐怖④:挑戦することの解釈を変える
挑戦から得られる恩恵は、成功することだけではありません。
経験や人脈、教訓や現状の把握など、挑戦からはさまざまな恩恵が得られます。
にもかかわらず、「成功しなければ無意味だ」と断じてしまうと、挑戦自体の動機が小さくなり勝てる試合にしか挑めなくなるでしょう。
- 成功だけが恩恵:失敗する確率があるなら挑戦しない、確実に成功できる方法が欲しい
- 成功以外にも恩恵がある:挑戦するだけで得られるものがある、成功確率が低くても試してみよう
勝ちを目指すことは大切ですが、勝利を確信できる戦いにしか挑まないことは成長を止める原因です。
挑戦することをポジティブに受け入れるためにも、「勝利の数」ではなく「勝利の質」にこだわってみてください。
絶対に勝たなくてはならない戦いを見極めることで、そこまでのレベルアップの手段として”負け”を許容できるようになります。
- 勝利の数:負けがどれほど少ないか、勝ちがどれほど多いか
- 勝利の質:自分が本当に勝つべき戦いはどれか、絶対に負けてはならない戦いはどれか
★締切を作ろう
成功を確信できるまで挑戦しないと考えていると、いつまで経っても「やり方がわからない」から抜け出せません。
確実に成功できる魔法の杖はそう簡単には見つからず、またその確信は主観でしかないためです。
「失敗してもいいから挑戦してみる」と締切を設けて、挑戦までに本気で仮説を練り上げてみてください。
たとえ本当に失敗しても、その経験からしか得られないものがあり、挑戦までの生産性も著しく高まるはずです。
・締切を設けない:挑戦できない、情報収集などの準備に熱が入らない
・締切を設ける:挑戦できる、挑戦から成果物を得られる、情報収集などの準備に熱が入る

課題への理解不足を解消する方法4選
ここでは、「やり方が分からない」を引き起こす要因の1つである「課題への理解不足」の解消方法についてお伝えしていきます。
課題①:実践してみる
課題が1つしかないということは存在せず、誰もが複数の課題を持っています。
しかし、課題には重要度や優先度があり、1歩前に進むためのボトルネックとなる課題を見つけなければなりません。
- 重要度:課題を解消したときの影響の大きさ
- 優先度:取り組む課題の適切な順序
実践から生じる迷いや葛藤、スキル不足などから、今取り組むべき課題が浮き彫りになります。
未熟であると分かっていても、どの課題に取り組むべきかを見定めるために実践してみてください。
- 迷い:何が正解か分からないこと
- 葛藤:「やりたい」と「やりたくない」の精神的な衝突
- スキル不足:やろうとしてもできないこと
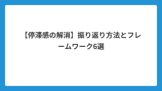
課題②:全体像を把握する
全体像を把握することで、取り組むべき課題が明確になります。
局所的な枝葉から幹にまで視野が広がり、現状と方法をより深く理解できるためです。
- 枝葉だけを見る:手段への固執
(例.学力を上げるには暗記が有効だ) - 幹も視野に入れる:目的からの俯瞰
(例.学力を上げる方法の1つは暗記だが、他にもあるはずだ)
どうすればいいか分からないときは、全体像を把握して、採用している方法がどんな局面で有効なのかを検討してみてください。
そして、他の方法もたくさん挙げて、現状を再評価し、より現状にマッチしたものを選んでみましょう。
ただし、私たちは身近にある手札で挑戦するしかありません。
「確実な方法」ではなく「アクセス可能な範囲内にある有効な方法」を見つけることを目的にすることをおすすめします。
- 確実な方法:これなら絶対に成功できるという確信を持てる方法
- アクセス可能な範囲内にある有効な方法:一定期間内に見つけられて実施もできる方法の中で最も現状に有効そうなもの
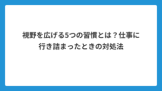
課題③:フィードバックをもらう
他者が見えている課題を教わることで、今取り組むべき課題候補が見つかります。
「自分の行動」「行動による結果」を客観的に把握するためには、外から情報を得るしかないためです。
フィードバックとは自分の行動に対する他者の反応であり、主に以下の3つに大別できます。
- 影響:自分の行動による相手の変化や反応
(例.悪口を言ったら相手が怒った) - 意見:自分の行動に対する相手の解釈が含まれた主観的な見え方
(例.あなたの今の発言は悪口だと思う。撮影された口論場面の動画) - 提案:自分の行動に対する助言、変更すべき箇所のアドバイス
(例.あなたは悪口を言わない方がいいと思う)
行き詰まったら「何のために」「誰から」「どんな情報を集めるのか」を決めてみてください。
ただし、すべてのフィードバックを真に受ける必要はないことに注意しましょう。
- 何のために:欲しい結果、行動目的
(例.夫婦関係を改善したい) - 誰から:フィードバックをくれる対象者
(例.パートナーの両親から) - どんな情報を:その人から得たい情報
(例.私たちの関係性や私の行動が客観的にどう見えるのかを知りたい)

課題④:仮説と結果パターンを明確にする
今ある仮説への理解を深めるには、試そうとしている仮説とその結果を明確にすることが重要になります。
私たちは自分が持っている仮説を把握しないまま、その結果の予測もせずに試し続けているためです。
例.SNS運用
・仮説:私の日常を1カ月間発信すればフォロワーが増えるだろう
・結果①:フォロワーが増える
・結果②:フォロワーが減る
・結果③:フォロワーの増減と関係なくクレームやストーカーが発生する
※「仮説」と「結果」の因果関係を探ることで仮説の質が上がります。
(例.フォロワーが増えるとしたら、私に共感した人がフォローをするからだろう)
「やり方が分からない」と立ち止まったら、今ある最低限の仮説を土台として明確にしてみてください。
その仮説をどの方向に改善していきたいかと検討することで、進むべき方向性が分かり次のアクションが浮き彫りになります。
例.主な改善ポイント
・成功の天井を突き破る:よりよい成功とは何か、この仮説でそれは得られそうなのか
・成功確率を上げる:成功確率を高めるにはどうすべきか、何が要因か
・失敗パターンを評価する:どんな失敗があるのか、それらはどれほどの確率で生じるのか
・失敗確率を下げる:失敗確率を小さくするにはどうすべきか、何が要因か

リサーチへの抵抗感を解消する方法3選
ここでは、「やり方が分からない」を引き起こす要因の1つである「リサーチへの抵抗感」の解消方法についてお伝えしていきます。
ただし、抵抗感自体がゼロになることはないことに注意してください。
抵抗①:目標を再設定する
リサーチへの抵抗感が生じる理由の1つは、目先の労働に焦点が当たることです。
目先の損得勘定になり、リサーチしないことのほうがお得だと感じてしまいます。
- リサーチすることは損:リサーチすると新たな行動をしなければならない
- リサーチしないことは得:リサーチしなければ労働量が減るだろう
目先の労働への苦労を過剰評価しないためには、目的や目標に焦点を当てることが有効です。
「それをしないとその目標が手に入らない」と考えることで、リサーチしないことは損であると認識できるようになります。
例.おしゃれしたいけどしたくない
・目標なし:わざわざ調べるのもめんどくさいから今のままでいいや
・目標あり:あの人に好きになってもらうためにも早くおしゃれできるようになろう!
「やり方が分からない」で立ち止まったとき、その状態で行動を促すほどの目標が設定できているのかを確認してみてください。
調べるのもめんどくさいと感じるならば、目標を再設定するか、手放すことをおすすめします。
- 目標の再設定:「欲しい」「得られないのはつらい」とより感じるワクワクする目標にする
- 目標を手放す:一旦その目標を諦める
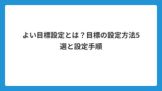
抵抗②:大量行動を肯定する
私たちはつい効率的な方法を採用したがります。
「この情報を調べれば確実に大きく前進するだろう」と感じないと、なかなか重い腰が上がりません。
もし確実性に納得できなかったら、たいていは行動しないことを選択してしまうでしょう。
- 納得できる確実性:この行動をすることには意味があると実感すること、期待値が高い行動
(例.成功者に教わった方法だからこれを実行すれば私も稼げるようになるはずだ!) - 納得できない確実性:この行動をしても無意味であると実感すること、期待値が低い行動
(例.誰にも保証されていない方法だしどうせ失敗する。ならやらないほうがいいだろう…)
成功できる方法を探し求めているあいだは、「自分の才能」や「集めるべき情報の種類」ばかりに注目して行動が止まります。
大量行動しているように見えたとしてもそれは悩んでいるのであり、その場で足踏みをしているだけです。
- 自分の才能:私には成功できる資質があるのだろうか、うまくできるのだろうか
- 情報の種類:どの本を読むべきか、どの人の意見を聞くべきか
この状況を打破して前進するためには、非効率的な行動を肯定することが重要になります。
失敗するとしても実行することを優先して、「やるorやらない」ではなく「どれから試すのか」に思考を変えるのです。
「工程」ではなく「サイクル」をたくさん回せるようになれば、「分からないから立ち止まる」から卒業できます。
- やるorやらない:成功しそうなら実行する、失敗しそうなら実行しない
- どれから試すのか:もっとも成功確率や気づきが大きいものを選び失敗するとしても実行する
- 工程をまわす:たくさん調べる→この方法は無理と判断する→調べなおす
- サイクルをまわす:PDCAやOODAを何度も実施する
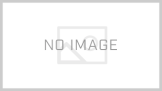
抵抗③:独自性の線引きをする
調べたり教わったりすることにより、独自性の薄れを感じることがあります。
これは模倣することへの抵抗感であり、自分だからできることを見つけたいという欲求です。
教わってしまうと自分の成功ではなくなると考え、「可能な限り調べない」という我流のような進み方を選びます。
例.教わることへの抵抗感
・他者が怖い:評価されることへの恐怖、他者の振る舞いに対する恐怖
・過ちへの恐怖:自分の考えが間違っていたと知りたくない
・自分で攻略したい:強い冒険欲
・自分で攻略方法を編み出したい:オリジナリティへのこだわり
しかし、他者と同じことを一切せずに、自分の独自性だけで成功することはほぼ不可能です。
教わるよりも時間も多く費やすため、趣味ならまだしも仕事ではそのこだわりは裏目に出てしまうでしょう。
また、「真似された」と感じやすくなり、他者に対して無駄にエネルギーを費やすことにもつながります。
例.独自性へのこだわりによるデメリット
・葛藤:一部でも他者の模倣が含まれている方法を採用することへのストレス
・開発時間の増加:調べればわかることをゼロから開発しようとするため
・方法への強い愛着と権利意識:その方法を開発/採用したのは誰が先かにこだわるようになる
独自性に振り回されなくするためには、自分がこだわるべきポイントを言語化することが有効です。
模倣が許される部分とそうでない部分の線引きをすることで、独自性を重視しつつ方法を模索できるようになります。
線引きでは「妥協」するのではなく、「とことんこだわりたい部分はどこか」と自問自答してみてください。
限られた資源を集中させたいポイントが明確になれば、前進することへの意欲が増して立ち止まってはいられなくなります。

抵抗④:リサーチ手段を増やす
リサーチへの抵抗感を減らすためには、「克服すること」だけではなく「現状でできることを探す」のも有効です。
例えばリサーチには以下の種類があり、人によって得手不得手が異なります。
身近なリサーチ方法が不得手であるならば、「これならできそう!」と感じるものを探してみてください。
- 書籍
- 論文
- SNS
- AIに尋ねる
- 人に尋ねる
- 現地で取材する
- インターネット
行動のしやすさは、「得意」と「効率」によって変動します。
自分の行動を止めている要因を明らかにして、試してみたくなるリサーチ手段を模索してみましょう。
- 得意:その行動ができる、抵抗感が少ない、報酬感が多い、成功体験がある
- 効率:有益な情報が得られるだろう、他の方法よりも有効だろう

状況ごとのやり方が分からないときのおすすめ対処法
ここでは、やり方が分からないときの状況ごとの対処法についてお伝えしていきます。
あくまでこうしたほうが効果的な場面が多いというものであり、誰にとっての正解ということはないことに注意してください。
状況①:初心者:仕組みを理解し行動に慣れよう
何かに取り組み始めてから半年未満の新規参入者は、圧倒的に情報が不足しています。
偏った情報収集になっていることが多いため、先輩や成功者から指導してもらうとよいでしょう。
独学である場合は、その領域の全体像を知るためにも書籍を10冊ほど適当に選んで読んでみてください。
例.起業してお金を稼ぎたい!
・局所的な情報収集:SNSでどんな発信をすればいいのだろうか?(how)
・網羅的な情報収集:お金を稼ぐには何が必要で今は何をすべきか(what+how)
また、初心者は分かっている気になっていることも多く、そのせいで立ち止まっている場合があります。
分かっていることと分かっていないことの線引きをするためにも、定期的に実戦の場を設けて課題を抽出することをおすすめします。
状況②:半人前:場面ごとに適応しよう
ある程度自分のパターンが定まってきたら、そのパターンである必要性に疑問を抱きましょう。
有効・非有効な場面を理解して、今のパターンを磨くか、他のパターンを臨機応変に使えるようになるかを選んでください。
- パターンを磨く:パターンの改善、リスクの軽減ための工夫、効率化
- パターンの取り入れ:他の方法を選べるようになる、適切に使い分けられるようになる
今のパターンに疑問を抱くためには、どういう状況を苦手としているのかを知るための情報が必要になります。
具体的には、他者からフィードバックをもらったり、過去の結果と内容を振り返ったりすることがおすすめです。
状況③:1人前:目的地を再設定しよう
ある程度安定して成功を収められるようになったら、目的地を再設定してみましょう。
目指す地点が変わることで必要な「思考/スキル/あり方」が変わり、新たな課題が明らかになるためです。
- 思考:考え方、捉え方
- スキル:技術、方法、やり方
- あり方:振る舞い、コンセプト、ルール
ここで重要なのは、目標ではなく目的地となるゴールから考えることです。
「何を得たいか」ではなく「どんな未来を実現したいのか」と自分に問うことで、進む方向性がガラッと変わります。
- 目標:月収を+20万円にする
- 目的地:皆が戻ってきたいと思える元気になれる居場所を作ること
自分にとっての真の成功とは何かを検討してみてください。
目標の奥にあるゴールを描くことで、「何のやり方を理解する必要があるのか」が明確になり、次の1歩を決められるようになります。
まとめ
「やり方が分からない」という言葉は抽象的であり、ここから前進するにはその真意を見定めることが必要です。
その真意は主に3つの要因に大別され、その要因ごとに対処法が異なります。
- 要因①:失敗への恐怖
→仮説を作り込む、他者からの保証、致命傷の見極め、挑戦することの解釈を変える - 要因②:課題への理解不足
→実践する、全体像の把握、他者からのフィードバック、仮説と結果パターンの明確化 - 要因③:リサーチへの抵抗感
→目標の再設定、大量行動の肯定、独自性の線引き、リサーチ手段を増やす
自分がどの行動に抵抗感を感じ、そのときどんな思考や葛藤が生じているのかを言語化してみてください。
「誰かに教われば解決する」という単純な問題でないことが多いため、動けなくなったら丁寧に自分と向き合ってみることをおすすめします。
自分を深く掘り下げることが難しく大量の時間を要してしまいそうであれば、コーチングのような内省の専門家に支援してもらいましょう。