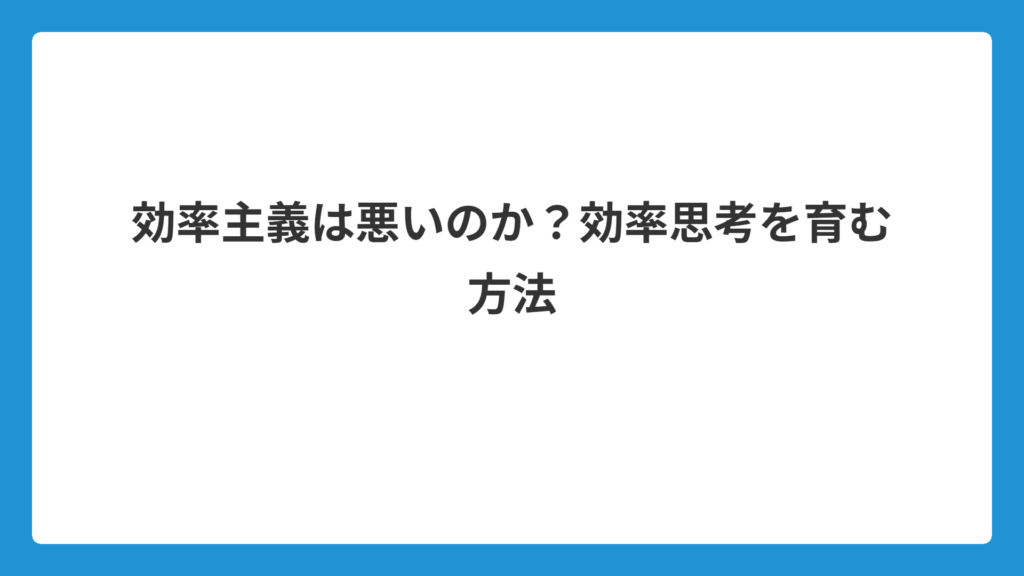効率主義とは限られた資源で、できるだけ多くの成果を上げようとする考え方のことです。
効率化そのものはビジネスにおいて大切な考え方ですが、使い方を誤ると不利益の方が大きくなります。
欲しい結果を得るためには、効率主義を育みコントロールできるようにならなければなりません。
この記事では、効率主義を育む方法についてお伝えしていきます。
効率主義における3つのレベル
効率主義は、次の3つのレベルに分けられます。
- なんでも効率化:非効率を効率にしたいという衝動に振り回される
- 自分の利益の最大化:最良な結果のために必要な効率化を目指す
- 全体の利益の最大化:自分と他者の長期的な利益の和が最大になるような効率化を目指す
非効率に対する苛立ちの核心的な目的や欲求を見つけることで、自分の効率主義レベルが判別できます。
効率化への欲求によって前に進めないときは、まずは内省して自分の本当の欲求と向き合ってみてください。
- 核心的な目的:私はなぜこの非効率に不快な感情を抱いているのか
- 核心的な欲求:私はこれを効率化してどうなることを期待しているのか
★エッセンシャル思考
効率主義に類似する思考法に、グレッグ・マキューン提案の”エッセンシャル思考”が挙げられます。
エッセンシャル思考とは、大事なことを見極め、自分の時間やエネルギーを最も効果的に配置し、最高パフォーマンスを目指すことです。
「大事なことを見極める」が条件であり、効率主義はエッセンシャル思考を包括する概念だといえます。
出典:https://www.flierinc.com/summary/417
効率主義とサイコパスの違い
効率主義傾向が強いと、よくサイコパスと間違えられます。
サイコパスは自分が求める結果のために、一般的には嫌悪する方法も容易に選択するからです。
効率化への欲求が強い人も同様の傾向があり、「過度な効率主義=サイコパス」として認識されます。
例.1ヶ月以内に100万円を稼ぐことが目標
・一般的な手段:地道な営業、ギャンブル
・過度な効率主義者:エロ系のアフィリエイト
・サイコパス:炎上商法、詐欺
サイコパスの特徴は、共感性の乏しさです。
他者の痛みを理解することはできても、それを自分も同じように感じないため、倫理観が外れた行動を取りやすい傾向があります。
目的志向であることは同じですが、共感できないことによる自分本位な選択方法がサイコパスと過度な効率主義者の違いです。
出典:https://www.dr-mizutani.jp/dr_blog/psychopath/
★省エネ主義
効率主義が包括する他の概念として、省エネ主義があります。
省エネ主義は「自分のリソースを損なわないこと」を第一に考える傾向のことで、事なかれ主義者が多いです。
効率的でないことを嫌がる傾向は同じですが、「自分が損するか」が優先的な判断基準になります。
効率主義のメリット5選
ここでは、効率化することのメリットについてお伝えしていきます。
メリット①:ミスの減少
ミスが減少する理由は、次の2つです。
- 工程が減る:無駄が省かれる
- 工程がパターン化される:最適パターンが明確になる
効率化すると複雑な工程がシンプルになり、いちいち迷わずに実行できるようになります。
ヒューマンエラーが起きづらくなるとともに、誤った手順にすぐ気づけて対処が容易になるでしょう。
★ミスの減少に貢献する2つの要素
・ミスの頻度減少:シンプルなプロセス、評価しやすい、誰がやっても同じ
・ミスの被害最小化:ミスに気づきやすい、陥りがちなミスと対処法が明確
メリット②:練度の向上
効率化すると練度が向上しやすくなる理由は、次の2つです。
- 決められた手順を繰り返すから
- 押さえどころが明確になるから
「何をするとどうなるのか」を明らかにすることで、効率的なプロセスを構築できます。
理論を理解して実践で深められるため、コスパ良く成長を促せるでしょう。
★押さえどころと成長
「守破離」という言葉があるように、最初は型通りの行動が成長を強く後押しします。
しかし、特にビジネスの世界では「型」は枠組みです。
その枠組み内での「自分なりの思考や行動」によって問題解決を目指さなければなりません。
マニュアルのように「AのときはBをする」と厳格に答えが用意されていないので、「型を使いこなす」という意識を持った方が成長が促されやすいです。
・マニュアル通り:型が具体的、自分の判断がほぼ必要ない
・型を使いこなす:型が抽象的、自分の判断による試行錯誤が必要
メリット③:生産性の向上
効率化の最大のメリットは、生産性の向上です。
少ないリソースで最大の成果を得られるため、次のような恩恵を授かれます。
- 時間が増える:新しいビジネス領域に展開できる、家族との時間を使える
- 成果が増大する:売上向上、インプット量の増大
時間だけは皆平等であり、人生とは「1日24時間という時間でどんな成果を上げるか」というゲームとも捉えられます。
時間が足りないと感じているときは、まずは理想的なスケジュールを作って求めている成果を炙り出してみてください。
★時間の捉え方
・8-8-8の法則:睡眠8時間+労働8時間+余暇8時間
・1日→24時間
・1年→8760時間
・1日の1%→15分
・1日の固定的な時間→睡眠8h+食事2h=10h
・1日の労働拘束時間→労働8h+通勤1.5h=9.5h
・1日の労働日の自由時間→24h-10h-9.5h=4.5h
・1年の休日(土日祝日)→土日104日+祝日16日=120日(1/3年)
・1年の労働日→365日-土日祝120日=245日(2/3年)
・1年の労働時間→245日+8h=1960h
・1年の自由時間→120×(24h-10h)+245×4.5h=1680+1100=2780h
・1ヶ月の平均労働日→245÷12=20日
・1ヶ月の平均労働時間→20×8=160h
・1ヶ月の平均自由時間→10×(24h-10h)+20×4.5h=140+90=230h
メリット④:集中力の向上
集中力が妨げられる最大の要因は、失敗への恐れから生じる迷いや不安です。
しかし多くの場合、失敗することの何を恐れているかは不明瞭であり、漠然とした不安だけが生じます。
- 明確な恐れ:「失敗→破産→従業員に迷惑をかける」という結果になることが怖い
- 不明確な恐れ:破産が怖い、低評価されるのが怖い、惨めな自分をさらるのが怖い
効率化すると、自分にとって大切な判断基準や優先順位が明確になります。
「何を恐れるべきか」が具体的になるため、その他のネガティブ要因は些細な問題になり、恐怖耐性が向上して集中力が高まるでしょう。
例.SNSでの情報発信
・非効率的:みんなに好かれる投稿をしよう
・効率的:ターゲットに好かれる投稿をすればいいや
メリット⑤:改善意欲の促進
効率主義傾向の強い人は、効率化すること自体がモチベーション源となります。
非効率であることに不満を抱き、効率的であることを魅力的に感じるためです。
★効率主義傾向が強い2つの資質
・最上志向:高みを目指すことに意欲が湧く
・回復志向:劣っている部分を改善することに意欲が湧く
効率化するためなら、試行錯誤への労力を惜しみません。
効率主義傾向が弱い人からしたら「よくやるよな」と感じることを、前向きに実行していきます。
★改善意欲と意味づけ
効率主義傾向が強い人は、「効率化」と結びつく意味づけをするとモチベーションが高まりやすいです。
どうすれば「ラク・早く・低コスト」になるかを考えて、その仮説を検証するための機会として捉えてみてください。
効率主義の問題点5選
ここでは、効率主義傾向の強い人が陥りがちな問題点についてお伝えしていきます。
問題点①:本当の目的を見失う
効率化を試みるとき、焦点が目先の問題に当たります。
「ラク・早く・低コスト」を善として、短絡的な視点で問題を解決してしまうのです。
例.会社の忘年会
・効率化の目的:労力やお金の軽減
・効率化の施策:忘年会をやめて経費を削減する
・本当の目的:上司と部下の顔をつなげたい
・本当の目的の施策:忘年会をやめて社内でメンター制度を導入する
効率化をするときは、効率的にしたい問題の目的を明確にしてみてください。
何を善とするかの判断基準が、全体にとっての利益になるものなのかを検討することをおすすめします。
問題点②:最初から効率を求める
効率主義傾向が強い人は、効率的でないことに強い不満感を抱きます。
「私が効率化させるんだ」と意欲を持てるならよいですが、それが手間である場合は非効率を理由に行動を止めてしまう可能性が高いです。
例.教わる態度
・効率主義:もっと情報をまとめてから教えてよ、正解だけを教えてよ
・効率化意欲あり:自分でマニュアルを作ろう、これを効率化することは穴場かも
・効率化意欲なし:めんどくさいからもうやめよう、教える人と相性悪いからやめよう
非効率な行動の実施に嫌悪感が生じる場合、それが全体的にみても非効率であるのかを確かめてみてください。
非効率だとする判断基準を疑うことで、求めているのが魔法の杖なのか否かを判別できるようになります。
★効率性に対する判断基準
特に未熟なうちは、「私は最適解か否かを判断できる」という謎の自信を持ちます。
これはダニング=クルーガー効果といわれる、「スキル練度が低いうちは自分の能力を過大評価する傾向がある」という認知バイアスによるものです。
しかし、それが本当に効率的なのか非効率的なのかはそうそう分かるものではありません。
「非効率だと感じること」はメモに残しておき、まずは一般的な方法で実施してみることをおすすめします。
問題点③:強迫観念による効率主義
効率を求める理由は、人によってそれぞれです。
気質ということもあれば、損失や他者評価への恐れなども考えられます。
- 気質:生まれ持った性質
- 恐れ:被害を回避しようとする動機
強迫観念によって効率化を望む場合は、高い確率で気質ではなく恐れによるものです。
非効率な行動は自分に損失を与えるため、「非効率だから行動しない」「重要度にかかわらず効率性を求める」という態度を持つ傾向があります。
★強迫観念による効率主義の恐れ例
・非効率だと自分の時間が無駄になる
・非効率な姿を見せたら周りにバカにされる
・非効率的な方法を選ぶ行為はクセづくものである
・非効率は愚か者が選ぶ選択であり、それを選ぶと自分は愚か者になる
「効率的の方が嬉しい」と「効率的でなければダメ」のいずれなのかを見極めてみてください。
自分を縛る強迫観念と折り合いをつけられれば、ストレスが軽減してより自由に物事を選べるようになるでしょう。
- 効率的の方が嬉しい:強迫観念である可能性低、効率化することに前向き
- 効率的でなければダメ:強迫観念である可能性大、効率化したいのではなく効率的でありたい
問題点④:他者にも最高効率を求める
効率主義傾向は、他者にも期待することがあります。
非効率的であることを悪として、行動や結果を逐一「効率的or非効率的」で評価しようとするのです。
★効率性の基準
他者の効率性を評価するとき、「自分」を基準にしがちです。
自分と同等以上なら合格、自分より非効率的なら不合格として認識し、その効率性には相手の能力や状況を考慮しない傾向があります。
他者への効率性を求める傾向は、特に協働や外注、育成への障害になります。
非効率であることに苛立ちを覚え、相手の成長を我慢できずに自分1人で仕事を回そうとしてしまうでしょう。
- 協働や外注→自分でやったほうが早いし品質が高い、任せられない
- 育成→育てる時間が無駄、育てられない
しかし、1人だけではすぐに生産性の限界に達して、できることの範囲が限られてしまいます。
将来のビジョンを描き、今一度自分1人でそれが実現可能なのか否かを検討してみてください。
★器の大きさ
他者に対して効率性を求めると、周りからは器の小さい人間だと認識されます。
成長するためには失敗が必要なのに、それを許容しない態度が見てとれるためです。
他者に対して苛立ちを抱く場合は、どんな自分でありたいのかという理想の自分像を描いてみてください。
その自分像になるためのスキル磨きに集中することで、効率性に振り回されることなく他者と向き合えるようになります。
問題点⑤:プロセスを楽しめなくなる
効率性を求めると、焦点が絞られて処理する情報が最小化されます。
論理的な思考ばかりを用いるようになり、興味関心が忘れ去られて感情が動きづらくなるでしょう。
- 論理的な思考:どうやったら効率的になるかだけを考える、冷淡、結果主義
- 興味関心のある思考:ワクワク感が生じるアイデアの発見と検証、高揚、プロセス主義
効率化に意欲的になれても、唐突に我に返って無意味感が生じることがあります。
無意味感を抱いたら、プロセスを実行すること自体から報酬を得るためにも、自分の価値観や興味関心と向き合ってみてください。
★読書と効率主義
効率的な読書では、没入せずに問いへの答えを探します。
感情は動きづらく、不必要な情報に興味も移らず、辞書を引くように求める答えだけを探すでしょう。
答えを探す速度は速いですが、限られた脳機能しか使われずに記憶に残りづらい傾向があります。
読書をするときは、知見を広めるためか答えを知るためかを分けて考える必要がありそうです。
・知見を広めるため:興味関心のアンテナを立てて情報を読み込む
・答えを知るため:問いを立ててからその答えを探す、答え以外の情報はスルー
効率主義を育む方法5選
効率主義を育むには、「目的」と「対象」を最適化することが大切です。
ここでは、目的と対象を最適化するための方法についてお伝えしていきます。
- 目的:なぜ効率化する必要があるのか
- 対象:何を効率化すべきか
育成①:理想を描く
効率化への衝動に駆られたら、効率的になることで生じる理想の未来について検討してみてください。
効率化を目的ではなく手段として、「何の目的のために効率化という手段を用いたいのか」を検討するのです。
- 効率化が目的:なんとなく効率化したい、非効率が気に食わない
- 効率化は手段:ラクしたいから効率化したい、叱られたくないから効率化したい
納得できる理想を描けたら、理想と現状のギャップを明確にして、そのギャップを埋めるための重要な要素を分析しましょう。
「Aを得るためにBを効率化すべきである」という仮説を構築してから実行することで、効率化への衝動に振り回されなくなります。
★仮説を構築するための質問
1.本当に欲しいものは何か
2.それは優先順位が高いのか
3.それを得るために必要な効率化とは何か
4.効率化して欲しいものは手に入ったか
5.手に入らなかったら次は何を試すか
育成②:焦り対策をする
結果に焦ると、過度な効率化を求めるようになります。
成功までのロードマップを無視して、無謀な挑戦を選ぶことを促してしまうでしょう。
例.起業して年商1千万円が目標
・1ヵ月後までに稼がなきゃ→焦って危うい手段を選ぶ動機にある
・預金が尽きるまでまだ1年ある→焦らずに慎重に前進できる
一見すると焦りは行動を促すように感じますが、過度な焦りは完璧主義を助長して行動量を低下させます。
「効率的でなければ間に合わない」と考えさせて、情報収集や計画立てばかりになって実行が疎かになるのです。
- まったく焦らない:行動量が減りやすい、興味関心のアンテナが立ちやすい
- ほどよい焦り:ほどよくプレッシャーがあり行動量が増えやすい
- 焦りすぎる:空回りした行動が増えるor一切実行できなくなる
焦りを対策するためには、「締切設定」や「直近の目標に集中する」が有効です。
「最高効率でなくてもなんとかなる」という余裕を作り、現実的な効率化だけに焦点を合わせてみてください。
- 締切を作る:いつまでに達成すればいいのか
- 直近の目標に集中する:「1歩前の自分」と「1歩先の自分」を把握しておく
育成③:効率性を検証する
「何をすると効率的になるか」という問いへの答えは、人によって異なります。
方法によってメリットデメリットが異なり、何を重視するかは人それぞれだからです。
例.専門性を深める
・Aさん→ざっくりと10冊の本を読んで全体像をつかんだほうが効率的
・Bさん→習得したい書籍を一字一句漏らさず、文脈も読み込んだほうが効率的
ここでの問題点は、自分の考える効率化する手段が検証されていないことです。
使い慣れている手段であればあるほど、非効率であることを受け入れられません。
例.1日を効率的に使うには
・非効率的な思い込み:睡眠時間が短いほど仕事や遊びの時間が増えるから効率的だ
・確証バイアス:やっぱり睡眠時間が長いと遊ぶ時間が確保できなくなって人生がつまらなくなる
効率性を検証するには、短期的と長期的なメリットデメリットを書き出すことをおすすめします。
また、実際にその方法を使った人の成果や末路を確認することも有効です。
確証バイアスに振り回されないためにも、検証前に目的を固定することが大切です。
育成④:今ある手札を明確にする
実行できる選択肢を明確にすることで、魔法の杖を探さなくなります。
効率的な方法の模索に見切りをつけて、今ある選択肢に集中できるようになるためです。
例.魔法の杖(効率的な方法)
・3日で運動せずに痩せる方法
・1日1時間でスキルゼロでも年商1千万円稼ぐ方法
「今ある手札で勝負するんだ」と覚悟を決めるためにも、手札を明確にする工程に時間を費やしましょう。
1週間程度全力で情報を集め、その中からもっとも効率的な方法を選択することで、「もっと効率的な方法があるかも」という迷いを取り払えます。
効率化をするときは「どれほどの効率化が可能なのか」を見極めて、地に足の着いた選択をすることをおすすめします。
★小さく試す
新しい施策は小さく試すことをおすすめします。
失敗しても損失が少なく後戻りできる規模感で試すことで、効率的な方法に拘らなくなります。
強い決断が必要な選択だと感じたら、もう少し小さく試せる方法はないのかを模索してみてください。
・強い決断が必要→会社を辞めて起業する
・強い決断が不必要→副業しながら起業する
育成⑤:効率欲求の隠れた恐れを見つける
効率化への欲求を活用するには、衝動に振り回されない必要があります。
「効率化しなければならない」という衝動に駆られたら、その衝動を生む理由を掘り下げてみてください。
★よくある効率化への衝動
・もったいない
・リソースの無駄
・方法にセンスがない
・周りに置いていかれている感覚、停滞感
効率的でありたい理由を明確にすることで、それを本当に効率化すべきなのかを検討できます。
「非効率だったらどんな嫌なことが起きるのか」について、深く内省してみましょう。
非効率であることを恐れる核心にたどり着いたら、その恐れが現実的であり、重要なものなのかを検証していきます。
★恐れを見つける問い
・最悪の未来とは何か
・最高の未来とは何か
・効率的である必要性とは何か
・どういう状況のとき、効率性を強く求めるのか
・非効率であるとき、どんな変化によって自分が非効率であると気づくのか
・効率的であるとき、どんな変化によって自分が効率的であると気づくのか
内省による気づきをいかに日常に反映させるかが重要です。
深い内省と行動による検証作業が1人では難しい場合は、コーチングやカウンセリングを受けてみることをおすすめします。
効率主義の個人事業が陥る問題ケース
ここでは、効率主義傾向が強い個人事業主が陥るよくある問題ケースについてお伝えしていきます。
ケース①:種まきを嫌がる
新たなビジネスに挑戦するとき、効率主義傾向が強いと最短ルートだけを求めてしまいます。
「すぐに結果がでなければ無駄である」と捉え、芽が出るか分からない種まきを敬遠するようになるのです。
★ビジネスにおける種まき(大きな成果の布石になるもの)
・目標設定
・人脈づくり
・小さな実績作り
・汎用的なスキル習得
・専門性と関連の薄い情報収集
すぐに成果が得られるタスクに従事することは大切ですが、視野狭窄になりやすく行き詰る可能性が高いです。
特に実際にサービスが売れていない段階は時間が有り余っているはずであるため、植えられる種はすべて植えてみてください。
★割合で考える
100%種まきも、100%目先のタスクもあまりおすすめしません。
まずは労働時間の20%を種まきに、80%を目先のタスクに振り分けてみましょう。
・100%種まき→収益に結びつかない、貯蓄が減る
・100%目先のタスク→自転車操業、仕事への無意味感
ただし、しだいに種をまくための時間が足りないと感じるようになります。
そうなったら、今までの経験をもとに、芽が出やすい種を選ぶことを始めましょう。
- 種を選ぶ:確実性を見極める
- 種を植える:実行する、経験を積む
ケース②:自分に合わない商材の購入
効率主義者のよくある失敗は、自分に合わない高額商材の購入です。
「自分で1から考えるよりも、すでにあるロードマップを指導されながら実行したほうが早い」と考えて、内容を精査せずに商品を買ってしまいます。
効率化という面では、考えるよりも教わる方が確かに効果的です。
しかし、「現状に行き詰っている原因」が、かならずしも「方法が分からないから」ではないことに注意しなければなりません。
効率主義者は「非効率な方法を試したくないから私は成功できないのだ」とよく結論付けますが、なぜ非効率な方法を試せないのかこそがその人にとって真の課題です。
★商材を買う動機
・時間の短縮:情報収集、計画立て、ロードマップ
・恐怖の解消:失敗が怖い、恥をかきたくない、無駄なことをしたくない
特に高額な商材を買うときは、本当にその商材で自分は実行できるのかを内省してみてください。
可能であればまずは無料や低額な商材を購入して、それを実行してみることをおすすめします。
★保証による課題の解決
他者から保証してもらうことで、真の課題を無視して前に進むことも可能です。
実践することで「大丈夫だった」という確信を得られれば、課題を解決することにもつながります。
ただし、1度成功しても再び実行が止まる場合は、他者の方法論を真似しても課題は解決できません。
その場合は、他の方法で課題の解消を試みる必要があります。
ケース③:行動するまでに時間を要する
効率主義者は、成功を確信できる道筋が見えるまで、行動が止まりやすい傾向があります。
実行するまでの閾値が高く、「やりたい→やってみる」まで多くの情報を必要とするためです。
しかし、ビジネスにおいては100%の成功法則は存在せず、そのため一切行動できずに何年も経過する人がよくいます。
「一度決めたらそれを続けなければならない」と踏ん切りをつけられず、存在しない魔法の杖を探し続けてしまうのです。
行動するまでの閾値を下げるには、存在しない方法を探すことは非効率であると認識してみてください。
「1週間探しても見つからないなら自分で思考錯誤したほうが早い」という信念を持つことで、情報収集や計画段階から抜け出しやすくなります。
準備中:目標の挫折理由
ケース④:外注できずに仕事を溜め込む
効率主義者は、仕事を委託することに抵抗感を示す傾向があります。
自分を基準に相手の生産性を評価するため、委託するたびにストレスが生じるためです。
しかし、自分1人ではできることは限られており、忙しい日々に振り回されることになります。
新しいサービスを作る余裕もなくなり、近い未来にオワコンとして認識されるかもしれません。
効率化のために外注するときは、目先の生産性にこだわるだけではなく、自分のビジョンに向けた方法を模索してみてください。
「できるようになる→効率化する→空いた時間で新しい取り組みを始める」という個人事業主の基本的な戦略がまわるようになると、人生を理想的なものにできる可能性が高まります。
準備中:自分ビジネス
ケース⑤:仕組化が好きで泥臭い営業を嫌がる
起業家は仕組化が大好きです。
少ない労力で稼げて、空いた時間で好きなことができることに憧れない人はむしろ少ないでしょう。
しかし、本来仕組化は泥臭い営業やモニターの実施の後の工程です。
仕組化という言葉に惑わされて、ビジネスの土台部分であるリサーチや検証、営業などを蔑ろにするとかえって成果が出づらくなります。
まずは高く売れるサービスを作れるようになることを、重点的に極めることをおすすめします。
「仕組化=効率的」という認識は間違っていませんが、現状何に力を入れるべきかを見誤らないことが肝心です。
- 0→1:需要の強い商品を作る術を学ぶ、そのために大量行動
- 1→100:商品を少ない労力で売る術を学ぶ、効率化
★コストを見積ろう
スキルの習得や目標達成では、一般的に「できるようになる→できたことの効率化」のステップを踏むことになります。
しかし、早くマスターしなければと焦りやすく、基礎部分を蔑ろにして最高効率の最短ルートを模索しがちです。
よりよい方法を探すことは大切ですが、その結果かえって時間がかかってしまっては意味がありません。
「できるようになる」ための時間や費用のコストをあらかじめ見積り、最高効率を見つける必要性を今一度検討してみてください。
たとえよりよい方法を見つけるにしても、今ある方法を進めながら模索することをおすすめします。
準備中:大量行動
ケース⑥:持続が難しいグレーゾーンでお金を稼ぐ
目先の利益だけを求めると、持続が難しいグレーゾーンな領域でお金を稼ごうとしてしまいます。
エロ系や炎上系、詐欺に近い情報商材系などが該当するでしょう。
稼ぎやすいものにはそれなりのデメリットがあり、それを長期的目線で検討する必要があります。
「どうせ長生きはしないんだ」と自暴自棄にならずに、「結婚して100歳まで生きるとしたら」という条件のもと考えてみてください。
ただし、遠くの理想像だけを求めるのも、ビジネスに失敗する原因になります。
方法に潔癖になり、きれいに成功しようとしすぎて何も行動できなくなるためです。
危険なことをしたり、潔癖になりすぎたりしないためにも、一般的な成功者を調べて自分なりの致命傷となる基準を設けてみてください。
まとめ
効率主義は有効な強みですが、扱い方を誤ると行動量の減少や、他者との関係性が希薄になります。
「効率化=善」として捉えるのではなく、目的や状況ごとに何を効率化すべきかを客観的に判断できるようになりましょう。
効率化したいという衝動に駆られたら、以下の問いを自分に投げてみてください。
- 何のために効率化すべきなのか
- 何を効率化すべきなのか
- その効率化は本当に必要なのか
- それを効率化するとどんな違いが生じるのか