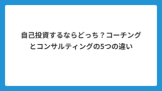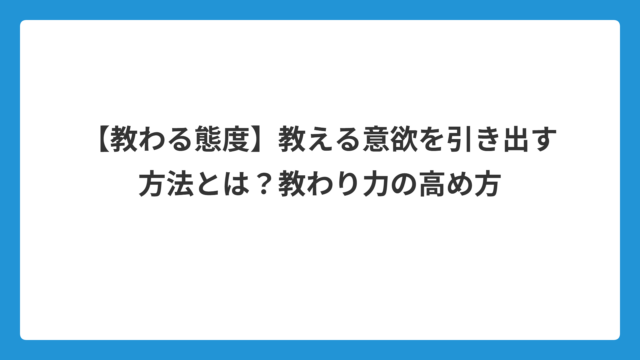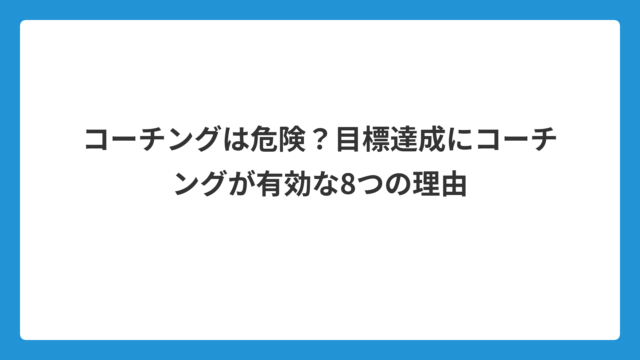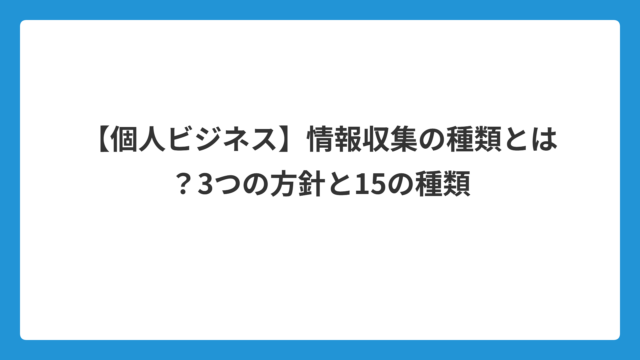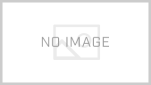高額な起業系コンサルを受講しても、かならず成果が出るわけではありません。
状況が受講前から何も変わらなかったという経験をした人も少なくないでしょう。
起業系コンサルの受講で現状が変化しない理由は、主に次の3つが考えられます。
- コンサルの質が低い
- クライアントの質が低い
- クライアントとコンサルの相性が悪い
この記事では、起業系コンサルを十分に活用するための「クライアントの質」についてお伝えしていきます。
「成果が出ない=コンサルが悪い」と決めつけず、自分の変われる部分を探してみてください、
起業系コンサルを上手に活用できない理由
ここでは、起業系コンサルを十分に活かせない3つの原因についてお伝えしていきます。
理由①:責任の押し付け
責任の押し付けとは、コンサルに任せれば万事解決だという思い込みによる振る舞いのことです。
「商品を買ったんだから成功させてよ」という態度であり、過ぎたお客様感覚だともいえます。
例.責任の押し付け理由
・客は神様だという思い込み
・コンサルは正解をすべて知っているという錯覚
・コンサルが思考も試行もすべてやってくれるという勘違い
コンサルを活用するには、コンサル側の責任と受講生側の責任を区別しなければなりません。
そして、受講生側の責任に関しては、コンサルに手伝ってもらうことはあっても、自分で果たす必要があります。
例.責任の区別
・コンサル側の責任:セールスで約束したものを提供すること
・受講生側の責任:意欲、主体性、宿題の実行、他者との交流など
コンサルは協働パートナーであり、あなたの目標に向かってあなたとは異なる役割を担う存在です。
すべての面倒を見てくれる親や奴隷のような存在と認識して、変な甘え方をしないようにしてください。
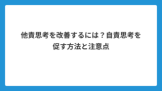
理由②:活用技術が未熟
起業系コンサルは、基本的にプログラム通りの行動のみをおこないます。
学校の授業のように、提供する内容や手順は固定的だということです。
- 提供する内容:何を教えるか、何をフィードバックするか、どうやって成長を促すか
- 提供する手順:何から教えるか、どこから確認するか、どの順番で成長を促すか
しかし、これは個別化された支援とは異なるため、必ずしも自分に適しているとは限りません。
学生時代の塾や自習のように、何かしらの対策をして一般化されたプログラムにおける不足分を補うことが必要です。
例.対策
・支援を要請する
・ニュアンスを汲み取る
・分からないことを尋ねる
この不足分を補うための働きかけのことを、起業系コンサルの活用技術と呼びます。
学ぶことが上手な人と下手な人の違いであり、同じ講師からどれほど成長できるかを分けるポイントです。
また、コンサルと関われる時間には限りがあります。
限られた時間のなかでどんな支援をしてもらうとよいのかを検討するためにも、「自分だけで解決できること」と「コンサルがいなければ解決が難しいこと」を区別するようにしてください。

理由③:そもそも課題が異なる
起業系コンサルも薬と同様に、特定の課題に対してのみ効力が発揮されます。
そのため、停滞している理由がコンサルの専門性と異なるならば、まったく変化が起きず時間を浪費することになるでしょう。
例.異なる課題による停滞
・目標:私は自分ビジネスで月30万円を稼ぎたい
・現状への認知:稼げないのはやり方がわからないからだ
・コンサルの専門性:稼ぐためのノウハウを提供できる
・結果:ノウハウを教わったのに何も変わらなかった
・真の課題:ノウハウも足りていなかったが、失敗することが怖くて私は動けないんだ
主な課題は「方法を知らないこと」「技術が低いこと」「実行できないこと」に分けられます。
ボトルネックとなる真の課題を明確にしてから、高単価商品を購入するようにしてください。
- 方法を知らない:何から取り組めばいいか分からない、成果に影響する要素や流れが分からない
(例.起業で稼ぐために何をすべきかが分からない) - 技術が低い:質や速度が成果を得るための条件に至っていない
(例.文章は書けるが、コンバージョン率の高いステップメールが書けない) - 実行できない:「やるべきこと」「やったほうがよいこと」が分かっていながら行動できない
(例.仕事に取り組めない。目指すべき地点が分からない。失敗が怖くて動けない。試せない)
また、「成功できないこと」と「歩みが止まっていること」は異なります。
現状をこの2つで区別してから課題を探ることで、より核心的な課題を見つけられるでしょう。
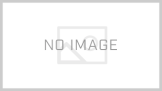
起業系コンサルにおける受講生側の責任
ここでは、受講生側にある4つの責任についてお伝えしていきます。
起業系コンサル受講後は、これらが自己責任だという前提をもって活用するようにしましょう。
責任①:意欲
意欲とは、俗にいうやる気やモチベーションのことです。
小学校の教師とは異なり、コンサルは「どうやったら受講生が意欲的になってくれるか」なんてほとんど考えません。
そもそもコンサルの専門性はビジネスであって意欲を出させる技術を持ち合わせていないため、わざわざ気にかける人が多くないのです。
- 意欲を他責にする受講生:私がやりたいと思えるように教えてよ、関わってよ
- 意欲を自責にする受講生:コンサルからは必要な情報さえ受け取れればいい、それを生かすも殺すも自分次第だ
高単価商品でも低単価商品でも、購入しただけで満足してしまい意欲が失われることがあります。
取得した情報をほとんど確認せず、宿題も手抜きをして、質問会にも参加しないという有様になってしまいます。
そんなやる気のない状態から抜け出すには、基本的には自分でどうにか足掻くしかありません。
いつか誰かがやる気を出させてくれると他責にしていては、いつまで経っても現状から抜け出せず、それどころか泥船に乗り続けることになるでしょう。
- 受講前のやる気:今の不安を解消したいから商品を購入しよう!
- 受講後のやる気:商品を購入したからよくなるはずだ。私ががんばる必要はない!
購入前の意欲を購入後も継続させるには、「意欲の向上」と「意志力を節約するための仕組化」が重要になります。
いずれにしても一朝一夕に得られるものではないため、意欲を課題だと認識して徐々に解消してみてください。
- 意欲の向上:目的や目標設定、報酬の多岐化と実感
- 意志力節約のための仕組化:習慣化、環境づくり、意味づけ、葛藤との折り合い
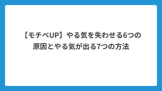
責任②:交流
交流とは、コンサルや他の受講生と積極的に関わることです。
ただし、イベントにただ参加するだけでは意味がありません。
一番前の席で授業を受けるような主体性が重要であり、機会を十分に活用する意気込みが大切です。
- 受動的:話しかけられるまで待つ、質問すべきことが分からない、言われたことだけをやる
- 主体的:自分から話しかける、質問すべきことを見つける、言われたことだけでなく+αの行動をする
交流を最大限に活用するには、イベント前と後における変化を明確にしてから参加することが有効です。
また、一回ごとのイベントの費用を計算して、参加前にそれを確認するとよいでしょう。
- イベント前後の変化:目標達成するためにこのイベントで得たいものとは?
- イベント費用の確認:「これは1回〇万円のイベントだ」と認識すること
情報を得ることよりも、むしろ成功者や同じレベル帯の人と接することに価値はあります。
慣れ合いは必要なく、自分の目標においてどういうメリットがあるのかを言語化してみてください。
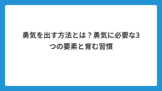
責任③:実行
起業系コンサルでは、一般的に効果的とされる方法を学べます。
しかし、学んだからといってできるようになるわけでも、細かなニュアンスまで把握できるわけでもありません。
だからこそ実践して、技術レベルを上げたり、自分に合うように方法を調整したりすることが重要になります。
- 技術レベルを上げる:量をこなして質を上げる
- 方法を調整する:自分とコンサルの違いに対する調整
稼ぐためには実行はかならず必要な工程ですが、ほぼ確実に最初の10回は失敗するものです。
また、初めての挑戦であるため、1回ごとに非常に大きな労力を費やす必要があり、先延ばしの原因になります。
そのため、「情報だけ取得して実行を疎かにしてしまう受講生」は全体の半数を超えていると言っても過言ではないでしょう。
例.実行の阻害要因
・青芝現象:もっといい方法があるだろう、他のことのほうがラクそう/楽しそう
・意欲の消失:何のために頑張る必要があるんだろう、働く意味って何だろう
・失敗する恐怖による停滞:失敗したらバカにされる、教わった方法では失敗するだろう
・めんどくさい、先延ばし癖:締切ギリギリじゃないと動けない、寝不足で作業に取り組めない
・完璧主義による下書きの量産:もっとちゃんとしたものを作らなきゃ、完璧にできるようになってからリリースしよう
教わったことを実施するだけですが、強制力のない個人事業主にとっては非常に難しいことです。
実行への抵抗感を抱いたら、その抵抗感の正体を見極めて対処するようにしてください。
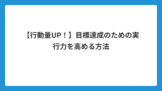
責任④:疑問と解消
教わった内容を実行することは大切ですが、それだけでは大きな成果を得ることが難しいです。
起業系コンサルは指導の専門家ではなく、また受講生の状態を細かく把握しているわけではないためです。
- 指導の専門家ではなく:ニュアンスを正しく伝えられていない可能性がある
- 状態の把握不足:受講生の「やったけど失敗した理由」はコンサルには分かりづらい
教わった内容がすべてではないという前提を持ち、「分かったこと」と「分かっておらず理解する必要があること」を区別するようにしてください。
そうして自身の状態を認識して、上手くいかない理由を見つけ、どうしたらいいのかと疑問を持ち、それを解消するためにコンサルと協働しましょう。
- 分かったこと:教わって理解できたこと、やってみてなるほどなと思ったこと
- 理解する必要があること:教わったけどイメージできないこと、やってみたけど分からなかったこと
疑問を持つこと、そしてその疑問を解消するために働きかけることは受講生の責任です。
起業系コンサルは尋ねたら教えてくれますが、尋ねない限りは個人的な課題に関して何も教えてくれません。
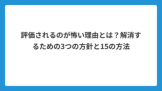
起業系コンサルの活用方法
塾に行ったからといって誰もが学力を上げられるわけでないのと同様に、起業系コンサルを受講したからといって現状が必ずしも改善されるわけではありません。
活用するスキルが低いと、どれほど質の高いコンサル商品であっても、多くを学習できないからです。
ここでは、起業系コンサルの活用方法についてお伝えしていきます。
自分に必要な支援方法を明確にして、コンサルにその支援をして欲しいと提案できるようになりましょう。
活用①:環境提供者
がんばるための仕組みの1つとして、コンサルを活用できます。
学校や塾の先生のような、自習室で怠けないための存在として認識できるということです。
また、コンサル側も受講生の意欲を出してもらうための工夫として、さまざまな施策をおこなっていることがあります。
例.コンサルによる環境提供
・宿題の管理:どれほど実施したかを確かめる
・仲間との居場所提供:お互いの進捗報告、モチベ管理
・先ゆく人として提示:「私もこうなりたい」と感じさせて受講生の意欲を高める
「次の会では〇〇まで進んだと報告できるようにがんばろう!」というように、自身を動かす動機の1つとして扱ってみてください。
また、褒められたらがんばれる人は、コンサルや同期にそのことを伝え、そのように接してもらうとよいでしょう。
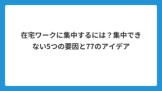
活用②:情報提供者
もっとも一般的な活用方法は、情報提供者です。
起業で成功するために必要な知識を教えてもらう存在としてコンサルを活用します。
例.提供する情報
・人脈
・戦略
・やり方
・考え方
・マインド
・成功要因
・押さえどころ
・業界の一般常識
コンサルを雇うときは、たいてい分からないことがあり、それをショートカットして知りたいときです。
自分で調べたり、思考したり、試行したりする手間や時間をお金で買う感覚なので、コンサルを情報提供者として活用することは難しくありません。
ただし、コンサルを雇ったからといって、何もせずに欲しい情報が手に入るとは限りません。
自分に必要な情報を得るためには、「必要な情報を具体的に理解する」「情報を引き出す技術がある」の2点が重要になります。
- 必要な情報を具体的に理解する:私はどんな情報が不足しているからうまくいかないのだろうか
- 情報を引き出す技術がある:私の知りたい情報をどう質問すれば伝わり教えてくれるだろうか

活用③:ロールモデル
ロールモデルとは、お手本にしたい人物のことです。
理想の自分像に似た人物、または理想の地点に近い人物がロールモデルになり得ます。
例.ロールモデルから真似ること
・外見:服装、髪型、振る舞い、働き方、暮らし方
・内面:考え方、判断基準、葛藤の解消方法、意味づけ、肯定の仕方
起業系コンサルは、コンサルというよりも先ゆく先輩というイメージが近いです。
そのため、ロールモデルとして活用しやすく、一旦の目指したい目標として活用できます。
ただしロールモデルとして活用するならば、その人物の外見と内面のどちらも模倣するようにしてください。
バランスが大切であり、そのバランスが崩れた状態ではかえってうまく回らなくなるかもしれません。
まずは自分で判断せずに真似てみて、それから必要か必要でないかを取捨選択するとよいでしょう。
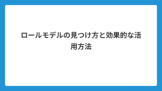
活用④:ペースメーカー
ペースメーカーとは、前に進むテンポ感の基準となる人です。
「このぐらいの速度で走るもんだよ」という基準になり、自分が遅いのか速いのかが分かるようになります。
例.ペースメーカーによる目印
・進捗スピード
・判断スピード
・目標の達成速度
・目標の更新速度
・目標の修正速度
・タスクの実行スピード
・期間あたりのタスクの実行量
ペースメーカーの存在は、主に「締切」と「心の安寧」として役立ちます。
自分1人ではだらだらと作業をしてしまったり、焦りにより不安が生じて空回りしたりするため、個人事業主においては重要な役割だといえるでしょう。
- 締切:いつまでに何を終わらせどこに辿り着いていればいいのか
- 心の安寧:今のスピードは妥当なのか、このルートは適切なのか

活用⑤:フィードバッカー
フィードバッカーとは、自分の状態を客観的に知らせてくれる人のことです。
勉学におけるテストと同様であり、自分だけでは分からない情報を教えてもらえます。
例.フィードバック内容
・目的や目標のズレ
・現在の熟達度合い
・躓いている現在の課題
・このままだとどうなるかの予測
・何をしようとしているのかという仮説
もっとも分かりやすいコンサルからのフィードバックは、添削されることです。
自分の成果物に対して、何が良くて何が悪いのかをフィードバックされ、さらにどう修正しようかという提案が加わることで、一段とよいものに仕上げられるでしょう。
ただし、フィードバックは別料金であったり、希望者のみのコンテンツだったりすることも少なくありません。
もしフィードバック込みの商品であったとしても、主体性をもってたくさん受け取るように働きかけることをおすすめします。

起業系コンサルの活用するための心構え
ここでは、起業系コンサルを十分に活用しやすくなるための心構えについてお伝えしていきます。
心構え①:受講理由を持ち続ける
最も大切な心構えは、コンサルを受講した理由を維持することです。
受講理由が失われると、主体性が欠けて歩みが止まったり、コンサルや同期の足を引っ張ることが目的になったりします。
例.受講理由
・現状:受講前はどんな状態だったか
・目的:何を実現したいか、どうなりたいか、どうありたいか
・目標:どんな数値目標を達成したいか、目的を実現するための要件
・課題:目標を達成できない理由は何か、何に躓いているのか、何が問題か
・仮説:コンサルを受けるとどうなるのか、それはなぜか
受講理由を維持することは、とても難易度の高いことです。
入学や入社などの前後を考えれば分かりますが、過去にそうしようと決めたことは時間とともに忘れ去られてしまいます。
コンサルにおいても目的を維持できるのは1カ月ほどが限界であり、忙しさやストレス、復讐心や嫉妬などに振り回され、簡単に見失ってしまうのです。
例.男女交際
・交際前:この人と〇〇だから付き合いたい!たくさん思い出を作って幸せになるんだ!
・交際後:めんどくさいからデートは年に3回程度でいいや、それより節約しよう
受講理由を維持するためには、「受講理由を思い出すこと」と「受講理由を修正すること」の2つの対策が有効になります。
自分1人では難しいときは、励ましあえる仲間を見つけて、定期的に報告会を開催するとよいでしょう。
- 受講理由を思い出す:毎日思い出す機会を設ける。理由をメモして読み返すなど
- 受講理由を修正する:このまま進むことにおける違和感と折り合いをつけた目的や目標に修正する
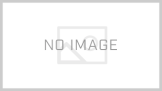
心構え②:誰よりも早く量をこなす
起業系コンサルは、「成果が出やすい受講生」を贔屓する傾向があります。
自分を信用してくれる人を好きになるものであり、やる気を持っている人を応援したくなるものだからです。
また、「成果を出した受講生がいる」という結果はコンサルにとっての最高の成果物であり、次の売上につながる情報でもあります。
- 成果が出そうな受講生を見つける
- その受講生を徹底的に支援する
- 受講生が成果を出す
- 成果が出たと公表してファンを増やす
よりたくさんの支援をコンサルから提供されるためには、「成果が出そうな人だ」と認知されることが重要です。
そのためには、言われたことをこなすスピード、試行錯誤する量を誰よりも早く多くすることが有効になります。
- スピード:宿題を渡されてからすぐに取り掛かりフィードバックをもらいにく
- 量:PDCAを他者が1回転している間に、自分は何回も回して質を上げる
この振る舞いに、才能なんてものは必要ありません。
誰にでもできることですが、ほとんどの人がやらない当たり前の努力です。
そもそも、このぐらいの意気込みがなければビジネスで成功することは難しいため、その場合はまだ自己投資する段階ではないでしょう。
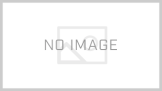
心構え③:歩み寄るような態度で教わる
起業系コンサルから指導を受けるときは、教わる技術が重要になります。
より個別化された悩みの解消をするときは、学校の授業のような一方的な情報提供だけでは不足するためです。
お互いに歩み寄り、すり合わせながら足りない部分を補わなければなりません。
- 一方的な情報:どうすべきか、どんな流れが一般的か、多くの人に当てはまる内容や論理
- すり合わせが必要な情報:今の課題は何か、本当は何に躓いているのか、何を試すべきか
コンサルは指導のプロではなく、また学校とは異なる答えのない題材を扱っているという前提を持ちましょう。
分からない部分は分からないと伝え、自分の考えを提示し、違いを教わるようにしてください。
個人に最適化された支援を受けるには、まずは自分から歩み寄る必要があります。
「お金を払ったから教えてくれるだろう」というマインドは捨て、目標を達成するためのパートナーとしての関係を築くことをおすすめします。
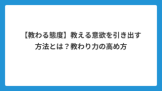
心構え④:まずは言われたとおりに実行する
もっとも自己投資を無駄にする行為は、コンサルからの宿題を実施しようとしないことです。
情報を得ても実施しないのであれば、日常は変わらず延長線上の未来から抜け出せないでしょう。
- 宿題を実施しない:やろうともしない、無駄だと考える、他に優先順位の高いものがある
- 宿題を実施できない:やろうとしても動けない、やったけれど失敗した
実施しないよくある理由は、方法の妥当性を自分が判断できると信じてしまうことです。
しかし、成功したことがない人が妥当性を判断できるわけもありません。
また、現状維持を正当化しようとその宿題は誤りだと決めつけることもあります。
- 方法の妥当性:この方法が自分の期待に沿うものなのか、理想に近づけるのか
- 現状維持の正当化:「やりたくない」が先にあり、その理由付けとしての失敗可能性の高さ
実施しないときは、「なぜ実施したくないのか」「何が無駄なのか」を言語化してみてください。
自分が持つ期待とその方法による結果の差分を明確にすることで、客観的に検討できるようになり、とりあえずやってみようと考えやすくなります。
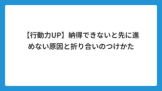
まとめ
起業系コンサルを最大限に活用できないのは、自分に理由があるからかもしれません。
よくあるコンサルで失敗する理由は次の3つです。
- 責任の押し付け
- 活用技術が未熟
- そもそも課題が異なる
起業系コンサルを雇うときは、「先人で優秀だが、教えるのはあまり上手くない人」という前提を持ちましょう。
その人から上手く支援を受けようとすることで、コンサルを最大限に活用できるようになります。
ただし、そもそも自分の課題が異なる場合は、他の自己投資が必要かもしれません。
コンサルの商品を買うときは、かならず自分が真っ先に解消すべき課題を明確にするようにしてください。