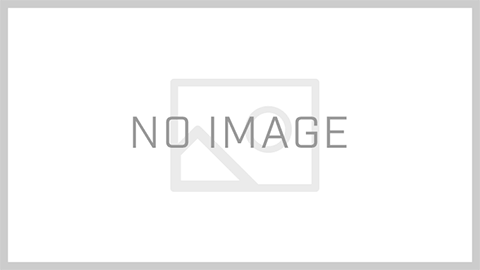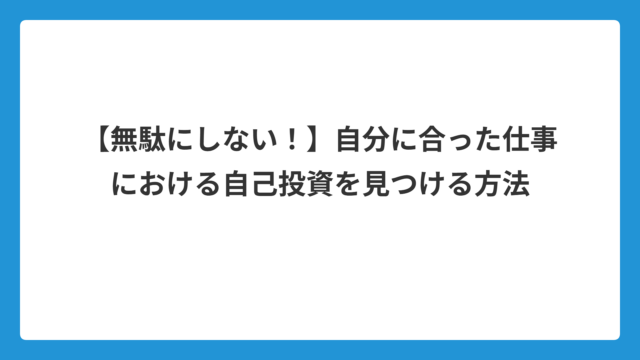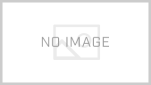オリジナル商品を作ったときに悩むポイントの1つが、価格設定です。
価格は売れやすさや顧客満足度の変数であり、どうしても慎重になってしまう人は多いのではないでしょうか。
この記事では、妥当な価格を設定するための方法についてお伝えしていきます。
商品の値段をつけることに抵抗感がある場合は、ここで紹介する情報をもとに価格設定してみてください。
妥当な価格の設定方法
ここでは、妥当な価格を設定するための手順についてお伝えしていきます。
手順①:相場を知る
まずは、次の2つの相場を調べます。
- 同じ変化に対する商品の価格:一般的にはいくらで売られているのか?
- 付けたい価格帯の商品と教育の内容:何があると高価格で売れるのか?
商品は自由な価格で売ってもよいのですが、一般的な価格帯から離れるほど怪しさが増していきます。
ターゲットと同じ肌感覚を持つためにも、競合調査をしっかりとおこないましょう。

手順②:お客様の判断基準を分析する
お客様の判断基準とは、商品の購入を決める最も重要視する要素のことです。
判断基準は主に次の2つに大別されます。
- 安さ:他の販売者に比べて安いほど購買意欲が高まる
- 確実性:確実な変化を起こせるという確信を持てるほど購買意欲が高まる
自分のターゲットがどちらの判断基準を重視するのかを分析してみてください。
”安さ”を重視するお客様が多いのならば、「価格やお得感」が重要になるでしょう。
一方で”確実性”を重視するお客様が多いならば、「競合よりも高い有効性」が重要になります。
例.確実性を重視するお客様の特徴
・猶予がないこと:短期間で成功させなければならない
・予算がないこと:他の商品も高額なものばかりで何を選んでも1つしか購入できない
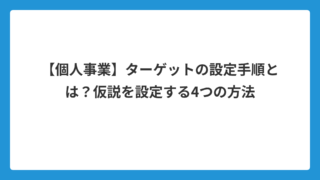
手順③:値付して売ってみる
ターゲットの判断基準をもとに、一般的な相場から離れすぎない程度の価格をつけてみましょう。
- 安さ重視:一般的な相場から高くなりすぎないように値段を抑える
- 確実性重視:期待感を持たせるために値段を高めにつける
値付けは、自分がプレッシャーを感じるかどうかが1つの基準になります。
売ることへの責任感を持てないほど安く値付けすると、「商品を売る=自分が損する」と感じてお客様に正しく向き合えなくなるためです。
安くする理由がない限りは、勇気を振り絞って高めに値付けをするようにしてください。
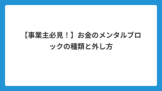
手順④:売れ行きと満足度で価格調整する
実際に売ってみることで、さまざまな情報が得られます。
その情報をもとに価格調整をするかを検討していきましょう。
例.売ることで得られる情報
・売れ行き:どれほどの打率で売れているのか
・満足度:購入者はこの価格に満足しているのか
ただし、安くすればするほど売れるわけでも、お客様が満足するわけでもありません。
得られた情報と価格の関係性は、慎重に分析するようにしてください。
- 売れるための施策:ターゲットを変える、認知を広げる、教育内容を見直す、特典を増やす
- 満足度を高めるための施策:商品内容を修正する、フォロー回数を増やす
今の値段で売れなかったとしても、価格下げは最後の手段にすることをおすすめします。
ビジネススキルを高める最も効果的な方法の1つは、「可能な限り高い価格で売るにはどうすべきか」と頭を悩ませ試行錯誤を続けることだからです。
★不満者への補償
高価格で売る勇気を持つためにも、商品を買って不満を抱く人への補償方法を決めておくことをおすすめします。
具体的には、全額返金やフォロー期間を延ばすなどが挙げられます。
ただし、「最悪お金を返せばいいや」と楽天的にならないようにしてください。
その態度はお客様にも伝わりやすく、「責任感のない事業者」という口コミが広まる原因になります。
ビジネスを続けていくためにも、お客様を幸せにすることに誠心誠意努めましょう。
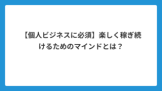
価格を決める3つの根拠
お客様は何を見てその価格に妥当性を判断しているのでしょうか。
ここでは、価格の根拠として活用される要素についてお伝えしていきます。
根拠①:原価
原価とは、その商品を提供するまでに必要な費用のことです。
ビジネスに精通していない人や、商品自体に価値を見出そうとする人ほど原価を重視します。
例.原価を重視
・素材は安いのだから外食はコスパが悪い
・話を聞いてもらうことにお金を払うなんてばからしい
・これだけの人員を導入しているのだからこの金額は妥当だ
原価を重視するタイプの人は、コストパフォーマンスの高い商品を好む傾向があります。
財布のひもが固い状態であり、薄利多売の戦略を取りづらい個人事業主にとっては、相性の悪い客層だと言えるでしょう。
ただし、「自分の価値」が高く認識されている人にとっては、高価格をつける都合のよい根拠になり得ます。
例.一般的な価値
・普通の会社員の意見を聞くのに10万円はばかげている
→一般的な会社員の日給は1~3万円。
・大谷翔平と1時間談話できるなら100万円でも安い
→大谷翔平は日給換算すると2千万円越え。
根拠②:変化
変化とは、商品を買って活用することで生じる恩恵のことです。
商品を買う目的とその効果性や付加価値に対して、どれほどお金を払うかを決めます。
例.変化を重視
・3ヶ月で確実に痩せられるなら30万円は安い
・1年かけても大して痩せられないなら1万円でも高い
・怠け者の私が毎日意欲的に仕事できるようになるらな100万円は安い
ビジネスに精通していたり、自分の課題に深い理解があったりする人ほど、現状と商品購入後の未来におけるギャップから価値を判断します。
厚利少売の戦略が有効になる個人事業主にとっては、変化で判断しようとする客層は相性がよいと言えるでしょう。
例.変化における変数
・変化の対象:どんな状況からどんな状況に変われるのか
・変化の対象者:誰に有効に働くのか
・変化の大きさ:どれほど大きな変化を起こせるのか
・変化の確実性:何割ぐらいの人が変化を起こせたのか
・変化までの期間:変化までの期間は長いのか短いのか
根拠③:希少性
希少性とは、どれほど類似商品が存在するのかということです。
希少であるほど値段が高くなり、ありふれているほど価格競争が起こります。
例.希少性を重視
・同じ性能なら安いほうを選ぼう
・他では手に入らないからいくらでもお金を支払う
・信用している人から商品を買えるなら多少高くてもいい
ただし、自分が必要とする希少性にしか価値を見出しません。
個人事業主の場合は、主に以下の希少性が価格に反映されやすいでしょう。
- ニッチであること:他の商品よりも私にフィットしている
- 供給が少ないこと:他にも同じ商品があるかもしれないが見つけづらい
- 信頼されていること:他の販売者よりもこの販売者から商品を買いたい
押さえておきたい価格設定のポイント
ここでは、価格設定をするときに押さえておきたい前提についてお伝えしていきます。
ポイント①:価格帯で客層が変わる
安いほどたくさん売れるとしても、必ずしも安売りをすべきであるとは限りません。
価格帯で客層が変わり、いくらで売るかはその後のビジネスに影響を及ぼすためです。
実際価格帯が安いほどクレームが多いと言われており、お客様のフォローで忙しくなることもあります。
フォローに失敗すればアンチが増え、ビジネスを継続することが困難になるでしょう。
例.価格帯による客層
・低価格帯:お試し、コスパ重視、予算が少ない、現状への危機感が低い
・高価格帯:本気、変化重視、予算が多い、現状への危機感が高い
低価格帯で売りたくなる欲求は、主に次の3つの信念から生じています。
- 安いものほど売れやすい
→安いから売れるとは限らない。 - 高いほど大きな責任を抱えなければならない
→商品を売る以上価格に関係なく責任を持つべき。 - お金を持っていない人は大金を払えないはずだ
→現状を本気で変えたいときは借金してでも大金を払う。
価格設定は「売れやすさ」だけではなく、「客層」にも影響を及ぼすことを押さえておきましょう。
価格帯をずらすことでターゲットとしている客層から離れるのであれば、そこに何らかの工夫が必要になります。
★ターゲットに売るための施策
・高価格帯の客層に安く売りたい:売る人を絞る仕組みを作る(常連限定の販売など)
・低価格帯の客層に高く売りたい:信用される、保証する、現状維持によるリスクを教育する
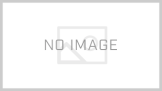
ポイント②:販売目的によって価格を変えよう
厚利少売の戦略を採用しているからといって、必ずしも高単価商品の販売がよいとは限りません。
販売する目的は主に3つあり、その目的によって価格を柔軟に変えることこそが大切だからです。
★販売する目的
・バック(利益):高い価値でも買ってくれる少数に売り、余力でフォローを充実させる
・フロント(信用):低い期待の購入者に大きな成果を与えることで信用につながる
・モニター(検証):ターゲットへの有効性や満足度の計測
信用を作ることが目的なのであれば、安く売ることも手段として有効です。
低価格商品は変化への期待を下げるため、成果とのギャップを大きくすることができます。
ギャップが大きいほど満足度が高まり、「この人の商品は間違いない!」とファンとなって高単価商品への購買意欲も強まるでしょう。
目的次第で価格の善し悪しが決定するため、値付けに迷ったらその商品を販売する目的を検討してみてください。
目的ごとに価格を割り切れない場合は、自分の中にある恐れや焦りと向き合うことをおすすめします。
例.目的ごとに価格を割り切れない
・モニターだから無料で提供すべきだ
・モニターだけど高単価で提供したい
・フロントだけど安く売ることはもったいない
・バックだけど価格を高く設定することが怖い

ポイント③:1万円で売れるなら30万円でも売れる
価格の根拠を紹介しましたが、根拠と価格は比例関係にあるわけではありません。
比例ではなく指数関数的であり、一定の価格帯を超えると些細な根拠の違いで価格が大きく変動するようになります。
例.価格と根拠の指数関数的な関係性
・ランチ:1千円以内なら10円単位で気にするが、2千円と3千円では大して変わらないように感じる
・自己投資:1万円で売られている商品を50万円で売ったらむしろ満足度が上がることもある
この関係性を理解しないと、価格に比例して商品の質や量を上げようとしてしまいます。
しかし、質や量はすぐ天井にぶつかり、「これ以上は価格を上げられない」と行き詰まってしまうのです。
大きく価格が上がりはじめる転換点は、「原価」から「変化」への目的の変更です。
商品購入で得られる付加価値に焦点を当てるように教育できれば、お客様の目的が変わり商品の内容に関わらず高い価値を見出してもらえます。
- 原価:コスパのよいものを買いたい、他の方が安かったと後悔したくない
- 変化:実際に変われるものを買いたい、買ったのに変われなかったと後悔したくない
例.変化を目的にするための教育
・最高の未来を伝える:この商品を買ったら「家族と楽しい思い出を作れる」ようになる
・延長線上にある最悪の未来を伝える:このままだと「家族との関係性が悪化して不幸」になる
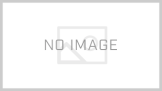
ポイント④:何に価値を感じるかは人によって異なる
価格設定をするためにモニターを実施すると、必ずと言ってよいほど「この商品にそんな高額を払えない」という意見をいただきます。
しかし、そうした商品価値に対する意見に関しては、慎重に検討するようにしてください。
何に価値を感じるかはその人の嗜好や状況によって異なり、たまたまその人が価値を感じない人だったという可能性があるためです。
例.価値の感じ方
・状況:砂漠での水の価値は非常に高い
・嗜好:チヤホヤされたい人はキャバクラに高い価値を感じる
そもそも興味がなかったり、すぐに変化を必要としていなかったりする人における価格への意見は、基本的にスルーしてよいでしょう。
そのような人たちからは、「価格」ではなく「変化量」に関する意見をフィードバックしてもらうことをおすすめします。
- 価格:いくらの価値がありそうか?この価格で納得できるか?
- 変化量:商品を試してどれほど変わったか?どれほどの期間を要したか?
価格に対する意見に関しては、「変わりたいのに変われていない人」に尋ねてみましょう。
「現在の窮地から脱することに〇〇万円の価値はあるのか?」と質問することで、変化に関する妥当な価格を調べられます。
例.”変化”に関する妥当な価格
・交際経験ゼロから交際経験1人になることに100万円の価値はある?
・スキルゼロから安定して30万円を稼げるようになることに50万円の価値はある?

ポイント⑤:高く売れるかと満足されるかは相関しない
高く売れたからといって、お客様が満足するとは限りません。
売り方と商品内容は別の話であり、売り方によっては道に転がっている石ですら高額で売れてしまいます。
「よいものが高く売れる」とは限らないように、「悪いものが高く売れない」とも限らないのです。
- 高く売れる:期待を高める技術、価値を見出す人を見つける技術
- 満足される:提供物による成果とお客様の期待とのギャップ
→満足(期待<成果)、不満(成果<期待)
資金が底を尽きかけている事業者に多いですが、高く売ることばかりに注力しないように注意してください。
商品内容の充足を軽視していると、購入者は期待外れだと感じて悪評ばかりが広まってしまいます。
高く売れるようになるための施策は最後にやるべきことです。
まずは、お客様が確実に変化を引き起こせるように商品内容を作り上げましょう。
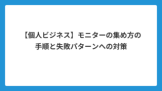
低価格をつけることのデメリット
個人事業主なり立てのときは、自分で作った商品を高く売りたくないという抵抗感が生じるものです。
ここでは、その抵抗感に抗うための「低価格で売ることのデメリット」についてお伝えしていきます。
低価格①:自転車操業になる
低価格で売るということは、薄利多売の戦略を取るということです。
しかし、薄利多売であるほど「販売」と「フォロー」に大きなリソースを注ぐ必要があり、たいていリソースが足りずに自分を犠牲にするようになります
- 販売:認知を広げる力弱く、よい商品であったとしても販売本数がすぐに天井になる
- フォロー:販売本数とフォロー量は比例関係。フォローが足りないと満足度は下がりクレームやファンの離脱につながる。関係性も深めづらい
安く売ることにはよい一面もありますが、自分を犠牲にしてまでおこなうことではありません。
もしも安く広く売りたいという場合は、まずは収益の柱となる事業を育ててから、薄利多売の事業に手を出してみてください。
例.安く広く売るメリット
・お客様が自分に合った商品を選びやすくなる
・困っている人が手軽に問題解決できるようになる
低価格②:クレームがつきやすい
低価格帯の客層は、変化することへの本気度が低い傾向にあります。
「自分が変わること」ではなく「商品の善し悪しを審査すること」に焦点を当てやすく、お得か否かで判断しようとします。
例.よくあるクレーム
・対応が悪い/遅い
・新しい知見ではない
・競合商品よりもコスパが悪い
また、不満の多くはフォローすることで解消できますが、薄利多売ではその余力がありません。
その結果、ますますお客様の不満は膨れ上がり、「この事業者は悪である」という流れが広まっていきます。
クレームを恐れるならなおさら、高価格帯の客層向けに商品を提供してフォローを徹底しましょう。
たしかな実績を得てから低価格帯の客層に商品を販売することで、ハロー効果によりクレームも抑えられるようになります。
低価格③:期待が下がり軽視される
低単価であるほど、その商品へのお客様の期待は低下します。
その結果商品を十分に活用しようという気になれず、実践することを先延ばしにしたり、上辺の情報だけを取得して次の商品を購入しようとしたりするのです。
- 低単価商品への態度:買ったけど放置してもいいや、安いし効果が低いだろう
- 高単価商品への態度:買ったからにはしっかり活用しよう、高かったし効果が高いだろう
お金目的のビジネスなら、売れるだけで幸せであり、お客様のその態度を気にしないでいられるかもしれません。
しかし、お客様のことを考え多大なリソースを払って作り上げた商品を、そんなぞんざいに扱われて喜べる人はそう多くないでしょう。
次第にビジネスをする意味が見失われていき、事業をすることに無力感を抱くようになります。
例.商品販売による報酬感
・お金:商品が売れた!これで欲しいものが買える!
・貢献:お客様が変われた!感謝された!
・重要感:自分のビジネスや生き方には意味がある!
本気で変わりたい人だけと接したいなら、高い価格設定こそがもっとも簡単にお客様を絞る手段です。
高い価格設定は利益が増えるだけではなく、自分を軽視するお客様に心をすり減らさないための予防策でもあります。
詐欺扱いされるよくある理由と対策
個人での商品販売は、どうしても詐欺扱いされやすいものです。
ここでは、詐欺扱いされないための対策についてお伝えしていきます。
詐欺①:第三者による介入
意外にも詐欺師と噂する人は、商品購入者ではなく全く関係のない第三者です。
正義感の強い人や嫉妬している人などが、高単価商品を売っている人を見つけて「この人は危ない」と周知します。
なかには自分の商品を売るために他者を酷評する人もおり、人気になるほど悪評が広まっていくものです。
例.よくある悪評
・売り方への批判:LINE誘導している事業者は危ない!
・未体験への批判:話を聞いてもらうだけで人は変われるわけがないのだから詐欺だ!
こうした悪評をゼロにすることはできませんが、可能な限りゼロに近づける対策をすることなら可能です。
具体的には、主に次の2つの方法が挙げられます。
- 実績で黙らせる:有名人のクチコミを得る、肯定的なクチコミやファンを増やす
- 商品自体を見せないようにする:限られた人にだけ商品を売る(公式LINEをプロフィールに書かないなど)
ターゲットを広げて情報発信をするほど、こうした批判者は増えていきます。
本当に困っている人だけに声が届くように、認知活動ではよりニッチな内容を発信するとよいでしょう。
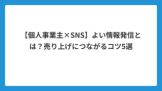
詐欺②:約束事と商品内容の不一致
約束事とは、販売者側が提供する商品内容のことです。
マーケティング活動によって、販売者とお客様における約束事の不一致が生じやすく、詐欺扱いされる原因になります。
例.約束事の不一致
・マーケティングによる宣伝文句:この商品を買えば毎月30万円稼げるようになる
・販売者目線:毎月30万円を稼ぐためのロードマップを提供する
・お客様目線:この商品さえ買えば実際にお金を稼げるようになる
・不一致:商品を買ったのに稼げない!買うだけで稼げるって言ったのに!!
マーケティングでは、現状と理想のギャップを解消できることを強調して購買意欲を高めます。
しかし実際の商品の多くは、現状と理想のギャップを作り出す課題の一部を解消するだけであり、他に課題を抱えている場合はギャップを解消しきれません。
その認識の違いを放置したまま商品を販売するとお客様の高い期待を下回ることになり、「詐欺だった」と烙印を押されます。
例.ギャップを解消するための課題
・理想:3カ月後に5kg減量する
・現状:運動習慣を持てずに痩せられない
・約束する課題:運動習慣を身に付きやすい環境の提供
・約束されていない課題:やる気を起こすことや成果の保証など
・詐欺扱いする言い分:この商品を買えばモチベーション高く痩せられると思ったのに!
この不一致を解消するためには、”夢”だけではなく”現実”も見せることが重要です。
具体的には、ロジックやプラン化、過程の困難さや難易度などを伝える必要があるでしょう。
- ロジック:この商品が有効に働く理由、有効に働かない理由
- プラン化:現状からどのような手順で理想にたどり着くのか
- 困難さ:そのプランを実行することはどれほど大変か
- 難易度:そのプランを実行するために必要なスキルや忍耐力、成功確率
”現実”を見せれば購入しようとするお客様は減りますが、そもそもその”現実”を知らずに購入するお客様は満足するはずもありません。
「”現実”を見てでも買いたい」というお客様に絞ったほうが、長期的にはお互いにとって得になります。
- お客様の得:覚悟をもって購入できる、自分に必要かを確かめられる
- 販売者の得:商品が効きやすい人だけに提供できる、肯定的なクチコミが増えやすい
商品を販売するときは、「約束できること」と「約束できないこと」を明確に区別してください。
「その商品の役割」が必要な人にだけ、商品を販売することをおすすめします。
詐欺③:価格を正当化できない商品内容
価格の正当化が難しいほど、次のように詐欺的な商品だという評価を受けます。
- パッケージだけリッチで内容は平凡
- 値段を釣り上げて情弱に売ろうとしているだけ
価格の正当性は、「購入前」だけでなく「購入後」でも引き続き納得できることが重要です。
購入後に価格を正当化できなくなるということは、宣伝文句が大言壮語だったことを意味します。
- 購入前の納得感:〇〇だからその値段なのか!それなら買ってみよう!
- 購入後の納得感:たしかによい商品だった!期待は裏切られなかった!
価格の根拠として「原価」「変化」「希少性」を挙げましたが、それは商品購入前の納得感だけに影響します。
購入後はそれらの根拠よりも、「購入を決めた期待に体感が上回ったか」が重視されるのです。
- 購入への納得感:先行く起業家の講座なのだからそのぐらいの値段が妥当だろう
- 購入への期待:この商品を買えば今ある悩みを解決できそうだ
- 購入後の体感:悩みが解決できたどころか計画が一気に進んだ(満足)、悩みは解決できず時間とお金の無駄だった(不満)
高級食材を使ったとしても、その料理がまずかったらクレームになります。
特に個人事業主の商品は内容が不明確であるため、商品の効き目が弱かったら詐欺扱いされてしまうでしょう。
詐欺扱いされないためにも、商品への期待と商品内容のバランスにこだわってください。
どんな期待で購入して、何をどれほどの質や量で提供すれば満足するのかを徹底的に分析することをおすすめします。
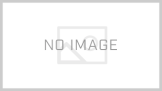
まとめ
価格を設定する手順は以下の通りです。
- 手順①:相場を知る
- 手順②:お客様の判断基準を分析する
- 手順③:値付して売ってみる
- 手順④:売れ行きと満足度で価格調整する
価格は売れやすさに影響しますが、価格を安くすれば売れるというものでもありません。
ビジネススキルを高めるためにも、「自分が少し高い」と感じる価格で売れるように、教育や商品開発に挑んでみてください。
「この商品をもっと広げたい」と思える商品を作れたのなら、少なくともアンチは極端に増えないはずです。
提供することに自信がないなら「商品開発」を、高く売れる自信がないなら「導線改善」を恐れずに優先することをおすすめします。